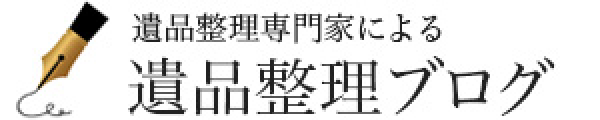遺品整理や生前整理では、処分に困ったり、悩んだりするようなものが出てくることがよくあります。
大きな家具や、大量の写真・アルバムなどがその代表ですが、それらのほかに困ってしまうのが、お札やお守りなどではないでしょうか。
いつからあるのか分からないようなものであっても、お札はお札。
神様からいただいたものだけに、変に捨ててしまえばバチが当たるような気がします・・・。
でも、自分で持つのも、ずっと保管するのも無理。
そこで今回は、神様に対して失礼のない、お札やお守りの正しい処分方法について見ていきましょう。
目次
お札やお守りの処分・返納方法は?

お守りやお札は、神社やお寺にある「古札納付所」などに納めます。
原則的に、神社のものは神社に、お寺のものはお寺にお返ししましょう。
神社やお寺に持ち込む
最も一般的なのは、神社やお寺に持ち込む方法です。
返納は、そのお札やお守りをいただいたところにお礼参りをし、お返しするのが基本です。
感謝を込めて返納しましょう。
しかし、遺品整理や生前整理で出てきたものには、どちらでいただいたものか分からない場合もありますね。
そういう時は、別の神社やお寺に持ち込むこともできます。
お寺の場合、宗派が違うお寺に持ち込むのは失礼にあたるので、注意が必要です。
神社の場合は、それほど神経質になる必要はありませんが、同じ神様を祀っているところなら、なおよいでしょう。
宗教や宗派が違ってもお札の処分を受け付けてくれる寺社もあります。
また、中にはそこでいただいたもの以外は受け付けていないというところもあります。
事前に確認しましょう。
お寺・神社に郵送する
旅先など遠方でいただいたお札やお守りは、郵送で返納できます。
宛名は「〇〇寺(神社)御中」、「○○寺 寺事務所御中」、「〇〇神社 社務所御中」などとします。
また、封筒に「お札(お守り)在中」と書き、お寺の場合は「焼納希望」、神社の場合は「お焚き上げ希望」と併記して郵送しましょう。
お礼の言葉などを一筆添えると、さらによいでしょう。
ただし、神社やお寺によって受け付けていないところもあるので、事前に確認しましょう。
どんど焼きに出す

全国各地で小正月に行われている行事、「どんど焼き」は、「才の神焼き」、「左義長」などともいい、お正月のしめ縄や門松、書き初めなどを神社や町内会などで燃やす行事です。
この際、古いお札やお守りも一緒に火にくべてお焚き上げすることができます。
どんど焼きは、その煙に乗って歳神様が天に帰っていくといわれています。
また、その火で使ったものを焼くのは、神様にお返しするという意味があり、お札やお守りも燃やしてよいとされています。
お焚き上げの依頼先や費用の相場・場所別のメリット・デメリット
自分で処分する
花火ができる程度の庭がある家なら、自分で処分することもできます。
その場合、お札やお守りを直に火の中に入れるのではなく、ひとつまみの粗塩と一緒に白い紙や半紙にくるみ、お札やお守りに感謝を込めてから焼却しましょう。
お清めのやり方は、まず、白い紙を広げ、その上にお札やお守りを置きます。
塩をつまみ、左→右→左の順にふりかけ、そのまま紙で包みます。
ただし、木製のものや、燃えにくい素材のもの、量が多い場合はNGです。
また、バケツに水を用意し、火事には気を付けましょう。
また、近隣の家で窓を開けていないか、洗濯物を干していないかにも気を配りましょう。
アパートやマンションで庭がない場合は、自治体の回収に出すこともできます。
この場合も、お札やお守りを粗塩で清め、白い紙や半紙にくるんでから出しましょう。
また、自治体のルールに従って分別します。
いずれにしても、感謝の気持ちを込めて処分することが大切です。
お焚き上げ専門業者に依頼する
お札やお守りの処分に困った場合、お焚き上げを専門に請け負う業者に依頼する方法があります。このサービスでは、業者が提携しているお寺や神社にお札やお守りを集め、合同供養の後に丁寧にお焚き上げを行います。
利用方法は非常に簡単です。多くの業者ではウェブサイトや電話から申し込みができ、専用の封筒や箱に処分したいお札やお守りを入れて送るだけです。少量のお札やお守り一つからでも受け付けている業者がほとんどで、気軽に利用できます。
料金は業者によって異なりますが、基本料金に加えて数量や重量に応じた料金体系になっていることが多いです。一般的には1,000円〜3,000円程度からのサービスが提供されています。
また、お焚き上げ専門業者は神道や仏教などの宗派を問わず対応していることがほとんどです。どの神社やお寺で授かったものでも、適切な作法で処分してもらえるので安心です。処分後には証明書を発行してくれる業者もあり、供養が正しく行われたことを確認できます。
遺品整理業者に依頼する

古いお札やお守りの処分は、遺品整理業者に依頼することもできます。
遺品整理の際に、一緒に処分してもらえます。
遺品整理業者の場合、他の人のお札などと一緒に供養する合同供養のほか、自宅に提携の僧侶を呼んでお経をあげてもらう直接供養も選択できます。
その場合、お札やお守りだけでなく、故人の愛用品や日用品も同時に供養してもらえるというメリットがあります。
また、遺品整理業者の場合、自分たちで荷造り・発送をしたり、ものを運んだりといった手間がかかりません。
供養後の処分も全ておまかせできるので、手間や時間がかからないのも大きなメリットです。
古いお札の引き取り・処分はバスター七福神へ

古いお札の処分方法でお悩みなら、専門業者へのご依頼がおすすめです。
ゴミ屋敷バスター七福神は、全国で片付け・不用品回収を行う専門業者です。私たちは「暮らしの再生」や「心の整理」に寄り添い、多くの片付けをサポートしてきました。
主なサービスは、ゴミ屋敷・汚部屋の片付け、不用品回収、遺品整理、生前整理、ハウスクリーニングです。「実家が遠方」「急ぎで整理したい」などのご要望にも柔軟に対応します。
一軒家・マンション・団地など住居の形態を問わず、分別から搬出、清掃までワンストップで任せられるのが強みです。古いお札の処分も安心してお任せください。
バスター七福神・遺品整理のご案内をご覧ください。
御札を処分(納める)時の注意ポイント

神社やお寺で授かった御札(おふだ)やお守りは、一定期間が過ぎたら適切に処分する必要があります。これらは単なる紙や物ではなく、神様や仏様の力が宿る神聖なものとされているためです。一般的には神社の御札は1年、お寺の御札やお守りは納めた年の大晦日までが有効期間とされています。処分する際には「焼く」「納める」という表現を使い、「捨てる」という言葉は避けるのがマナーです。ここでは、御札を適切に納める際の注意点について解説します。
神社とお寺の御札は分けて納める
神社とお寺の御札は必ず分けて納めるようにしましょう。これは神道と仏教という異なる宗教の違いを尊重するためです。神社で授かった御札には神様が、お寺で授かった御札には仏様がそれぞれ宿るとされています。
神道と仏教では御札に対する考え方や扱い方が異なります。神社の御札は神様の依り代(よりしろ)として神様自身が宿るものであり、お寺の御札は仏様の教えや加護を表すものです。それぞれの宗教的な背景や意味合いが異なるため、混ぜて納めることは失礼にあたると考えられています。
また、神社とお寺では御札のお焚き上げの方法も異なることがあります。神社では「おはらい」という清めの儀式の一環として行われ、お寺では「供養」として行われることが多いのです。このような宗教的な作法の違いを尊重するためにも、御札は授かった場所に応じて分けて納めることが望ましいでしょう。
紙札を開封して中を見ない
紙で包まれた御札は、開封して中を見ないようにしましょう。これは神様や仏様への敬意を表す行為であると同時に、古来からの伝統的なしきたりでもあります。
御札の中には、特別な文字や印が記されていることがあります。これらは一般の人が見ることを想定されておらず、神職や僧侶といった専門の方々のみが扱うべきものとされています。むやみに開封して中を見ることは、神聖な力を損なう可能性があるとも考えられているのです。
また、御札には祈祷の際に込められた願いや祝詞(のりと)が宿っているとされています。その神秘的な力を保つためにも、授かったままの状態で大切に保管し、処分する際もそのまま納めることが大切です。開封せずに納めることで、神様や仏様への敬意を示し、御札に込められた力を最後まで尊重する姿勢を表すことができます。
郵送での返納の際には必ず事前に確認する
遠方の神社やお寺に御札を返納する場合、郵送という方法もありますが、必ず事前に受け入れ可能かどうかを確認しましょう。すべての神社やお寺が郵送での返納を受け付けているわけではないためです。
郵送を受け付けている場合でも、包装方法や送付先、必要な情報(住所や氏名、初穂料の同封など)について事前に確認することが重要です。神社やお寺によって郵送での返納に関するルールが異なるため、公式ウェブサイトで確認するか、直接電話で問い合わせるとよいでしょう。
また、郵送の際には御札を丁寧に包み、汚れや破損がないように配慮することも大切です。白い紙や和紙で包み、清潔な状態で送ることが望ましいとされています。これは御札に宿る神様や仏様への敬意を表す行為であり、心を込めて最後まで大切に扱うという気持ちの表れでもあります。
返納の際は、感謝の気持ちをお賽銭で示す
御札を返納する際には、お賽銭を添えて感謝の気持ちを示すことが望ましいとされています。これは一年間守護していただいた神様や仏様への感謝の気持ちを形に表す行為です。
お賽銭の金額に決まりはありませんが、一般的には新しい御札やお守りを授かる際と同程度か、それ以上の金額を奉納するとよいでしょう。これは「お礼」と「新たな御札を授かる際のお願い」の両方の意味を込めた行為です。
また、お賽銭を包む際には、白い紙や御札袋を使い、丁寧に包むことも大切です。お賽銭を直接手渡しではなく、賽銭箱に納めることで、神様や仏様への敬意を示します。感謝の気持ちを込めてお賽銭を納めることで、御札が持つ力への謝意を表すとともに、これからも変わらぬ加護を願う気持ちを伝えることができるのです。
神社やお寺での御札の返納は、単なる物の処分ではなく、神聖な儀式の一つです。マナーやしきたりを理解し、敬意を持って行うことで、神様や仏様との良好な関係を保ち、これからの健康や幸せを祈願することができるでしょう。
お札の寿命はどのくらい?

基本的に、お札やお守りの効力は、だいたい1年といわれています。
1年以上経つとご利益や効果がなくなるというわけではありません。
しかし、お札やお守りは持ち主の身代わりとして災厄を受けて不浄のものとなったり、人間界の気にさらされ続けて汚れたり痛んだりして、時と共に効果が薄くなるとされています。
そのため、通常は1年後に返納します。
たとえば、春に受けたお守りやお札は、翌年の春にお返しします。
初詣で受けたお札やお守りは、次の年の初詣で感謝を込めてお返ししましょう。
ただし、安産祈願や合格祈願などのお守りに関しては、1年経っていなくても、願いがかなった後にお礼参りをし、お返しします。
また、お寺のお守りの中には、1年以上持てるもの、一生持てるものもあります。
寺務所で確認してみましょう。
なお、どうしても取っておきたいお守りや、思い出のお守りは、無理に処分する必要はありません。
そのような場合は、そのお守りをいただいた神社やお寺に、お礼としてお賽銭を入れるとよいそうです。
古いお札を持ち続けるとどうなる?
古いお札を処分せずに持ち続けると、様々な影響があると言われています。まず、お札には神様や仏様の力が宿るとされていますが、その効力には期限があります。多くの場合、神社のお札は1年、お寺のお札は年末までが有効期間とされています。
期限を過ぎたお札は「お役目終了」となり、新しい御利益を受け入れる余地がなくなると考えられています。そのため、古いお札を持ち続けることで新たな福運や御利益が入りにくくなるとされています。
また、神聖なものである以上、粗末に扱うことは避けるべきです。古くなって破れたり汚れたりしたお札をそのまま持ち続けることは、神様や仏様への敬意に欠ける行為とも言えます。
適切な時期に丁寧に納めることで、感謝の気持ちを表すとともに、新たな御利益を受け入れる準備ができるのです。
お札(護符)とは?

生活に身近なお札やお守りですが、改めてその意味をおさらいしておきましょう。
お札
神社で神様から下賜されるもので、神札、守札、神符と呼ばれることもあります。
家庭の鎮守を願うためのもので、表面には神社名や祭神名が書かれています。
お札には紙製のものが多いですが、木製(木札)、金属製のものもあります。
また、紙製のもの1枚であることもあれば、折りたたんだお札を和紙に包み、神札を封印してあるもの(紙札)もあります。このような形のお札は、開封してはいけません。
お守り

お守り(守札)は、もともと陰陽道や寺院で作られたものでしたが、のちに神道にも取り入れられました。
お札が家庭の鎮守であるのに対して、お守りは身につけて厄除けや招福など神の守護を個人的に願うためのものです。
布製の袋に入れられたもの、パワーストーン、鈴、根付、アクセサリー状のものなどさまざまな形のものがあります。
御朱印
御朱印とは、神社や寺院で、参拝者に押印される印章・印影のことです。
もともと御朱印は、寺社へ写経を納めた際の受付印であったといわれています。
現代では、その寺社におまいりした参拝証のようなものと考えればよいでしょう。
一般的に、神社の押印のほか、参拝した日付や寺社名、御祭神・御本尊の名前などを墨書きしてもらえます。
また、御朱印をもらうためのノートを、御朱印帳といいます。
破魔矢
破魔矢とは、お正月や上棟式、初節句などの際に縁起物や厄除けとして神社やお寺で授与してもらう魔除けの道具です。
正月に行われていた弓の技を試す「射礼」に使われた弓矢に由来するとされ、弓とセットになっているものもあります。
自分の身にかかる災いや魔を破り、幸せに暮らせますようにという願いを込めた縁起物で、特に1年のはじめである正月に飾ることが一般的です。
また、矢の「射る」という特性から、チャンスを射止めるご利益があるともいわれています。
おみくじ
おみくじは、神社や寺院で、吉凶を占うために引くくじです。
御神籤・御御籤・御仏籤とも書きます。
一般的には区別せず「おみくじ」と書かれていますが、厳密にいえば、神社のものは「神籤」、寺院のものは「仏籤」と書きます。
紙製のものがほとんどで、占いの内容が書かれています。
おみくじの引き方は、みくじ棒と呼ばれる細長い棒の入った筒状の箱を振って、箱に空けられた小さな穴から一本取り出し、棒に記された番号と同じくじ(みくじ紙)を受け取るのが一般的です。
このほか、自動販売機になっているものや、からくりの動物人形がみくじ紙を選ぶものなど、さまざまです。
持ち帰ったおみくじはどうやって捨てる?タイミングや処分方法を解説
まとめ

お札の処分方法とその注意点について学ぶことで、新たな信仰のステップを踏み出す準備が整いました。古くなったお札を持ち続けることにはさまざまな影響があるため、適切な方法で処分することが重要です。
お札は、神社やお寺から授けられた大切なものであり、信仰の象徴でもあります。そのため、新しいお札に替える際は、古いお札を正しく納め、感謝の気持ちを忘れずに示しましょう。
最後に、お札の処分は単なる物理的な行為ではなく、心を込めて行うべき重要な儀式です。適切な手続きを踏むことで、より良いご加護を受けられるとされています。お札に対する理解を深め、正しく向き合うことで、より充実した信仰生活を送ることができるでしょう。これからの信仰の道を大切にし、心豊かな日々を送ってください。