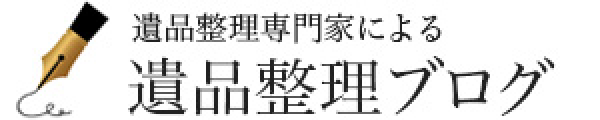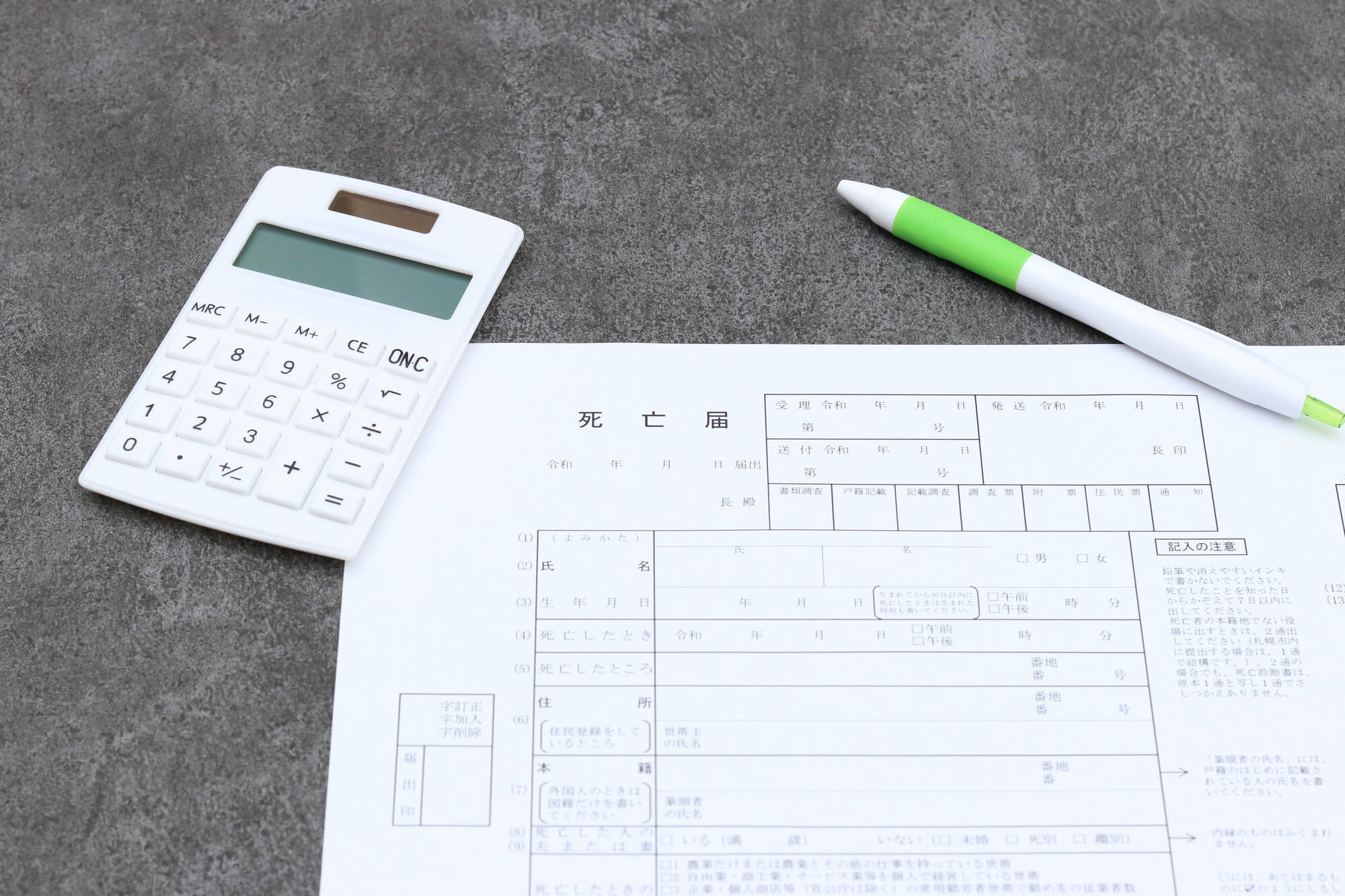大切な家族を失うことは、誰しも気持ちの整理が追いつかないほどつらい出来事です。そのうえ、急な休みの取得や手続き・連絡など、頭を悩ませることも多いでしょう。さらにコロナ禍が続く今は、家族だけで葬儀を行う「家族葬」を選ぶケースも増え、「会社にはどのように報告すればいいのか」「どこまで詳細を伝えるべきなのか」と不安に思う方もいるかもしれません。
本記事では、家族に不幸があった際の会社への連絡方法やマナーを整理し、突然の出来事にも落ち着いて対処できるヒントをお伝えします。いざというときに慌てずに済むよう、ぜひ最後までお読みください 。
目次
親が亡くなった際の会社への報告

親が亡くなったときは、気持ちの整理がつかないうえに、急に休まなければならないなど事務的な対応にも追われることでしょう。しかし、仕事を休む場合には必ず会社への報告が必要になります。ここでは、親が亡くなってから会社に対してすべきことを具体的に解説していきます。
会社への報告は電話がベスト
まずは上司や直属の管理者など、業務に直接的な影響のある相手に電話で報告しましょう。電話であれば迅速かつ確実に状況を伝えることができます。緊急度が高い相手には、メールやメッセージではなく直接音声でやり取りしたほうが誤解や遅延が発生しにくく、必要な手続きもスムーズに進められる点がメリットです。
緊急性の低い相手にはメールで訃報を知らせる
電話での連絡は時間帯や状況を選ぶため、すぐに対応が必要でない社員や取引先などに対しては、メールやメッセージを活用するのが便利です。連絡が遅れて相手に迷惑をかけることのないよう、必要に応じてあらかじめ文面を作成しておきましょう。
【メール文例】
件名:訃報のご連絡(○○部 △△より)
○○部 △△様 いつもお世話になっております。△△部の□□と申します。 突然のご連絡となり恐縮ですが、このたび実父(または実母)が○月○日に永眠いたしました。 葬儀は近親者のみで執り行う予定ですので、皆さまへのご参列はご遠慮いただければと存じます。 ご香典などのお気遣いも辞退させていただく方針ですが、何かございましたらお気軽にご連絡ください。 また、私事ではございますが、○月○日から○月○日まで休暇をいただく予定です。 業務上、ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 何か急ぎのご連絡がある場合は、上司の◇◇(メールアドレス:XXX@xxxx.co.jp)まで ご一報いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。
======================================
△△部 □□ メール:xxx@xxxx.co.jp 電話:03-xxxx-xxxx ======================================
上記はあくまで一例ですが、最低限お伝えすべきポイントとしては以下の通りです。
- 誰がいつ亡くなったのか
- 家族葬であるなど葬儀の規模
- 参列の要・不要
- 香典や弔電についての対応
- 自身の休暇の期間と、代替連絡先
相手に余計な心配をかけないよう、簡潔かつ失礼のない文面を心がけるのが大切です。
上司に訃報連絡で伝えるべき内容
上司へ連絡する際には、状況を正確かつ手短に伝えることがポイントです。具体的には、以下の情報を伝えましょう。
- 亡くなった日時・親との続柄
- 葬儀の実施予定日および場所
- 仕事の引き継ぎ
- 休みの期間
また、上司や会社のルールによっては、必要書類(死亡診断書のコピーなど)の提出を求められる場合があります。予め確認し、余裕を持って準備するのが重要です。
葬儀のスタイルや香典・弔電の受け取りを伝える
コロナ禍や故人の遺志などを考慮し、最近は「家族葬」を選択する方も増えています。葬儀の規模によっては、香典や弔電を受け取るかどうかについても会社に伝えておく必要があります。特に香典を辞退する意向がある場合や式の参列を遠慮してほしい場合は、誤解を生まないようきちんと説明しましょう。社内で取りまとめを行うケースもあるため、担当となる上司や総務部門などに相談しておくと安心です。
親が亡くなったら忌引きは何日取れる?

親が亡くなった場合、会社の規定によって定められている「忌引き休暇」を取得することができます。ただし、日数や取得方法は企業や就業規則によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。ここでは一般的な例として、どのくらい休暇が取れるのか、また忌引きの開始日や休日の扱いについて解説します。
7日取れる会社が多い
故人と自分がどのような間柄であるのかを明確に伝えます。
ほとんどの会社の場合、身内が亡くなった時に休暇を取得できる「忌引休暇制度」を設けています。
ただ、忌引休暇は法律上で規定のある休暇制度ではないため、何日休めるかは会社によって異なります。
忌引休暇は故人との関係によって日数が異なり、以下が一般的です。
| 続柄 | 忌引休暇の日数 |
| 配偶者 | 10日 |
| 父母 | 7日 |
| 子 | 5日 |
| 祖父母 | 3日 |
| おじ・おば・孫 | 1日 |
忌引きの開始日と休日
忌引き休暇は「亡くなった日」や「死亡を知った日」を起算日とすることが多いですが、これも企業により取り扱いが異なります。また、土日祝日や会社の定める休日を忌引き日数に含めるかどうかも規定によって変わります。
例えば、土日や祝日が含まれる場合に実質的な休暇日数が少なくなる可能性がありますので、「いつから休暇がスタートし、何日間が忌引きとして認められるのか」を明確に把握しておきましょう。
忌引き明けの上司・会社へのスマートな対応を解説

葬儀や法要のために休暇をいただいたあとは、職場復帰するときにどのように対応すればよいか気になる方も多いでしょう。ここでは、忌引き明けの対応を具体的に解説していきます。
上司や同僚へ直接お礼を伝える
まず大切なのは、上司や同僚に「休暇をいただいてありがとうございました」と直接感謝の気持ちを伝えることです。忙しい中で業務をカバーしてもらったり、香典や弔電をいただいたりした場合は、ひと声かけるだけでも印象が大きく違います。お礼を伝えるとともに、業務の状況を把握し、早めに仕事のリズムを取り戻すようにしましょう。
香典返しや菓子折りなどを持参する
会社や部署によっては香典をとりまとめてくださったり、お悔やみの言葉をかけてくださることがあります。その際には、香典返しやお菓子など、簡単な品物を持参してお礼を伝えるのも丁寧です。 ただし、あまり高価なものを贈ると相手に気を遣わせてしまうため、適切な金額感や品物を選ぶことが大切です。状況に応じて会社や上司の方に「お礼はどのようにしたらよいか」を確認し、トラブルを避けるようにしましょう。
直接会えない場合の対処法
リモートワークや出張などで直接会えない場合は、メールやチャットツールを活用してお礼の言葉を伝えると良いでしょう。できれば短い電話やオンライン通話など、声や表情を通じて感謝の気持ちが伝わる方法を選ぶのがおすすめです。
直接会えなくても、「休暇中はご迷惑をおかけしました」「香典をありがとうございました」と具体的にお礼の内容を伝えることで、相手への配慮が伝わりやすくなります。
家族の葬儀、どうする?

日本で一番多いのは、仏式のお葬式です。
しかし、新型コロナウィルスの流行によって大勢の人が集まることが難しくなり、お葬式にも変化があらわれています。
コロナ禍の現在、どのようなお葬式が行われているのでしょうか。
オンライン(リモート)葬儀
コロナ禍で新しく出てきたお葬式の形です。
通常のお葬式は多くの人が集まるため、コロナ感染の観点から敬遠されるようになりました。
そこで、お葬式をライブ配信するサービスが出てきました。
多くの人がパソコン、スマートフォン、タブレット端末などを利用して、コロナ感染の心配をすることなく遠隔参列できます。
オンライン葬儀のメリットは以下です。
- ・感染症対策ができる
- ・遠方に住んでいる人、身体的理由で移動ができない人なども参列できる
- ・小さな会場で行えるため会場費が抑えられる
デメリットは以下です。
- ・デジタル端末がないと参列できない
- ・葬儀社によっては扱っていない
- ・回線やシステム障害の可能性がある
家族葬(小規模葬)
最近増えているのが、小規模人数で行う家族葬です。
「家族葬」という名称がついていますが、実際には親戚や友人・知人が出席することもあります。
家族だけのお葬式というよりは、ごく少人数の近親者が参列する葬儀と考えればよいでしょう。
家族葬のメリットは以下です。
- ・親しい間柄の人が集まるためアットホームな雰囲気になる
- ・当面は親しい人への連絡のみで済む
- ・準備や手間、当日の参列者への対応など負担が軽くなる
- ・故人とゆっくりお別れができる
- ・飲食などの費用がかからないため、出費を抑えることができる
などがあります。
デメリットとしては以下が考えられます。
- ・誰に声をかけるか難しい
- ・訃報を送ったり、参列できなかった人の弔問を受けたりするなど、葬儀後の対応が多くなる
家族が亡くなった際やってはいけないこととは?

家族の死去に際し、やらなくてはならないことがたくさんあります。
しかし逆に「やってはいけないこと」もあります。
気が動転していても、以下のことは行わないよう注意が必要です。
銀行への届け出
人が亡くなった場合、取り引きを行なっていた銀行に知らせる必要があります。
しかし、銀行に死去の届け出を行うと、口座は凍結され、引き出すことも振り込むこともできなくなってしまいます。
そのため、もし誰かがお金を振り込む予定がある場合は、振り込みの期日を考えて届け出る方が良いでしょう。
遺言書の開封
遺産相続を行う場合、遺言書は大変重要です。
なぜなら、もし遺言書が存在していて、その中に相続について書かれていた場合、相続人や相続の割合は、基本的に遺言書に従わなくてはならないからです。
遺言書がなかった場合は、民法で規定されている人(法定相続人)が、規定されている割合で相続を行うことになります。
遺言書がもしあったら、中に何が書かれているのか気になります。
でも、すぐに開封してはいけません。
遺言書は、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをする必要があります。
この検認を行わずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の科料を課せられることがあるので注意しましょう。
ただし、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認を行う必要はありません。
故人の遺産を使う
人が亡くなると、お金がかかるものです。
お通夜やお葬式などを行う場合、100万円単位のお金が必要になることもあります。
特に、急死であった場合は、費用をすぐに捻出するのが難しいかもしれません。
しかし、葬儀費用に限らず、故人の遺産を使ってしまうことは控えるべきです。
もし、相続前に遺産を使ってしまうと、故人の遺産の相続を了承したとみなされるからです。
すると、相続放棄ができなくなってしまいます。
もし、故人に借金などマイナスの遺産があったとしても、すべて相続しなくてはならなくなってしまうのです。
遺産を使ってしまったために相続放棄ができなくなり、借金を背負うことになってしまう可能性があるのです。
故人の携帯電話の解約
携帯電話は、持ち主が亡くなれば、もう使う人はいません。
そのため、ほかのいろいろな手続きと一緒に、携帯電話の解約もしておこうと思う人も多いかもしれません。
しかし、故人が連絡先の一覧などを作っていない場合、携帯電話のメモリーが唯一の連絡の手がかりとなることもあります。
携帯電話の解約には期限が設けられているわけではありません。
解約しない限り料金は引き落とされますが、すぐに解約してしまわず、一定の期間置いておく方がよいでしょう。
まとめ

家族が亡くなったら、すみやかに会社に連絡しましょう。
まず総務へ連絡し、忌引休暇の日数を確認します。
また、上司や同僚に連絡し、休暇中の仕事の段取りをしておく必要があります。
連絡には、電話で伝えるのがベターですが、事情によってはメールで伝えてもよいでしょう。
連絡の際は、故人の名前と自分との関係、葬儀の日程や場所、葬儀の形式や緊急連絡先などを知らせておきましょう。