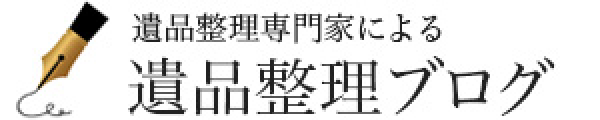近年、シンプルで使いやすいシニア向けの携帯電話やスマホが増え、多くの高齢者がこれらを持つようになりました。中には、難しい操作をこなすシニアも少なくありません。しかし、もし親が亡くなった際、その携帯電話やスマホをどう扱うべきか、悩む方も多いのではないでしょうか。
解約手続きをする必要があり、これが意外に手間がかかることがあります。特に遺族がスマホの解約や承継を進める際、トラブルも多いのです。親の携帯の解約方法を理解しておくことで、万が一の時に慌てずに済むでしょう。今回、この問題に対する具体的な対策をご紹介します。
目次
親の携帯電話・スマホの解約手続き

親が亡くなった後、携帯電話やスマートフォンの契約を解約する必要があります。解約手続きは、思ったよりも複雑に感じるかもしれませんが、いくつかのポイントを押さえておけばスムーズに進められます。ここでは、親の携帯電話やスマートフォンの解約手続きについて、必要な情報や手順を解説します。
死亡した親の携帯をそのまま利用することもできる
まず、亡くなった親の携帯をそのまま利用することも可能です。解約せずに、しばらくの間そのまま使用する選択肢もあります。しかし、基本的には、名義変更や利用停止手続きを行う必要が出てきます。
親の携帯電話を解約できる人
次に、親の携帯電話を解約する際に、その手続きを行える人について説明します。基本的には、親の遺族や法定代理人が解約手続きを行うことができます。遺族であれば、配偶者や子どもが手続きを担当するのが一般的です。
ただし、遺産相続が関係してくるため、場合によっては相続人全員の同意が必要になることもあります。また、携帯電話の契約者が個人名義の場合、手続きを行う際には相続を証明する書類が求められることがあるため、事前に準備しておきましょう。
ただ、解約手続きを急いで行うと、故人に関する情報にアクセスできなくなることがあるため、慎重に対応することが大切です。特に、葬儀前に解約してしまうと、電話番号に関連したショートメッセージ(SMS)が使えなくなる可能性があるので注意が必要です。手続き前に状況を十分確認しましょう。
親の携帯解約に必要な書類
解約に必要な書類についても触れておきます。通常、携帯電話会社に解約を申し込む際には、親が亡くなったことを証明するための書類が必要です。これには、死亡診断書や戸籍謄本などが含まれます。
また、契約者が相続人であることを示すために、遺産分割協議書や相続人の証明書類も求められることがあります。各通信会社で必要書類は異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。必要書類を揃えておくことで、手続きがスムーズに進みます。
ここで注意すべきなのは、解約手続きを行う際に必要な書類です。契約している携帯電話やスマートフォンの本体、故人の場合は死亡を証明する戸籍謄本や住民票、さらに手続きを行う家族の身分証明書が求められます。
携帯電話の解約先
携帯電話の解約先についても重要です。解約の手続きは、契約している通信会社の窓口で行います。通信会社によって手続き方法が異なるため、事前に電話で確認することをおすすめします。
オンラインでの手続きが可能な場合もありますが、特に相続が関係している場合は、店舗での直接手続きを求められることが多いです。解約を申し込む際には、本人確認のために必要書類を持参し、手続きを進めましょう。
また、解約手続きの際には、残っている料金や契約内容についても確認しておくことが大切です。
親の携帯電話解約にかかる費用
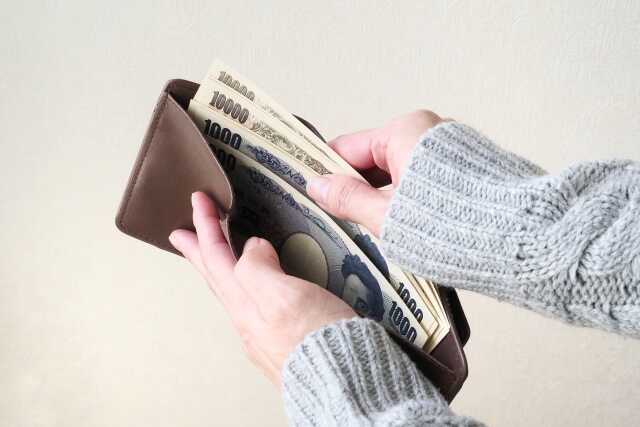
携帯電話の解約には基本的に費用はかかりませんが、いくつか注意が必要です。解約そのものには違約金や手数料は発生しません。しかし、契約中に残っている端末の分割払い金や利用料金は支払う必要があります。また、年契約型の割引が適用されている場合でも、解約に際して特別な費用が発生することはありません。
例えば、ソフトバンク、NTTドコモ、KDDI、楽天モバイルなどは、解約に関して違約金を撤廃しています。ワイモバイルも2022年2月1日から、解約金を含めた違約金を撤廃しました。これにより、解約時に高額な費用がかかる心配は減少しています。さらに、ソフトバンクの解約手続きでは事務手数料も無料です。
ただし、解約月の料金については注意が必要です。ソフトバンクでは、月の初めに解約しても料金が日割り計算されることはなく、1か月分の料金がそのまま請求されます。ドコモでは解約タイミングに関係なく、その月の料金は1ヶ月分全額が請求されます。この点も事前に確認しておくことが大切です。
携帯電話の解約に際しては、費用がかからない場合もありますが、残る支払い金額や料金の仕組みについてはしっかり理解しておくことが重要です。契約内容を確認し、計画的に解約手続きを進めましょう。
大手キャリア・格安SIMの解約・承継方法

では、代表的な3大キャリアの解約・承継方法を見ていきましょう。
docomo
解約・承継ともに、以下の書類を持参します。
- ・葬儀の案内状や死亡診断書など死亡の事実が確認できるもの
- ・ご利用中のドコモUIMカード
- ・来店する人の「運転免許証」または「マイナンバーカード(個人番号カード)」など
承継の場合のみ、承継者本人名義の「クレジットカード」または「キャッシュカード」、または「預金通帳と届け印」を持参しましょう。
必要な料金は解約日までに利用した料金のみで、翌月、請求されます。
事務手数料または手数料などは無料です。
解約すると、これまで貯めていたdポイントやドコモポイントは失効します。
承継の場合もポイントは引き継げません。
au
解約の場合は、以下のものを用意します。
- ・au電話機本体(auICカード対応機の場合は、本体+auICカード)
- ・来店者の印鑑(ゴム印以外)
- ・来店者の本人確認書類(原本)
- ・前契約者が亡くなったことを確認できる書類の原本(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、会葬礼状/新聞のお悔やみ欄、死亡届、死亡診断書、火葬(埋葬)許可書、香典返し、斎場使用料の領収書のいずれか1つ)
承継する場合は、上記の書類に加え、承継者の月々の支払方法に応じたもの(金融機関届出印、口座番号の控え、キャッシュカード、クレジットカードなど)を持参しましょう。
書類は、原本の提出が困難な場合はコピーでもOKです。
「2年契約」「2年契約N」などの料金割引サービスに加入している場合、更新期間外の解約であっても、契約解除料は発生しません。
また、「au購入サポート特約」が適用されている場合、解約に伴ってサポート解除料が発生する契約形態であっても免除されます。
ソフトバンク
解約の場合は、以下のものを用意します。
- ・契約者、使用者の死亡が確認できる書類(会葬案内状/礼状、新聞のおくやみ欄、除籍が分かる戸籍謄本、住民票(除票)、医師の死亡診断書、埋葬許可証など)
- ・契約していた「USIMカード」
- ・来店者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
を持参します。
前契約者との家族関係を示す家族確認書類(戸籍や住民票が同一など)は不要ですが、前契約者と来店者の姓が異なる場合は、提出が必要となることがあります。
また、承継する場合は、上記の書類に加え、承継者の口座名義、口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)と、金融機関への届け印またはクレジットカードを持参しましょう。
前契約者が契約解除料のかかるサービスに加入していた場合でも、解約に際し契約解除料、手数料はかかりません。
ただし、本体代金のローンの残債は継続して支払う必要があります。
楽天モバイル
楽天モバイルの解約は、Webまたはアプリの「my 楽天モバイル」から手続きできます。電話や店舗での解約はできません。以下の手順で解約手続きを行ってください。
- 逝去解約手続きの書類をダウンロードし、情報を記入する
- 必要書類を楽天モバイルに郵送する
- 解約完了のお知らせを受け取る
解約の際には以下の書類が必要です。
ご契約者様が逝去されたことを確認できる書類のコピー
ご契約者様が逝去されたことを確認するために、以下のいずれか1点のコピーをご提出ください。戸籍全部事項証明書の場合は、一部ではなく全ページのコピーをご用意ください。
発行日や発行元の自治体、公印が確認できる必要があります。他には、戸籍個人事項証明書、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、または死亡診断書も有効です。書類は判読可能な状態でご提出ください。
ご契約者様とご申告者様の関係がわかる書類のコピー
ご契約者様とご申告者様の関係を確認するために、発行日から3カ月以内の以下の書類のコピーを1点ご提出ください。関係性が記載されていない場合は不備となりますので、必ず事前にご確認ください。
提出書類には「戸籍全部事項証明書」または「除籍謄本」が含まれます。戸籍全部事項証明書は一式(全ページ)のコピーが必要で、発行日・発行元自治体・公印が確認できる必要があります。
除籍謄本は、ご契約者様の逝去とご申告者様との関係を確認できる書類です。その他、関係性が証明できる契約書なども有効です。なお、ご申告者様が高齢者等終身サポート事業者の場合は、逝去者と携帯電話解約の委託契約を結んだ書類のコピー(全ページ)が必要です。
ご申告者様の本人確認書類のコピー
ご申告者様であることを確認するために、本人確認書類のコピーをご用意ください。運転免許証や運転経歴証明書の場合は、表面と裏面の両方をコピーしてください。マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面のみで問題ありません。
ご申告者様が高齢者等終身サポート事業者の場合は、法人登記簿のコピーが必要です。その際は、一部のみではなく全ページをコピーしてください。書類は鮮明で判読できる状態でご提出ください。
不備がある場合、再提出をお願いすることがありますのでご注意ください。
解約後、登録されたメールアドレスやSMS等に「解約完了のお知らせ」が届きます。なお、契約プランの解約時に自動解約されないオプションサービス(例:製品保証オプションサービスなど)は、個別に解約手続きを行う必要があります。
UQモバイルLINE・モバイルなど格安SIM
UQモバイルやLINEモバイルの解約は、オンラインまたは店舗で手続きが可能です。
【UQモバイルの解約方法】
UQモバイルの契約者が亡くなった場合、家族が店舗で解約手続きを行います。手続きには、契約者の本人確認書類(コピー可)、死亡を証明する書類(戸籍謄本や住民票など)、契約者の委任状(関係性を示す書類)、印鑑、支払い情報、現在使用中の携帯電話端末(ICカード含む)が必要です。
代理人が手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類も求められます。解約の流れは、UQモバイルの店舗に来店し、手続きを進めるというシンプルなものです。未払い料金がある場合は、相続人が料金も引き継ぎます。ただし、相続放棄をしている場合は、未払い料金の支払い義務もなくなります。
解約後は、元の電話番号は再利用されるため、二度と同じ番号を使うことはできません。総務省の「電気通信番号規則」に基づき、一定期間経過後に別の利用者に割り当てられます。
【LINEモバイルの解約方法】
LINEモバイル(LINEMO)の契約者が亡くなった場合は、代理人による解約手続きが必要です。
【手続きに必要な書類】
- ・契約者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ・死亡の事実が確認できる書類(除籍謄(抄)本、住民票(除籍)、医師の死亡診断書など)
- ・代理人の本人確認書類
【手続きの流れ】
- LINEモバイルの「マイページ」にログインする
- 「MNP転出・解約」に進む
- 「解約・MNP転出」ページで「解約する」をタップする
- アンケートに回答する
- 最後に「申し込む」をタップする
- 解約手続きに必要な書類をアップロードする
解約手続きには、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した書類の写真をアップロードする必要があります。PDFファイルはアップロードできません。
解約してしまうと、その電話番号は二度と使用できません。総務省の「電気通信番号規則」に基づき、一定期間をおいた後に別の誰かの番号として再利用されます。
【解約に関する注意点】
- ・端末を分割購入している場合、解約後も残債の支払いが続きます。
- ・他社に乗り換える場合は「解約」ではなく「MNP転出」の手続きを行う必要があります。
- ・解約月の月額料金は日割り計算されません。
- ・月末最終日に解約手続きをした場合、解約月が翌月になることがあります。
親の携帯解約時の注意点

親の携帯電話を解約する際には、いくつかの重要なポイントを確認しておくことが大切です。特に、故人の携帯電話の解約や、家族が使用している携帯電話の名義変更など、手続きに関わる内容は慎重に進める必要があります。以下の点に注意しながら解約手続きを進めましょう。
データのバックアップを取っておく
携帯電話の解約前に、データのバックアップを必ず取っておきましょう。携帯電話には、大切な連絡先や写真、メモなど、個人情報が多数保存されています。これらのデータを失ってしまわないよう、バックアップを取っておくことが重要です。
バックアップは、スマートフォンのクラウドサービスやパソコンに保存する方法が一般的です。特に、iPhoneやAndroidのクラウドサービスを活用すると、簡単にデータを保存できます。また、写真や動画はSDカードに保存することも可能です。バックアップを取ることで、解約後にデータが消失することを防げます。
携帯電話会社のポイントは引き継げない
携帯電話の解約時には、携帯電話会社が提供しているポイントが引き継げないことを覚えておきましょう。多くの携帯電話会社では、使用状況に応じてポイントが貯まりますが、解約手続きが完了すると、そのポイントは消失することが一般的です。解約前に、貯まったポイントを使い切るようにしましょう。
ポイントの使い方としては、機種変更やアクセサリ購入に使用する方法があります。また、一部の携帯電話会社では、ポイントを他のサービスや商品券と交換できる場合もあるため、事前にポイントの使い道を確認しておくと良いでしょう。
故人の携帯電話はすぐに解約しない方が良い
親が亡くなった場合、携帯電話の解約をすぐに行わない方が良い場合があります。故人の携帯電話を解約するタイミングは慎重に決める必要があります。なぜなら、解約してしまうと、通話履歴やメッセージなど、重要な情報が手に入らなくなる可能性があるからです。
また、解約後に発生した料金や未払いの請求が未解決となってしまうこともあります。まずは、携帯電話会社に故人の状況を伝え、必要な手続きを進めた上で解約を行うようにしましょう。携帯電話会社は、故人の解約手続きに関するサポートを提供している場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。
家族が使用する携帯電話の名義人も確認しておく
家族の携帯電話を解約する場合、名義人が誰であるかを確認しておくことが重要です。携帯電話契約は、名義人が契約者となります。そのため、家族が使っている携帯電話の名義人が実際に誰かを把握しておかなければ、解約手続きがスムーズに進まない可能性があります。
例えば、親が家族の携帯電話を契約している場合、親が解約手続きを行うことになります。もし、親が亡くなった場合、名義変更や解約の手続きを進めるためには、名義人が誰かを確認し、必要な書類を用意しておくことが求められます。特に、名義人が親以外の家族である場合も、契約内容や解約の際に必要な書類を事前に確認しておくと良いでしょう。
また、家族間で携帯電話の名義変更を希望する場合も、同様に契約者の確認が重要です。名義変更の手続きには、本人確認書類や利用者の承諾が必要な場合があります。事前に必要な手続きや書類を準備しておくと、手続きがスムーズに進みます。
トラブル続出!? 携帯・スマホの解約

人が亡くなると、公共料金に始まり、保険や年金など、さまざまな手続きが必要になりますね。
その一つが、携帯電話やスマホの承継・解約です。
書類さえあれば簡単に解約できそうですが、意外とトラブルが頻発しているようです。
その例を見てみましょう。
Aさんの場合
半年前にご主人を亡くしたAさん。
亡きご主人とAさん、そして息子さんは、携帯電話の家族割引を利用していました。
ご主人が亡くなったあと、Aさんは携帯ショップに行き、ご主人が亡くなったことを伝えました。
でも、ご主人の死後、半年たっても、ご主人の分の基本料金も含まれた請求書が届いていたそうです。
Bさんの場合
お父さまを亡くされたBさん。
亡くなったあとすぐ、お父さまの携帯を解約したのですが、解約後も請求書が送られてきます。
おかしいと思い調べてもらったところ、お父さまは携帯を契約した際に、wi-fiのルータをセットで契約しておられたことがわかりました。
請求書は、そのルータの電話番号のものでした。
しかし、実際には、お父さまはwi-fiを全く使っておられなかったそうです。
今度はこのwi-fiを解約しなくてはならなくなったのですが、カスタマーセンターの電話でしか解約手続きができず、また、電話がなかなか通じず、アポイントを取るまでに数日もかかってしまいました。
何とか解約に必要な書類を取り寄せ、記入してすぐに発送したものの、実際に解約が完了したのは書類発送後2週間も経ってのこと。
その間も請求は止まらず、Bさんは非常に不愉快な思いをされたそうです。
Cさんの場合
最近、「亡くなった伯父の携帯電話を解約するために、携帯ショップに行ったところ『本人がいらっしゃらないと解約できません』と言われた」というツイートが話題になりました。
伯父さまが生前に使っていた携帯電話を解約することになったため、携帯電話について家族の中で一番詳しいCさんが、解約手続をすることになったそうです。
もちろん、携帯ショップには、死亡診断書と戸籍謄本を持って行きました。
ところが、携帯ショップでは「当店では、ご本人様以外の手続きは一切承っていません」と言われ、解約を断られたというのです。
この理不尽な対応に憤ったCさんでしたが、その後、別のショップで無事解約できたそうです。
遺品整理はゴミ屋敷バスター七福神にご相談ください

遺品整理にお困りなら、ゴミ屋敷バスター七福神にご相談ください。専門のスタッフが、整理や片付けの作業を迅速かつ丁寧に行います。不要な物の処分から、思い出の品の取り扱いまで、幅広く対応いたします。
遺品整理は感情的な負担が大きいため、安心して任せられる専門業者に依頼することが重要です。七福神では、心を込めて作業を進め、お客様のご希望に沿ったサービスを提供しています。お困りの際は、ぜひお電話でのお問い合わせをお待ちしております。
まとめ

携帯電話やスマホに関しては、解約・承継だけでなく、インターネット上で使用していたサービスについても解約しなくてはなりません。
遺族の苦労を軽減するためにも、家族の間で、万が一のときにお互いの携帯をどのように処分してほしいか話し合っておきましょう。
スマホの持ち主は、携帯電話の契約書とともに、インターネット上でのIDとパスワードをエンディングノートなどに記載しておくことをお勧めします。
また、終活の一環として、使用していないサービスは解約しておきましょう。
しかし、こういったメモなどがなく、どうしたら良いのかわからない時や、お困りの方は、遺品整理業者に相談することをお勧めします。
自社で処理できない場合は、提携しているデジタル遺品整理の専門業者を紹介してもらえることもあります。
デジタルデータをまとめるなど、必要に応じて処分をしてくれます。
デジタル機器を扱うのが苦手な人は、相談してみましょう。