「散らかった部屋にいると、どうして気が滅入るんだろう?」
「イライラするし、やる気も出ないし……まったく掃除が進まない!」
というお悩みはありませんか? 部屋は心理状態を映し出す鏡とも言われており、部屋が汚いと精神状態が不安定になりやすくなるため注意が必要です。
汚い部屋はストレスが溜まるだけでなく、自己肯定感が下がったり人間関係が悪くなったりする場合もあるため、放置するのは危険です……。
この記事では、汚れた部屋と精神状態の関係について解説し、病気との関連や部屋を散らかしやすい人の性格的特徴なども説明します。汚部屋を解消する方法もお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
<この記事で分かること>
- 部屋が汚いとなぜ精神状態が悪くなるのか
- 部屋の汚さに関連する病気と性格的特徴
- 片付いた部屋が精神状態に良い理由
- 片付け下手な人でも無理なく汚部屋を片付ける方法
目次
部屋の汚さは精神状態にも悪影響

汚れた部屋は見た目が悪いだけでなく、私たちの精神状態にも深刻な影響を及ぼします。
雑然とした部屋で生活しているうちに、イライラしたり気分が落ち込んだりした経験はありませんか? 汚れた部屋が及ぼす心理的な悪影響について、詳しく解説します。
汚い部屋は精神状態をさらに追い詰める
汚い部屋は、私たちの精神状態を悪化させる原因となります。散らかっている物を目で見るたびに、その視覚情報が不快な刺激として脳に伝わり、ネガティブな感情を引き起こしてしまうからです。
雑然とした室内は情報過多な状態であり、脳は常に情報処理に追われています。ゆっくりリラックスできないため、脳が疲労してストレスが蓄積していくのです。
ストレスは、腎臓の上に位置する副腎皮質という臓器からのストレスホルモン・コルチゾールの分泌を促します。一時的なストレスであればあまり問題ありませんが、汚い部屋に居続けると慢性的なストレスに晒されるため注意が必要です。
コルチゾールが慢性的に分泌されると、不安やイライラ感が増幅されて不眠や抑うつ状態などのメンタル不調につながることがあります。
汚い部屋での生活ではやる気が起きない
汚い部屋で暮らしていると、やる気が湧きにくくなります。視覚的な混乱によって脳の処理能力が低下し、集中力や生産性を発揮しづらくなるからです。何かにチャレンジする意欲も生まれにくくなり、問題解決能力も低下していきます。
しかし、汚部屋に住んでいる本人は、「やる気が出ないのが住環境のせいだ」とはなかなか気付けません。そのため、「理由は分からないけれど全然やる気が出ない……」「こんな自分はダメだ」とネガティブな気分になってしまい、ますます行動意欲が湧かなくなるという悪循環に陥りがちです。
汚い部屋は自己肯定感を下げやすい
自己肯定感は、汚い部屋に居続けると下がってしまうことがあります。「部屋がいつまでも片付かないのは、自分に管理能力がない証拠だ」と考えてしまい、自己否定の気持ちが湧きあがってくるからです。
汚れた部屋は、ただでさえ精神状態が不安定になりやすい環境です。「ストレスが溜まって心が休まらず、やる気が出ずに片付ける気分にもなれない」という状況では、どうしても自己肯定感が下がりやすくなってしまします。
自己肯定感とは、ありのままの自分で良いという感覚のことです。自己肯定感を高めたいと思っていても、汚い部屋に住んでいると「こんな部屋にいる現状を受け入れたくない」「もっとちゃんとしなくちゃダメなのに……」と自己否定的な思考パターンが強化され、ありのままの自分を受け入れるのが難しくなってしまうので注意しましょう。
精神状態に影響するほど、部屋が汚くなる原因

片付けが得意な人は「いつまでも部屋を散らかしていないで、さっさと片付ければ良いのに!」と思うのかもしれません。しかし、部屋を片付けられない人の多くは、決して怠けていたわけではないのです。
片付けられない人のほとんどは、その人なりの深刻な事情を抱えています。きれいに片付けたいと思っているのにもかかわらず、どうして部屋が汚くなってしまうのか? その理由を詳しく解説していきます。
忙しすぎて片付ける時間がない
仕事や家事、育児などに追われて慌ただしく暮らしていると、片付ける時間がなかなか取れません。たとえば、仕事で夜遅くまで帰宅できなかったり、帰宅後も何かしらのタスクが残っていたりすると、部屋を片付けるどころではなくなってしまいます。小さな子どもがいる家庭では、自分が片付けたそばから子どもが散らかしてしまうこともあり、片付け直す時間がとれない場合もあるでしょう。
また、時間に追われているとストレスや疲れが溜まって気力が低下しやすくなり、部屋を片付ける意欲が低下しがちです。意欲が落ちると、ますます片付けが困難になってしまいます。
部屋に対して、物が多すぎる
必要以上に物が多いと、片付けが大変になって汚部屋化しやすくなります。収納スペースに入りきらなくなった物が床やテーブルに積み上げられ、雑然としてしまうからです。
また、物が多い部屋は視覚的な情報が過多になるため、脳に余分なストレスがかかります。ストレスで集中力や思考力が低下すれば、片付けはますます困難になるでしょう。
整理整頓のしにくさと精神的なストレスのたまりやすさという2つ理由により、物だらけの部屋はきれいに保つのが難しいのです。
片付けや住環境への優先順位が低い
片付けや住環境への関心が低い人には、部屋を散らかしやすい傾向が見られます。仕事や趣味、人間関係などに強い関心を向ける結果として、部屋の乱れへの関心が相対的に弱くなっている状態と言えるでしょう。
また、「散らかっていても生活できているなら別に気にしない」というタイプの人は、片付けを先延ばししがちです。片付けや掃除に苦手意識があるケースでは、さらに片付けを先延ばしにしてしまうため汚部屋化が進みやすいと言えます。
疲れやストレスで片付けられない
仕事や人間関係などで疲れやストレスが溜まっていると、片付ける気力が湧かなくなってしまいます。ぐったり疲れてイライラしていると何をするのも億劫になり、片付けるどころではなくなってしまうのです。
また、ストレスは脳の機能を低下させます。脳の機能が低下すると集中力や判断力を発揮しにくくなるため、片付けの段取りを考えることができずに延々と先延ばししてしまいます。
さらに、心身の疲労やストレスは倦怠感や抑うつ状態、不眠などさまざまな不調の原因となります。メンタル面や身体面で明らかな不調が出ると、ますます片付ける余裕がなくなってしまうでしょう。
精神状態が安定しない方に疑われる病気

部屋が汚いと精神状態が不安定になるのは、誰にでも共通することと言えます。しかし、中には部屋の汚さに病気が関連しているケースもあるので注意が必要です。
<部屋の汚さとの関連が疑われる病気>
- うつ病
- 買い物依存症
- 溜め込み症(ホーディング障害)
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD)
- 強迫性障害(OCD)
- 慢性的なストレスや不安
それぞれの症状や部屋の状態との関連について、詳しく解説します。これらの病気が疑われる場合には、できるだけ早く心療内科や精神科の医療機関を受診しましょう。
うつ病
うつ病は気分が落ち込んで憂鬱になり、やる気が出なくなる病気です。疲れやすさや不眠などを伴うことも多く、集中力の低下や「自分は無価値な人間だ」という感覚に苛まれることもあります。
うつ病の人は片付けへの意欲が低下したり、片付け中に集中力が維持できなくなったりして、部屋を散らかしてしまうことがあります。散らかった部屋にますますイライラしたり、部屋を汚してしまう自分を責めてさらに憂うつな気分になったりすることもあるため注意が必要です。
悲しくて憂うつな気分が1日中続いている、これまで好きだったことに興味を持てなくなってしまった、などの症状が2週間以上続く場合にはうつ病の可能性があるため、心療内科や精神科に相談しましょう。
買い物依存症
正式な病名ではありませんが、必要のない物を過剰に購入してしまう状態を一般的に「買い物依存症」と言います。物を買うときの高揚感でストレスや不安を解消しようとするため、結果的に部屋が物だらけになってしまいます。
買い物依存症の人は買い物をするときの快感を求めて衝動的に買ってしまうのですが、後で「また無駄な物を買っちゃった……」と自分を責めることが多いです。そして、自分を責める気持ちや物だらけの部屋にストレスを感じてしまうと、そのストレスを解消したくてさらに買い物をするという悪循環に陥りがちです。
買い物依存症は、自然治癒するケースが少ないと言われています。心療内科や精神科を受診して、カウンセリングや認知行動療法を通して買い物への考え方や行動を変えていくことが大切です。
溜め込み症(ホーディング障害)
溜め込み症はホーディング障害や強迫性貯蔵症とも呼ばれ、物を捨てられずに大量に溜め込んでしまう病気です。不要な物でも「いつか使うかもしれない」「捨てるのはもったいない」と感じて捨てるのが怖くなり、部屋中が物で溢れかえっていきます。
溜め込み症は単なる性格上の問題ではなく、強迫性障害や不安障害などの精神疾患と関連していることがあります。溜め込み症の症状が自然に落ち着くケースは少ないといわれており、治療には精神科や心療内科を受診することが必要です。医療機関ではカウンセリングや認知行動療法などを通して、少しずつ物を手放せるように訓練していきます。
ホーダー(ためこみ症)とは?原因や治し方、部屋を綺麗に保つ方法について解説
注意欠陥・多動性障害(ADHD)
ADHDは注意力の欠如や多動性、衝動性などが見られる発達障害です。ADHDの人には部屋の片付けが苦手な人が多く、整理整頓ができない、物をなくしやすい、片付けの途中で他のことに気を取られてしまうなどの症状がしばしば見られます。
ADHDの人は整理整頓や計画的行動が苦手な傾向が見られ、部屋を散らかしてしまうことが多いです。この傾向は脳の特徴によるものなので、本人の努力ややる気とは必ずしも関係しません。
汚部屋化する可能性が高いことを前提として、物を減らして片付けやすくする、収納を単純にするなど散らかりにくい部屋を作ることがADHDの人にとって重要です。
汚部屋は発達障害やADHDと関係があるもの?その理由と解決方法を解説
強迫性障害(OCD)
強迫性障害は、特定の考えや行動を繰り返してしまう精神疾患です。いわゆる潔癖症も強迫性障害の一種であり、汚れや細菌を過剰におそれて必要以上に手を洗ったりドアノブを触れなくなったりすることがあります。その一方で、不潔な物を嫌がるあまり室内のゴミに触れなくなったり、完璧を求めるあまり片付けが進まなくなったりするケースも見られます。
強迫性障害は、強いストレスやこだわりが原因で発症すると言われる病気です。適切な治療によって改善することが知られており、症状改善には医療機関で薬物療法や認知行動療法を受ける必要があります。
慢性的なストレスや不安
慢性的なストレスや不安があると精神的なゆとりがなくなり、部屋を片付ける余裕もなくなってしまいます。強いストレスは心身を消耗させるため、片付けをする気力が湧かなくなってしまうのです。
たとえば、仕事や人間関係のトラブル、将来への不安や心配事など、私達はいつもさまざまなストレスに晒されています。それらを受け流したり解消したりできずにいると、どんどんストレスが溜まってしまいます。
ストレスは、うつ病や強迫性障害などのおもな原因です。これの精神疾患を発症すると、ますます精神状態が悪化するので注意しましょう。ストレスや不安を解消するには、十分な休息や睡眠、趣味の時間、適度な運動などが必要です。また、カウンセリングを受けてストレスの原因やケア方法を探るのも、根本的な対処法になります。
部屋が汚いとイライラするのは病気?ストレスの原因と対処法を解説
部屋が汚くなりやすい人の性格
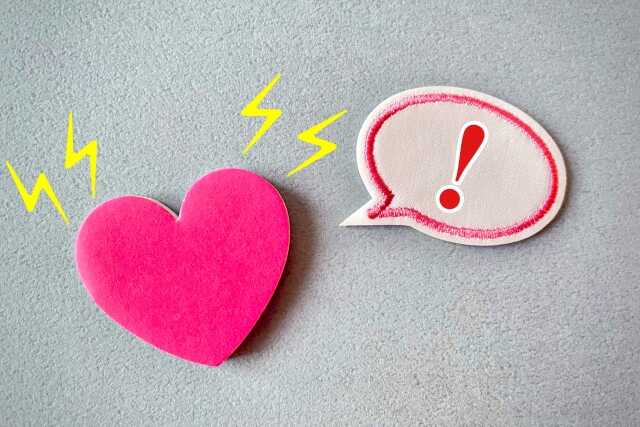
部屋が汚くなりやすい人は、必ずしも病的な問題を抱えているわけではありません。病気とまではいかなくても、性格的な特徴によって部屋が散らかりがちになることがあります。
ここでは、部屋を散らかしやすい人に多く見られる性格的な特徴について解説します。
中途半端は許せない!完璧主義
意外に感じるかもしれませんが、完璧主義な人は部屋を汚くしやすい傾向があります。「一度始めたら最後まで徹底的に片付けたい。今はあまり時間がないから、掃除はまた今度にしよう」と考えて、先延ばしにしてしまうからです。
完璧主義の人は中途半端に手を付けるのを好まず、掃除や整理整頓も完璧に仕上げないと気が済みません。しかし、日常生活ではまとまった時間が取れないことが多いため、いつまでも掃除に取りかかれないのです。その結果、ゴミや汚れが溜まって部屋全体が汚くなってしまい、片付けの難易度がどんどん上がってしまいます。
物への執着が強い
物への執着が強い性格の人も、部屋を汚してしまいがちです。手に入れた物をなかなか手放せない人には、「サンクコストバイアス」という心理現象が働いていると言われています。
サンクコストバイアスとは、それを入手するときに払ったお金や労力(サンクコスト)に執着するあまり、「いつか使うかもしれない」「高かったからもったいない」と考えて手放せなくなる状態のことです。損をしたくないという気持ちが強くて合理的な判断ができなくなり、部屋を物だらけにしてしまうのです。
先延ばし癖がある
先延ばし癖がある人は「後でやろう」「明日で良いか」と考えて、すべきことを後回しにしてしまう傾向があります。部屋の片付けも例外ではなく、先延ばしを続けていくうちにどんどん汚部屋化してしまうのです。
最初のうちは、「片付けるのはちょっと面倒だな」と感じる程度かもしれません。しかし、先延ばしにすればするほど、片付ける物の量が増えていきます。すると、ますます面倒になってしまい、気づいたときには汚部屋化していた……というケースも少なくありません。
汚い部屋を片付けると精神状態も安定しやすい

汚い部屋を片付けると、精神状態に良い影響が現れます。「毎日なぜかイライラする」、「感情の落ち込みや浮き沈みが激しい」など、メンタルに課題を抱えている人は、ぜひ部屋をきれいにしてみましょう。
部屋の片付けが精神状態を安定させる、6つの理由を解説します。
ストレスが緩和される
片付いた部屋で生活していると、ストレスが和らぎます。部屋がきれいだと不快な視覚情報がなくなるため、脳疲労が起こりにくくなるためです。
散らかった部屋では、溜めこんだ物のひとつひとつが視覚的なストレスとなって脳に負担がかかります。住んでいるだけで知らず知らずのうちにストレスが溜まり、精神状態が不安定になってしまうのです。
現代人は仕事や家事などのタスクに追われ、ただでさえストレスを抱え込みがちです。部屋をきれいに保って、リラックスしやすい環境にしましょう。
部屋にいるときの集中力が上がる
きれいな部屋で暮らしていると、集中力が高まります。無駄な視覚的刺激を受け取らずに済むため、脳が疲れにくくなるからです。
散らかった部屋で暮らしていると、ひとつのタスクに取り組んでいる間にも「洗っていないお皿を片付けなくちゃ」「そういえば、あの服はどこにしまったっけ?」など別の考え事に囚われやすくなってしまいます。すると、特定の作業になかなか集中できません。
一方で、きれいな部屋では余計な考え事に気を取られることが減るため、物事に集中しやすくなります。物事を深く考えたり、大変なことをやり抜いたりするには集中力が不可欠です。作業効率を高めて思考をクリアにしたい人は、部屋を整えていきましょう。
汚部屋を片付けた達成感・充実感を味わえる
汚部屋を片付けると、大きな達成感や充実感を味わうことができます。片付けるのが大変だからこそ、やりとげたときに得られる満足感が大きくなるのです。
部屋がきれいになるにつれて、自分のがんばりを実感できて達成感が湧いてきます。きれいになった部屋での暮らしは心地よく、継続的に充実感を味わうことができるでしょう。
なお、必ずしも自分一人で片付けをやりとげる必要はありません。家族や友人、プロの片付け業者などの力を借りたとしても、達成感や満足感は湧いてきます。あなた自身が「片付けよう」と思って働きかけなければ、片付けは実現できなかったはずだからです。
時間にゆとりができる
整理整頓された環境では時間を有効に使えるため、余裕を持って生活できるようになります。部屋が整理されていると必要な物がすぐに見つかり、時間を浪費せずに済むからです。
物で散らかった部屋では、すぐに物がどこかに行ってしまいます。探し物のたびにタイムロスが発生すると、時間にも心にもゆとりがなくなってしまうでしょう。
また、物だらけだとホコリや湿気が溜まりやすくなるため、掃除にも長い時間がかかります。掃除時間が長引けば、自由な時間をなかなか確保できません。時間にゆとりが欲しい人は、部屋を片付けて物の定位置を決めましょう。掃除もしやすくなり、時間を有効活用できるようになります。
睡眠の質が良くなり、メンタルも安定する
整然とした部屋にいると、心も体もリラックスできてぐっすり眠れるようになります。質の良い睡眠は、ストレス対策の基本です。毎日しっかり眠るうちに、メンタルが安定していくのが実感できるでしょう。
汚れた部屋には、睡眠の質を低下させる要因がたくさんあります。散らかった物は、視覚的な刺激となって寝る直前までストレスを与えます。また、ホコリやダニなどのハウスダストはアレルギー性鼻炎などの原因となり、鼻水や鼻づまりなどのトラブルを起こします。
メンタルが不安定になりがちな人は、毎日ぐっすり眠れているかふり返ってみましょう。満足な睡眠がとれていないようであれば、寝室の環境改善を目指すのがおすすめです。
自己肯定感が高まる
汚い部屋が片付くと、自己肯定感が高くなります。部屋を快適な状態に維持・管理できているという事実が目に見えて分かるため、自分に自信を持つことができるからです。きれいな部屋での生活が、ひとつの成功体験としてあなたにポジティブな影響を与えてくれるでしょう。
汚れた部屋で生活していると、ついつい気が滅入りがちです。散らかった物や不潔な物、溜まった湿気のせいで生えてしまったカビなどを見るたびに、「片付けなくちゃ」「でも、今は片付ける余裕がない」「部屋の片付けさえできないなんて……」と自分を責めるループに陥ってしまうからです。
自分を責める癖がある人は、部屋をきれいにして自己肯定感を高めていきましょう。
片付けられない人が汚い部屋を脱出する方法

これまでに、部屋が散らかりやすい人に共通する性格や状況などをお伝えしてきました。しかし、性格や状況は簡単に変えられるものではなく、「じゃあ、どうすれば片付けられるの?」と困っている人もいるのではないでしょうか。
無理なくきれいな部屋を目指すための、具体的なポイントや心構えを解説します。
小さな目標を立てる
いきなり完璧を目指すのではなく、小さな目標から始めることが大切す。たとえば、「今日は机の上だけ片付ける」「玄関のホコリをはいて靴を整える」のように目に見える成果を実感できて、達成可能な小さい目標を設定しましょう。
片付けの難易度は、できるだけ低くするのがポイントです。小さな成功体験を積み重ねると自信が付き、片付けを習慣化しやすくなります。重要なのは、できるだけ毎日継続することです。
習慣化できるなら、すきま時間にできるような小さな片付けでかまいません。数か月に一度だけ長時間の片付けをするよりも、毎日15分の小さな片付けを積み重ねるほうが効果的です。
タイマーを使って短時間だけ片付ける
タイマーを使って、10~15分などの短時間の片付けをするのも小さな目標を設定するのに役立ちます。とくに、「片付けているとすぐ集中力が尽きてしまう」「片付けが面倒でなかなか取りかかれない」という人には、タイマーの利用が効果的です。
片付けのハードルを低くして小さな目標をこまめに達成していくことが、きれいな部屋を目指す秘訣と言えます。片付けの作業範囲だけでなく、作業時間も負担のないレベルに引き下げておくことが小さな目標を設定する上で欠かせません。自分の集中力や疲れ具合などを考慮しながら、タイマーを活用して短時間の片付けを継続しましょう。
一時的に保管し、処分を急がない
物を捨てるときに迷って捨てられなくなってしまう人は、「一時保管ボックス」を用意して迷った物を入れましょう。一時的に判断を保留してから1週間後や1か月後などに見直し、冷静になって判断し直すのです。
とくに、思い出の詰まった物や写真、買い直し不可能なアイテムなどは、判断に悩みがちなので一時保管がおすすめです。処分を急がないことで、心理的な抵抗感を減らすことができます。
「保留」は、断捨離の基本テクニックのひとつです。必要か不要かを即座に判断するだけでなく、保留するという第3の選択肢を用意しておくことで作業の手が止まるのを防ぐことができます。ただし、一時保管した物は後できちんと見直してください。見直さずに保管していると、結局、部屋の物が減らせなくなってしまいます。
理想の部屋をイメージする
理想の部屋をイメージすると、片付けのモチベーションを維持できます。「こんな部屋に住みたい」「片付いた部屋で趣味の時間を取りたい」など、ゴールを明確にするとワクワクしながら片付けられるようになるのでおすすめです。雑誌やインターネットで理想の部屋の画像を探したり、その画像やイラストを見やすい場所に貼ったりするのも良いでしょう。
みなさんは「ビジョンボード」をご存じでしょうか。叶えたい夢や目標を絵や写真で可視化したものをビジョンボードと言い、それを目につく場所に置くと実現しやすくなるというものです。
ビジョンボードは、ただのおまじないではありません。視覚情報として理想の部屋や生活習慣をリアルにイメージできるようになるため、無意識に行動が変わったり片付けの意欲が湧いたりするのです。理想の生活やきれいな部屋のイメージ画像を、スマホの待ち受け画面にするのも効果的です。
汚部屋の片付け、何から始めればいい?自力で片付けきる手順とコツ
物を増やさない習慣をつける
部屋をきれいに保つためには、物を増やさない習慣を付けることが欠かせません。買い物をするときは、本当に必要かどうかをよく考えて衝動買いを避けましょう。また、定期的に持ち物を見直して、いらない物を処分することも大切です。
物が増えれば増えるほど、片付けの手間がかかって自分が苦労することになります。「お金を出して買った物を捨てるのはもったいない」という執着と、「物が減ると自分が楽をできる」という現実的なメリットを天秤にかけてみましょう。メリットの多さを実感できると、悩まずに物を捨てられるようになります。
日常的にストレスケアを行う
こまめにストレスケアをして、心労を溜め込まないようにしましょう。ストレスが溜まっていれば、片付けの意欲が湧かなくなるのは当然です。ストレスは精神状態を悪化させて集中力や判断力を鈍らせてしまうので、日常的なストレス対策が欠かせません。
汚い部屋に住んでいるとストレスが溜まりやすくなるため、まずは意識的に休んでストレス解消を心がけましょう。できるだけしっかり眠り、無理のない運動習慣を取り入れたり、栄養バランスの良い食事を続けたりすることがストレス対策の基本です。
精神状態が非常に悪く、不安やイライラなどが込み上げてくる場合には専門家のカウンセリングや医療機関への受診も検討しましょう。
汚部屋の片付けは七福神におまかせください!

汚部屋の片付けでお困りの人は、ゴミ屋敷バスター七福神にご相談ください! 年中無休の最短即日対応で、お客様の部屋をきれいに片付けます。
「片付けたいけれど、部屋にいるだけで気が滅入る」「部屋中が物だらけで手を付けられないし、時間も足りない……」そんな悩みも、ゴミ屋敷バスター七福神なら心配ありません。汚部屋・ゴミ屋敷清掃の経験豊富なスタッフが数時間で片付けて、快適な部屋を取り戻します。「まさか、こんなにきれいになるなんて!」という、驚きの声も多数お寄せいただいています。
不用品の買取も行っており、買取価格を片付け費用から値引きできるので経済的です。また、女性スタッフも在籍しているため、一人暮らしの女性のお客様もご安心ください。汚部屋のストレスから解放されて、心の休まる毎日を送りましょう! ご相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ

汚れた部屋は精神状態に悪影響を及ぼして、住む人のやる気や自己肯定感を失わせてしまいます。部屋が荒れる原因としてうつ病や発達障害などが隠れていることもありますが、病気ではなくても日々忙しく過ごしていたり、ストレスを抱えていたりすると汚部屋になってしまうことがあります。また、完璧主義や先延ばし癖などの性格も、汚部屋化につながりやすい要素のひとつです。
部屋をきれいにするためには、全体を一気に片付けようとするのではなく、小さなエリアを短時間だけ片付けることを習慣付けることが大切です。物を増やさない工夫や理想の部屋をリアルにイメージすること、ストレスケアを日常的に行うことも欠かせません。 自力での片付けが難しいと感じたら、無理をせずに片付けの専門業者に相談してみましょう。プロの力を借りていったん部屋をリセットし、精神状態を安定させてから汚れにくい部屋を目指すのがおすすめです。




