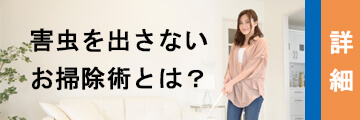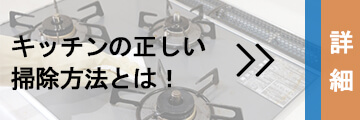気温が高い日が増えてきたら気を付けたいのが、虫問題。
キッチンに虫が飛び回っている光景は、見ていて気持ちが良いものではありませんよね。
日ごろからしっかり対策をしておかないと、虫は繁殖し数がどんどん増えてしまいます。
虫に悩むことなく過ごすためにも、虫を寄せ付けない対策が重要です。
今回は、生ゴミに虫が発生する原因や対策について徹底解説します。
夏本番を迎える前にしっかり準備を整えて、快適な暮らしを手に入れましょう。
目次
家に虫が湧く11の原因

部屋を閉め切っているつもりでも、なぜか虫が湧くことがあります。
その原因は虫を引き付けるニオイやエサの存在や観葉植物、小動物など多種多様です。網戸やドアの小さな隙間から侵入した虫が、家具や排水溝の中で増殖して湧き出してくることも……。
家庭ゴミに虫が湧く原因として、代表的なものを11個紹介します。
虫が侵入できるすき間が空いている
家に虫が湧く原因はさまざまですが、まず一つは家に虫が侵入できる隙間があることです。家の隙間から虫は簡単に入ってきます。窓やドアの隙間、または壁や床のひび割れがその原因となることがあります。
これらの隙間を放置しておくと、虫が室内に入り込みやすくなります。特に、古くなった窓やドアのゴムパッキンが劣化している場合、虫が簡単に入り込む原因となります。
隙間を防ぐためには、パッキンを交換したり、ひび割れを修復することが重要です。家の隙間をきちんと塞ぐことで、虫の侵入を防ぐことができます。
生ゴミの腐敗臭
腐った生ゴミから発生する不快な「腐敗臭」は、さまざまな虫が好むニオイです。この腐敗臭に引き寄せられて、エサを求める虫たちが網戸などのわずかな隙間から侵入してくるのです。
とくに夏場は高温多湿で雑菌が繁殖しやすいため、キッチンの三角コーナーに溜まった野菜くずや食べ残しを放置したり室内に生ゴミを置きっぱなしにしたりすると、数日内に強烈な腐敗臭を発するようになります。
ゴミ箱やシンクの水分
シンクやゴミ箱に水分があると、生ゴミはますます強烈な腐敗臭を放って虫を引き付けます。生ゴミについた雑菌は水分があるとより活発に増殖するため、強い腐敗臭を発するようになるのです。
キッチンのシンクは調理のために水を多く使いますし、ゴミ箱は生ゴミから漏れ出た水分が付着して湿気が高くなり、腐敗臭とともに虫にとって魅力的な環境となるのです。
なお、室内で虫が集まってくるのはシンクやゴミ箱だけではありません。飲みっぱなしにしたジュースやビールなどの缶、コップなども水分とエサを求めて虫が湧く場合があります。
外に放置したゴミ
集めた生ゴミを入れたゴミ袋を収集日まで屋外に出している人もいますが、虫が大量に湧く原因となるため注意が必要です。
とくに春から秋にかけての屋外は家の中よりも気温が高くなることもあり、生ゴミがあっという間に腐敗します。屋外にはたくさんの虫がおり、虫にとっては屋内に侵入するより屋外のゴミ袋に入り込むほうが簡単なので虫の被害が深刻化しやすいともいえます。
「ゴミ出しの日に捨てようと思ったら、大量の虫が湧いていた」ということになりかねません。
袋のまま保管されたお米
スーパーや農家から買ってきたお米は、袋のまま保管しているとコクゾウムシなどの虫が湧くおそれがあります。しっかり袋の口を閉じていない米袋には、虫が容易に侵入します。ビニール製の袋を食い破ってもぐりこんでくる場合もあるので「袋の口が締まっているから大丈夫」という油断は禁物です。
とくに春から夏に向けて気温が上昇すると、虫も活発になるので発生リスクが高まります。虫は米に卵を産み付けるため、一度虫が湧くと米から完全に取り除くのは困難です。コクゾウムシは人体には基本的に無害といわれていますが、精神衛生上好ましいものではありません。
密閉できる米びつに入れて米びつ専用防虫剤を用いるなどの対処をしなければ、お米は虫の発生源の一つとなってしまいます。
排水溝の詰まり
キッチンやお風呂などの排水溝が詰まると、チョウバエをなどの虫が湧くおそれがあります。排水溝に詰まって蓄積した食品カスや垢、毛髪などのゴミは栄養分・水分ともに豊富で、虫にとっては恰好のエサです。虫が集まってくるばかりか、排水溝に溜まった水に産卵されるとさらに増殖するおそれがあります。
こまめに清掃を行わなかったり、滅多に水が流れず古い水が溜まりっぱなしになったりしている排水溝は、虫が湧くリスクが高いです。
部屋に湿気が溜まっている
部屋に湿気が溜まるとカビやダニが繁殖しやすくなり、そのカビなどを食べるチャタテムシなどの虫が集まってきます。チャタテムシは押し入れや木製家具、畳、段ボールなど湿気の溜まりやすい場所を好み、そこに生えたカビを食べて生息します。チャタテムシはとくに梅雨から初秋の湿度が高い時期は増えやすく、カビの付着した体で動き回って周囲にカビを広げてしまうので要注意です。
こまめに換気をして空気を循環させないと、家の中に湿気が溜まって虫が湧くおそれがあります。雨の多い梅雨の季節などは、外気を取り込む代わりにエアコンの除湿モードを使用すると効果的です。
駆除しきれなかった虫の再発
家の中で見かけた虫を駆除しきれずにいると、生き残った虫が子孫を増やして大量発生する場合があります。小さくて俊敏な虫は追いかけている最中に見失いやすく、数が多いと手に負えなくなってしまうため、一匹残らず完璧に駆除するというのはなかなか大変です。
「ゴキブリを1匹見付けたら100匹いると思え」という言葉もあるように、生命力・繁殖力が強い虫は多いものです。虫の再発が心配な人は後述する防虫剤の設置や、専門の害虫駆除業者への依頼などを検討する必要があります。
鳥や小動物によって持ち込まれる
ベランダや庭先に訪れるカラスやハトなどの野鳥、野良猫や小動物などが虫を運んでくる可能性があります。鳥や小動物の体にはダニ、ノミなどの虫が付着していることがあり、鳥獣を介して家に持ち込まれるケースがあるのです。
飛来した鳥がベランダの手すりに留まれないようにする便利グッズや野良猫除けシートなど、野生生物が家に寄り付きにくくする工夫をすると虫対策になります。定期的に家の周りを清掃し、清潔を保つことも大切です。
家具や収納の中で繁殖
タンスや押し入れ、衣装ケースなどは湿気が溜まりやすく、虫が湧きやすい場所の代表例です。湿気が高いとダニやカビが発生し、カビを食べるチャタテムシも湧きます。とくに、収納家具の中にものをいっぱいに詰め込み、出し入れしない状態だと空気が循環しないので湿気が溜まりやすくなります。
衣替えや大掃除のタイミングに、収納の中をチェックしてみましょう。引き出しの中身をいったんすべて取り出してから風を通して拭き掃除をすると、家具内のカビや虫を予防することが可能です。
また、本棚や押し入れに入れっぱなしの本には、紙虫(シミ)という害虫が湧くことがあります。紙虫を防ぐには、本棚から本を取り出し、晴れた日に数時間ほど陰干しをする「虫干し」が必要です。
虫の巣がある
家の中や付近にシロアリやゴキブリなどの巣があると、これらの虫が大量発生します。シロアリは木材を食べて家を朽ちさせる害虫で、家の柱や床下、浴室など湿気の高い場所に巣を作ります。巣には数千から数万、あるいは数百万匹単位のシロアリが生息するため、専門業者の力を借りずに自分で駆除するのはほぼ不可能です。
ゴキブリの巣は冷蔵庫の後ろやガスコンロの裏、流しの下など水場がある狭い隙間に多いです。ゴキブリは集団生活をする習性を持っています。一般的な「虫の巣」らしい形状を持たずにゴキブリ同士で一か所に集まり、そこで糞を排出したり繁殖行動をしたりしています。
観葉植物から虫が湧く
観葉植物に虫が湧き、家の中に虫が増えてしまう場合があります。観葉植物の購入時には気付かなくても、葉の裏や堆肥などに虫の卵が産み付けられているケースがあるのです。また、水やりのし過ぎによって観葉植物の周囲が高温多湿になり、屋外から忍び込んできた虫が住み着くこともあります。
外からの風に乗って運ばれてきたハダニが観葉植物に湧くケースも知られており、この場合は虫の被害に防ぐことは困難といえます。定期的に観葉植物に虫がついていないか確認する癖を付けましょう。
<オススメ関連記事>
生ゴミに発生するのはこんな虫!

生ゴミを放置すると小さな羽虫やゴキブリなど、さまざまな種類の不快な虫が寄ってきます。はじめは1匹しかいなくても、根本的な対策を取らないとあっという間に大量発生してしまうので注意が必要です。
生ゴミに発生しやすい虫の特徴や、その虫がもたらす害について解説します。
うじむし
うじむしとはハエの幼虫のことで、ハエが産卵した卵から発生する虫です。高温多湿で生ゴミなどの有機物の多い場所では、うじむしが発生しやすくなります。とくに、掃除が行き届いていないゴミ屋敷や汚部屋のような環境では、ハエがよく集まるためうじむしの大量発生が見られます。
うじむしは4日~10日程度でサナギになり、さらに4日~10日程度経過すると成虫のハエになります。ハエは不潔な場所を歩き回ってサルモネラ菌や大腸菌などの病原菌を体に付着させ、それを周辺に伝播するため健康被害に注意が必要です。
羽虫
羽虫とは羽の生えている小さな虫の総称で、ユスリカやクロアリ、シロアリなどの種類があります。ユスリカは血を吸う蚊ではなく、人体への害はあまり問題になりません。
クロアリは通常は羽のない姿ですが、繁殖期に羽のある個体が現れます。家の中の砂糖などを求めてクロアリが大量発生する場合があるため、見かけたら注意しましょう。
羽虫の中で、とくに注意が必要なのはシロアリです。シロアリは前述のとおり、家の建材を食い荒らして家屋倒壊の原因にもなるため迅速な駆除が必要です。木造建築以外でもシロアリ被害が起こる危険があり、たとえばコンクリートマンションでも室内の床や壁などの木材にシロアリが繁殖することがあります。
ゴキブリ
「害虫といえばゴキブリ」と即答する人も多いのではないでしょうか。生命力、繁殖力の強いゴキブリは、駆除しようとしても俊敏な動きですぐに物陰に忍び込んでしまいます。一匹のメスが生涯に500匹前後の卵を産むと言われており、見付けたら確実に駆除することが大切です。
ゴキブリは見ていて不快なだけでなく、有害な菌やウイルスを伝播させます。サルモネラ菌や大腸菌、赤痢菌やチフス菌などを体に付着しており、家中を歩き回ってこれらをまき散らすおそれがあるのです。ゴキブリの糞や死骸がアレルゲンとなり、喘息などのアレルギー疾患をもたらす場合もあります。
お米に湧く虫
お米に湧くコクゾウムシは、3ミリメートルくらいの黒い甲虫です。口の部分がゾウの鼻に似て出っ張った形をしており、この口を使って米に穴をあけ、卵を産み付けていきます。1粒の米に1個の卵を産み、米袋の中の大量の米粒に産卵していくため、1匹見付けたときにはすでに大量の幼虫・成虫が米袋の中に潜んでいる可能性が高いです。
コクゾウムシが湧いた米を食べても人体には無害とも言われていますが、虫に食い荒らされた米粒は中身がスカスカになって美味しくなく、精神衛生面でも好ましくありません。アレルギーなど不測の事態への心配もあるため、食べることはおすすめできません。
ゴミに虫を寄せ付けないために有効な7つの対策

生活をしている中で生ゴミをゼロにすることは難しく、どんなに気を付けていても生ゴミは少なからず発生します。しかし、生ゴミの処分方法を少し工夫するだけでも、虫が寄り付きにくくなります。
次の7つを実践して、虫が住みづらい環境を作りましょう。
生ゴミを溜めっぱなしにしない
虫を寄せ付けないためには、生ゴミを溜めずに早く処分することが大切です。生ゴミを放置する時間が長いほど腐敗が進んでニオイもきつくなり、虫が集まりやすくなります。
フードロスを避け、生ゴミはできるだけ水気を切ってかさばらないようにしましょう。生ゴミはできるだけこまめに小袋にまとめて袋の口を閉じ、三角コーナーや排水溝は生ゴミをためずにキレイな状態をキープすることが大切です。可燃ゴミの収集日まで日数がある場合には、生ゴミを一時的に冷凍庫保存して凍らせておくと害虫対策になります。
もちろん収集日に出し忘れないようにすることも欠かせません。ほとんどの自治体では週に2~3回は可燃ゴミの収集があるので、溜め込まずに処分しましょう。
生ゴミの捨て方を工夫する
生ゴミを捨てるときは、できるだけニオイを発生させないことが重要です。腐敗臭の原因となる水分をできるだけ減らして、処分しましょう。手で水気を絞るだけでも効果はありますが、生ゴミを触るのは抵抗がある方も少なくないかと思います。
そんなときは、以下の方法を試してみましょう。
新聞紙に包み、ビニール袋に入れて捨てる

読み終わった新聞紙がある場合は、生ゴミの処理に使いましょう。
新聞紙に包んで捨てると、生ゴミから発生した水分が新聞紙に染み込んで、悪臭が発生しづらくなります。
また、新聞紙に含まれているインクには吸着効果があるため、臭いが抑えられるメリットもあり一石二鳥です。
新聞紙で包んだ生ゴミは、ニオイや水分が漏れ出ないよう、ビニール袋に入れて袋の口を閉じてからゴミ箱へ入れましょう。
ペットシーツにくるむ

新聞を取っていない方は、ペット用のトイレシート(ペットシーツ)を代用すると便利です。
ペットシーツはもともとトイレ用の商品のため、吸水力があり消臭加工も施されています。
そのため、生ゴミの腐敗臭や水気もペットシーツがしっかりキャッチしてくれて、臭いが漂いにくくなります。
処理の仕方は新聞紙とまったく同じで大丈夫です。
生ゴミをペットシーツで包み、ビニール袋に入れて処分します。
ペットシーツは100枚入りで1,000円程度と買いやすい値段なので、生ゴミの処分用に買うのも検討してみましょう。
食べ終わったお菓子包装にくるむ

ポテトチップスやチョコ菓子などの包装は、長期間保存するために空気を通さない構造になっています。そのため、普通のビニールより臭いが漏れにくく、生ゴミの処分にも便利です。
空気に触れない分、腐敗するスピードを遅らせられるメリットもあります。
お菓子の包装は本来なら捨ててしまうものなので、お金もかかりませんし環境にも優しいです。
新聞紙やペットシーツでくるんだ生ゴミお菓子の包装に入れて捨てれば、より臭いを抑えられます。
生ゴミを冷凍庫で保存する

ゴミ収集日まで日があくときや、旅行や帰省で留守にするときは生ゴミを冷凍保存してみましょう。新聞紙やペットシーツにくるんでもニオイを抑えられるのはもって数日なので、長期間のニオイ対策には向きません。
生ゴミを冷凍すれば、腐らないので腐敗臭が発生することもありません。
「冷凍庫に生ゴミを入れるのはことに抵抗がある……」という人は、生ゴミを小さくまとめてジップロックで密閉し、冷凍庫内の仕切りなどを活用して食品と生ゴミの保管場所を分けるというのもひとつです。
【一人暮らしの方必見】臭いの発生を防ぐ!生ごみの処分方法9選
フタ付きのゴミ箱を使う
虫の発生を防ぐには、できるだけニオイが漏れ出さないゴミ箱を使うことも有効な対策です。フタ付きのゴミ箱はニオイが外に漏れにくいだけでなく、物理的に虫が侵入しにくくする効果もあります。
キッチンであれば調理中に手を汚さずにゴミ捨てできるよう、ペダルのついたフタ付きゴミ箱が便利です。よりしっかりとニオイ漏れを防ぎたいのであれば、パッキンのあるフタ付きゴミ箱が適しています。ゴミ箱用の防臭剤や防虫剤を併用すれば、より効果的です。
防虫剤を設置する

生ゴミの腐敗臭が漏れないように気を付けていても、虫は一瞬のスキをついて侵入してきます。虫をできるだけ家に入れないために、置き型の防虫剤を活用しましょう。
玄関用に吊り下げられる防虫剤や、外置き用のゴキブリ駆除剤も市販されています。窓には、網戸に取り付け可能な防虫剤を付けると効果的です。
コバエが発生しやすいキッチンには、コバエ専用の駆除剤を置いておきましょう。駆除剤には、テープに粘着させるものや、感電させて撃退するものなど、いろいろなタイプがあります。誘因ゼリーが入った駆除剤は、置いておくだけでコバエが集まる上に、そのまま捨てられるので便利です。駆除剤はコバエが発生しやすい三角コーナーの近くに置いておくと、より効果が高まります。
お米には、米びつ専用の防虫剤を入れておくと、コクゾウムシの発生を防げます。小さな子どもがいる場合は、ハーブ由来の商品を選ぶと安心です。
シンクを清潔に保つ
虫の発生を防ぐためにも、キッチンの清潔を保つことが重要です。食材の残りやカスがシンク内に残っていたり、付着したままになっていたりすると、虫を引き寄せる原因となってしまいます。
ぬめりを除去し、食べ物のくずを残さないよう、こまめに掃除を行いましょう。シンクは、ブラシと漂白剤があれば手間なく簡単にキレイになります。
手軽で効果的なシンク掃除の手順を紹介します。
シンク掃除の手順①排水溝はブラシ、スポンジで細かい部分まで汚れを落とす

排水溝は、シンクの汚れと水が溜まる部分のため、掃除をしていても虫が発生しやすい場所です。
溜まった水で汚れが見えづらいため、ブラシとスポンジを使ってしっかり掃除しましょう。
シンク掃除の手順②三角コーナー、ゴミ受け皿も漂白剤で付け置きを

三角コーナーと排水溝のゴミ受け皿は、生ゴミを溜めておく役割があるものなので、より汚れやすいです。
生ゴミを処理した後は、三角コーナーとゴミ受け皿も漂白剤で付け置きしましょう。
細かい穴などの隙間は汚れが蓄積しやすいので、使い古した歯ブラシなどを使って汚れを落とします。
毎日でなくても構いませんが、キッチンハイターなどで定期的に除菌しておくとより安心です。
シンク掃除の手順③排水溝カバーも台所用洗剤でぬめりを落とす

ゴミ受け皿に重ねて取り付ける排水溝カバーは、シンクから流れてくる汚れやゴミがひっかかります。
そのため、思っている以上に汚れていて、ぬめりが蓄積している場合が多いです。
直接ゴミが溜まる部分ではないので、つい掃除を忘れてしまいがちになりますが、ブラシやスポンジを使ってしっかりぬめりを落としましょう。
台所用洗剤を使うと、ぬめりが落としやすくなりますよ。
ちなみに、食器洗い用のスポンジも使ったまま放置すると、雑菌が繁殖します。
使い終わったら食べ物のかすを洗い流し、キレイに洗って乾かしておきましょう。
網戸で侵入経路を防ぐ
虫が外から侵入しにくくするため網戸は隙間のできないようにしっかり閉め、隙間がある際には市販の「スキマテープ」を用いましょう。洗濯の出し入れやゴミ出しの際に網戸や玄関ドアを開けっぱなしにするのもNGです。
外から運び込んだ荷物や散歩帰りのペットの体についてた虫を家の中に運び込んでしまう場合もあるため、家に入る前に虫が付いていないかチェックするといいでしょう。
虫が湧かない食品の管理方法
果物や食パンなどの食品は密閉容器で保存して、虫が付かないようにしましょう。冷蔵保存できる食品は、冷蔵庫内で保管するとさらに安心です。水分や糖分たっぷりの食品は、ゴキブリやハエなどの虫にとって理想的なエサとなるため、剥き出しの状態で放置しないようにしてください。
とくに、小麦粉やホットケーキミックス、パン粉などはダニが発生しやすく、ダニの死骸や糞が含まれた小麦粉などを食べるとアナフィラキシーショック(重篤なアレルギー反応)が起こる危険性があります。袋の口を開けっ放しにせず、密閉容器に入れてから冷蔵庫で保管しましょう。
もちろん、食べかけの食品を部屋に置きっぱなしにするのも厳禁です。食べ終わったらすぐに片付け、ゴミ袋をきちんと密閉して虫が湧かないようにしましょう。
家に虫が湧いた時の対処法!

「家に虫が湧いてしまった!」そんなときは、被害の拡大を防ぐために次の4つの対処を取りましょう。
殺虫剤で駆除する
ゴキブリやハエなどの害虫を見付けたら、スプレー式殺虫剤で駆除しましょう。殺虫成分を散布して、速やかに駆除することができます。新聞紙やスリッパなどで叩き潰すと虫の体表面に付着した細菌などをまき散らしてしまうおそれがあるため、殺虫剤を使うことが大切です。
家の中に何匹も隠れているのを感じたら、燻煙(くんえん)剤型の殺虫剤で部屋のすみずみまで駆除するのが効果的です。けむりの中にミクロの殺虫成分が入っており、ゴキブリやダニ、ノミなどの潜むわずかな隙間でも駆除することができます。
ただし、燻煙剤型は人体への刺激感がある製品が多いです。燻煙剤の使用中は在室しない、一定時間放置後に十分な換気をするなどの注意事項をしっかり読んでから使用しましょう。
物理的に取り除く(殺虫剤を使いたくない人向け)
「殺虫剤を使うと人体への刺激感や有害性が心配……」という人は、物理的に虫を取り除いていきましょう。虫に嫌悪感がある人にはおすすめしにくい手段ですが、一匹ずつ捕まえて駆除したり、虫の湧いた食品をより分けたりする方法です。コクゾウムシの湧いた米を丸ごと処分するのも、物理的な対処法といえます。
ただし、ゴキブリやハエを叩いてつぶすのは感染症予防の観点からおすすめできません。薬剤を用いない害虫駆除の効果は限定的であるため、日頃から生ゴミ処理をこまめに行ない、家の湿気対策をこまめにするなどの予防策も徹底しましょう。
ゴミ箱に虫が湧いたときの対処法
ゴミ箱に虫が湧いたら、中身のゴミ袋を出して密閉してから処分しましょう。袋の口を閉じるときに虫が這い出してくる可能性がある際は、いったんゴミ箱の口を閉じてから屋外に運び出してから作業するのもひとつです。
中身を取り出したゴミ箱は屋外で水と洗剤で丁寧に洗ってから乾かし、消毒用スプレーを噴霧します。さらに、アルコールが完全に乾いてから虫の種類に合わせたスプレー型殺虫剤を噴霧しておけば、ゴミ箱に潜む虫や卵を効果的に駆除できるでしょう。
ゴミ箱をすみずみまで清潔にして、しっかり乾燥させれば再び屋内で使用できます。
なんでゴミ箱に虫が湧きやすいの?
ゴミ箱は虫の大好物である食べ残しや生ゴミがたっぷりと入っているため、虫が湧きやすい場所です。ゴミ箱の中は湿気がこもりやすく、さらに生ゴミは水分豊富であることが多いため雑菌やカビが増えやすくなります。その結果、腐敗が進んで強烈なニオイを発し、ニオイに引き寄せられた虫は大量のエサにありつくこととなるのです。
ゴミ箱に生ゴミを長期間溜め込んだり、定期的な清掃を怠ったりしていると、虫が湧くリスクが高まります。フタ付きのゴミ箱にする、ゴミ箱用防虫剤を使う、不衛生にならないようこまめに掃除するなどの基本的な対策によって、虫の発生を予防できます。
害虫駆除業者に任せる
殺虫剤を使ってもすぐに虫が湧いてくるのであれば、害虫駆除業者に任せるのが現実的な解決法といえます。ゴキブリやハエなどの虫が大量発生している場合、自分で完全に駆除するのは困難です。シロアリの場合は家の柱や床裏などに潜んでいるため、自力の駆除はほとんど不可能と言えます。
害虫の駆除を専門としている業者に依頼して、徹底的に駆除してもらいましょう。「ペットがいるから、殺虫剤を使っていいのか分からない」などの個別の悩みにも、プロの業者は丁寧に応じてくれます。
部屋を徹底的に片付ける
家に虫が湧いた場合、まず部屋を徹底的に片付けましょう。散らかった場所は虫の隠れ家になりやすく、清掃することで発生源を減らすことができます。床に落ちた食べ物やゴミを取り除き、家具や隅々まで掃除を行いましょう。
また、食べ物は密閉容器に保存し、ゴミはこまめに捨てることが大切です。さらに、湿気が虫を引き寄せる原因になるため、換気をしっかり行い、乾燥した環境を保つことが重要です。これらを実践することで、虫の発生を防ぐことができます。
虫が湧いた汚部屋を放置するのは危険

湧いた虫を放置していると、さまざまなトラブルにつながります。具体的なリスクを解説します。
放置するにつれ虫の駆除が難しくなる
虫がいるのに対策を取らずにいると、どんどん数が増えて完全な駆除が難しくなります。たとえば、チャバネゴキブリは1か月に1回程度の間隔で産卵すると考えられており、1回の産卵時に1つの卵鞘(らんしょう)から40匹程度の幼虫がふ化します。幼虫は60日程度で成虫となり、さらに繁殖するのです。
放置は問題の先延ばしにしかならず、いざ駆除しようと思ったときには自分の手に負えない状態になっている場合があります。
健康に悪影響がある
虫を放置した不潔な環境では、健康への悪影響が生じます。ゴキブリやハエなどの体に付着した病原菌が感染症をもたらしたり、虫の糞や死骸によるアレルギー疾患になったりするおそれがあるため注意が必要です。
数匹の虫ではこれらの健康被害が起こることは稀ですが、虫を放置して大量発生が起きれば健康被害の危険性は高まっていきます。
また、健康被害が心配されるほどゴキブリやハエが大量発生している状況では、家の中が汚部屋化している可能性も高いです。この場合には健康被害リスク軽減のためにも、目の前の虫を駆除するだけでなく根本的な部屋の清掃も必要となります。
近隣とのトラブルに発展する
虫は家の境界線など無視して好き勝手に移動するため、自分の家で湧いた虫がご近所さんの家に移動して近隣トラブルになる可能性があります。
地続きである以上、家と家の間である程度虫が行き来するのは自然なことです。しかし、外観からしてゴミ屋敷化しているようなケースでは「この家が害虫の発生源になっている」とクレームが入るかもしれません。
自宅の庭に生ゴミを放置して腐敗臭を発生させた場合にも、ニオイや虫の問題で近隣関係が悪化する可能性が高いです。
マンションがゴミ屋敷になったらどうする?隣人トラブルのリスクや対策方法を解説
虫が湧く部屋を片付ける

虫が湧いてしまったら、次の4つの手順で部屋を片付けていきましょう。次に解説するコツと手順に沿って片づけを行い、自力での片付けが難しい場合には汚部屋清掃のプロへの依頼を依頼することをおすすめします。
道具を準備する
部屋の片づけに必要な道具を用意しましょう。ゴミ袋と殺虫剤、消毒用アルコール、軍手、マスク、汚れていい服と雑巾、紙類をしばる紐、雑巾、荷物保管用の段ボール箱に加えて、自分の必要だと思う道具を準備しておきます。
道具の用意をしつつ、片付けの手順も考えておきましょう。虫の発生源になっている場所を最優先で片付け、虫の湧きそうな場所を次に片付けていくなどの段取りを組んでいきます。自治体のゴミの収集日も確認して、出たゴミをすぐ捨てられるようにタイミングを考慮しましょう。
水回りを片付ける
キッチンや浴室、洗面所などの水回りは虫が発生しやすい場所なので、優先的に片付けましょう。水回りにはチョウバエが発生しやすく、チョウバエが何匹か飛んでいるようであれば排水溝や浴槽の裏などの場所が発生源になっている可能性があります。発生源を特定して、70度程度の高温のお湯をかけて卵や幼虫、成虫を死滅させます。熱湯の代わりにカビ取り剤を用いるのも効果的です。
水回りに虫の発生が見られない場合でも排水溝のゴミやヘドロを丁寧に取り除き、台所用洗剤や浴室用洗剤など、その場所に適した洗剤で清掃しましょう。
思い切って断捨離する
虫の湧きやすい押し入れやタンスの中身を整理して、思い切って断捨離しましょう。収納家具は湿気が溜まりやすく、湿気を好む虫の住み家になりやすい場所です。不用なものを処分して風通しを良くすると湿気対策になりますし、物を出し入れするという作業自体が空気の循環をよくします。
キッチンの食品棚も、期限切れの食品や袋の口が空いたまま放置している粉物の食材がないかなどをチェックして断捨離しましょう。ものを減らせば部屋の掃除をしやすくなり、虫が発生しにくい環境づくりにつながります。
汚部屋片付け業者に依頼する
手順に沿って片付けたいと思っていても、汚部屋化が進んでいると自力では解消できないものです。虫が湧く部屋を今すぐきれいにしたいなら、汚部屋やゴミ屋敷の片付けを専門とする業者に依頼してみましょう。気になる業者を選んで電話やインターネットで問い合わせを行い、予約すればあっという間に一部屋まるごときれいになります。
汚部屋清掃の費用は部屋の状態や片付ける範囲などによって異なりますが、一般的には1部屋50000円程度が目安です。スタッフ1名または2名体制で訪問し、ゴミの仕分けや搬出までの一連の作業を4~5時間程度で行ってくれます。
虫の湧いた部屋の片付けはゴミ屋敷バスター七福神がおすすめ

虫の湧いた部屋の片づけなら、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください! 仕事が忙しくて片付けをする時間がない人や、汚部屋生活から脱出したい人、家族やご近所さんにバレずに部屋を片付けたい人など、さまざまなニーズにお応えします。
最短即日で汚部屋が片付く
ゴミ屋敷バスター七福神は、最短即日で汚部屋の片付けが可能です! 関東8県、関西6件、東海4県、東北1県のご依頼に対応しており、お急ぎの依頼も承ります。引っ越しや転勤の期日が迫っている、来客予定日までに片付けたいなどの場合も安心してお任せ下さい。
年中無休の24時間対応で、出張料金、特急料金、深夜料金はいただきません。エリア別の追加料金などもありませんので、お気軽に無料相談・見積もりをご利用ください。
不用品の処分虫の駆除もまとめて完了
ゴミ屋敷バスター七福神なら、不用品の処分も虫の駆除もまとめてご依頼可能です。家いっぱいにゴミがあふれている場合でも、仕分けから運び出しまでスピーディに行ないます。
また、オプションでのハウスクリーニングもご用意しており、水回りやお部屋の清掃を追加で承ることも可能です! 荒れたお庭の草刈りや伸び放題の木の剪定、畳の撤去などのご依頼も可能なので、虫の発生しにくいお家作りにお役立てください。
経験豊富なスタッフがお客様のご要望と費用感をおうかがいしながら、ぴったりの片付けプランとご料金を提案させていただきます。
汚部屋が近隣にバレずに片付けられる
ご近所にバレないように汚部屋を片付けたい場合も、ゴミ屋敷バスター七福神なら安心です!
深夜や早朝の作業も追加料金なしで承っており、お客様のご要望があればスタッフが普段着で作業いたします。家の前に車を止められない、家の前に坂や階段があるなどのケースでも、もちろん問題ありませんのでご安心ください。
まとめ

家庭ゴミに虫が湧く原因として、生ゴミの腐敗臭や密封されていない食品、部屋や収納家具の湿気など、さまざまな要素が挙げられます。
ゴキブリやシロアリなど、健康被害や家屋倒壊のような害をもたらす虫も多く存在するため虫を見かけたらすばやく駆除することが大切です。
虫の発生を防ぐため生ゴミは水気を切って密閉し、溜め込まずに捨てましょう。捨て方を工夫したり、清潔なフタ付きゴミ箱を利用したりすることで虫の発生を抑えることが可能です。
虫を放置すると駆除が難しくなるため、健康被害や近隣トラブルなどが生じる前に対策を取ることが欠かせません。自分で部屋を掃除したり、プロの害虫駆除業者や汚部屋片付け業者に依頼して、清潔な環境を保ちましょう。