ゴミ屋敷対策において、ゴミ屋敷に関連する法律や条例の知識を身につけておくことは大切です。実は「ゴミ屋敷が法律に違反している」と言い切れる事例は少なく、このことがゴミ屋敷対策の難易度を上げています。法律に違反をしていないのであれば、警察や自治体が動くことも難しく、対策のしようがありません。
しかし条例が制定されている場合は、対策のしようがあります。そこで今回は、ゴミ屋敷対策における法律や条例について、全国自治体の事例付きでまとめました。
「自宅がゴミ屋敷化しているけど大丈夫なのかな?」「近くにゴミ屋敷があって何か対策をしたい」と考えている方は、この記事を参考にしてみてください。
目次
- 地域のゴミ屋敷対策を法律・条例の観点から見てみる
- ゴミ屋敷対策の条例を整備している自治体一覧
- 東京都の代表的なゴミ屋敷対策に関する条例をいくつか紹介
- 東京都以外のゴミ屋敷対策に関する条例をいくつか紹介
- 条例によるゴミ屋敷への行政代執行事例2つ
- ゴミ屋敷対策に関する条例のある自治体とない自治体がある理由
- ゴミ屋敷対策のために条例を制定する3つのメリット
- ゴミ屋敷対策のために条例を制定する2つのデメリット
- ゴミ屋敷対策のために条例を制定する4つの問題点
- ゴミ屋敷条例の問題解決のための2つのポイント
- ゴミ屋敷対策条例に関する豆知識
- 実家がゴミ屋敷の場合は市役所や行政に頼るしかない?
- ゴミ屋敷対策に関する法律・条例についてのまとめ
地域のゴミ屋敷対策を法律・条例の観点から見てみる
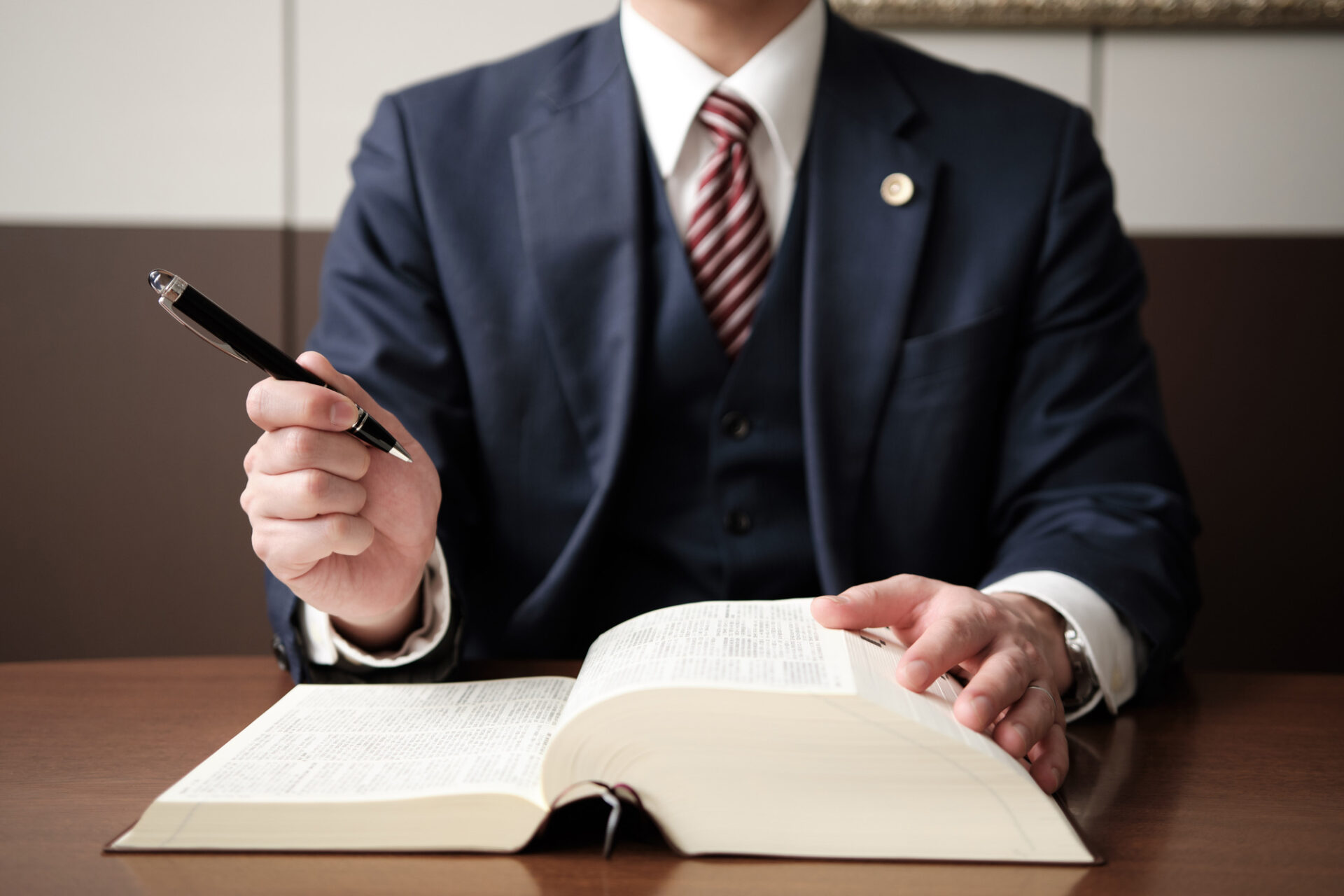
ゴミ屋敷は多くの人にとって好ましいものではないでしょう。しかし、感情論ではなく法律的な見地から考えると、実はゴミ屋敷だけでは違法とは断定できません。つまり何の対策もできません。
近隣住民にとってゴミ屋敷は迷惑です。しかし、「迷惑」は主観的なものであって、何らかの法律に違反している訳ではありません。
ですから、ゴミ屋敷を相手に司法や警察が対策を取ったり、動いたりすることはできないのです。裏を返せば、法律では解決できないからこそ、条例化して対策しようとしている自治体が増えているとも考えられます。
法律では対応できないからこその条例
条例は制定されている自治体に於いては、法律と同程度の拘束力を有します。罰則まで規定していれば、条例に基づく罰則を科すこともできますし、罰則が抑止力となって問題を未然に防ぐこともできます。
ゴミ屋敷対策の条例を整備している自治体一覧

法律での対策ができないからこそ、ゴミ屋敷問題の解決・対策は自治体による条例化が肝となります。実際、多くの自治体にてゴミ屋敷のための条例が制定されています。
そこで、全国の自治体が制定しているゴミ屋敷に関する条例の一覧をご紹介しましょう。
【ごみ屋敷に対する条例について】「ごみ屋敷」に関する調査報告書から分かること
関連記事:【ごみ屋敷に対する条例について】「ごみ屋敷」に関する調査報告書から分かること
東京都の代表的なゴミ屋敷対策に関する条例をいくつか紹介

続いては、東京23区のうち、6つの区で実施されているゴミ屋敷対策に関する条例を見てみましょう。
東京都荒川区のゴミ屋敷対策条例
東京都荒川区では、以下の条例でゴミ屋敷問題の対策を行っています。
荒川区良好な生活環境の確保に関する条例
こちらは行政代執行、さらには代執行実行時の費用請求についてまで条例で制定しています。上記の条例はゴミ屋敷対策だけではなく、環境全般に関する条例です。 それでも、行政代執行や費用請求まで制定している点に荒川区の本気度が伺えます。
東京都足立区のゴミ屋敷対策条例
東京都足立区では以下の条例を制定し、ゴミ屋敷問題の抑止力・対策をと考えています。
足立区生活環境の保全に関する条例
上記条例の特筆すべき部分は、名称からも分かるように環境保全のための条例です。それでも、ゴミ屋敷対策のために、荒川区と同様に行政代執行、さらには代執行の費用請求について条例化しています。加えて、支援の方法まで条例として定めている点は特筆すべき点です。
ゴミ屋敷は度々再発がみられますが、支援まで定めているのは、ゴミ屋敷対策だけでなく再発防止まで考えているからにほかなりません。
東京都新宿区のゴミ屋敷対策条例
東京都新宿区では「新宿区空き家等の適正管理に関する条例」が定められています。名称からもわかるように、ゴミ屋敷対策だけに主眼を置いたものではありません。空家対策の一環として、ゴミ屋敷の予防や対策も条例として定めています。
ゴミ屋敷は決して住人がいる家屋だけではなく、空家で発生するケースもあります。そこまで検討して、空家まで条例の対象範囲を広げているのでしょう。また、新宿区でも荒川区や足立区同様、行政代執行まで制定しているのですが、代執行の費用拠出・請求に関しては制定されていません。
東京都豊島区のゴミ屋敷対策条例
東京都豊島区では「豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例」が制定されています。建物を適正に維持管理するという観点から、ゴミ屋敷対策にも切り込んでいる条例です。
こちらも代執行まで条例化されていますが、代執行の費用や支援・再発防止策は見当たりません。それでも、緊急安全措置での費用は請求できるとありますので、代執行以外の対策での費用請求も可能と解釈できるでしょう。
東京都品川区のゴミ屋敷対策条例
東京都品川区では「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」が定められています。
新宿区同様、空家問題対策の観点からゴミ屋敷対策にもアプローチしている条例です。代執行も明文化されているのですが、費用請求に関しては記述がありません。それでも、支援については記載があります。
東京都世田谷区のゴミ屋敷対策条例
東京都世田谷区では「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」が制定されています。住居管理、生活環境保全の観点からゴミ屋敷対策にアプローチしています。
代執行に関しての記述がありませんが、区長権限で「必要な措置が可能」との文言が盛り込まれています。
東京都以外のゴミ屋敷対策に関する条例をいくつか紹介

東京23区以外の自治体でもゴミ屋敷対策に関する条例を制定しています。ここでは、6つの府県が実施しているゴミ屋敷対策に関する条例を見てみましょう。
神奈川県横浜市のゴミ屋敷対策条例
「市」としては全国最多の人口を誇る横浜市。東京のベッドタウン的な街もあれば、独自の発展を遂げている街もあるなど「住みたい街」として挙げられることの多い横浜市には「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)」が用意されています。
ゴミ屋敷対策だけではなく、ゴミ屋敷住人の背景まで踏まえ、福祉的側面や市・区役所と関係機関、さらには地域住人が連携するなどしてゴミ屋敷居住者に寄り添った支援を行える条例となっています。
大阪市のゴミ屋敷対策条例
大阪市では「大阪市住居における物品の堆積等による不良な状態の適正化に関する条例」が制定されています。行政代執行、さらにはその費用請求まで明文化されています。
京都市のゴミ屋敷対策条例
京都市では「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」が制定されています。京都市のゴミ屋敷対策に関する条例には、全国的に珍しいものがあります。それは過料を制定している点です。
行政代執行、さらには代執行実行時の費用請求に加え、命令違反者は50,000円以下の過料に処すと明文化されています。ゴミ屋敷対策を含めた環境問題において、個人を相手に過料を制定している自治体は多くありません。
愛知県豊田市のゴミ屋敷対策条例
愛知県豊田市では「豊田市不良な生活環境を解消するための条例」が制定されています。実は豊田市ではゴミ屋敷対策に関する問題が顕在化したことがありました。それで、代執行を含めたより具体的な条例となっています。
行政代執行や費用請求だけではなく、地域の役割、さらには京都市と同様、過料も制定しています。
福島県郡山市のゴミ屋敷対策条例
福島県郡山市では「郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例」が制定されています。郡山市でもゴミ屋敷対策に関する問題が顕在化した過去があります。それで、より具体的な内容のゴミ屋敷条例となっています。
行政代執行や費用負担はもちろんですが、先述した京都市や豊田市同様、過料も制定されています。ただし過料に関しては、立ち入り調査の拒否や立ち入り調査時の虚偽陳述が対象となっています。
秋田県秋田市のゴミ屋敷対策条例
秋田県秋田市では「秋田市住宅等の適切な管理による生活環境の保全に関する条例」が制定されています。こちらも行政代執行、さらには費用の請求まで制定されています。ただし、支援策や再発防止、さらには地域との連携に関しては特に記述は見当たりません。
条例によるゴミ屋敷への行政代執行事例2つ

ゴミ屋敷対策においては、条例に基づいて、行政代執行が行われることがあります。ここでは、京都府京都市と神奈川県横須賀市で行政代執行が行われた事例を紹介します。
京都府京都市の事例
日本で初めて、条例に基づいたゴミ屋敷への行政代執行が実施されたのが、京都府京都市左京区です。この事例では、ゴミが自宅内のみならず、私道や公道にも体積されており、自治体から120回以上の指導を受けたものの、状況が完璧に改善されることはありませんでした。
結果として、平成27年11月に行政代執行が実施されています。近隣住民の相談を受けてから、実に6年の歳月が経ったのちの行政代執行でした。
神奈川県横須賀市の事例
2018年8月、神奈川県で初めてのゴミ屋敷への行政代執行が行われました。こちらも京都の例と同じように、横須賀市による100回以上の説得に住民が応じなかった上での実施です。
一度は行政代執行によって綺麗になったゴミ屋敷ですが、3年後の2021年には再びマスメディアに取り上げられるようなゴミ屋敷へと逆戻りしてしまっています。
行政代執行が問題の根本的な解決にはならないということが具現化された事例として、神奈川県横須賀市の事例は注目されています。
神奈川県横須賀市の行政代執行については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:神奈川県横須賀市のゴミ屋敷問題|市での行政代執行後、再び
ゴミ屋敷対策における行政代執行については、以下の記事でも詳しくまとめています。ぜひチェックしてみてください。
関連記事:ゴミ屋敷に執行する「行政代執行」とは?費用なども紹介
ゴミ屋敷対策に関する条例のある自治体とない自治体がある理由

お伝えしたように、ゴミ屋敷対策に関する条例を制定している自治体もあれば、ゴミ屋敷対策に関する条例を制定していない自治体もあります。ゴミ屋敷対策問題を考えると、ゴミ屋敷対策に関する条例は「あった方が良い」と考える人も多いかと思いますが、なぜまだゴミ屋敷対策に関する条例を制定していない自治体があるのか、その理由をいくつかご紹介しましょう。
ゴミ屋敷対策に関する問題が顕在化していない
ゴミ屋敷対策に関する条例があればゴミ屋敷問題を改善できます。裏を返せば、ゴミ屋敷問題がなければ不要な条例とも解釈できます。つまり、既に条例化している自治体は、ゴミ屋敷対策で悩まされていたので解決するために条例化したと考えることができます。
自治体は基本的に受け身です。条例とは「制定して未然に防ぐ」ではなく「問題を解決・対策するためのもの」です。地域住民が近隣のゴミ屋敷対策に悩まされている地域であれば、いち早く条例化した方が良いのですが、ゴミ屋敷対策に関する問題の無い自治体であれば、早急に条例化する必要はありません。
反対意見もあるので話がまとまらない
ゴミ屋敷対策に関する条例だけではなく、条例は市長や区長といった首長が勝手に決めるものではありません。条例を制定するためには、議会の承認が必要です。
「ゴミ屋敷対策条例に反対する人間がいるのか?」と思うかもしれませんが、条例は感情論ではなく、冷静に考えなければなりません。制定した条例を実行に移したと仮定し、そこに不都合等はないのか。冷静に精査したうえで条例を制定しなければなりませんので、反対意見だけではなく、条例の運用で穴がある等の指摘を受け、話がまとまらないケースもあります。
優先順位の問題
多くの住民がゴミ屋敷対策に悩んでいる地域であれば、条例化も早いでしょう。しかし、そこまで多くの住民が悩んでいる訳ではなく、かつ他に多くの住民が悩んでいる問題がある場合、多くの住民の悩み解決のための条例の方が優先順位が上です。
地域が抱えている問題はゴミ屋敷対策だけではありませんので、他に解決しなければならない問題がある自治体では、ゴミ屋敷対策に関する条例が後回しになってしまいます。
ゴミ屋敷対策のために条例を制定する3つのメリット

ゴミ屋敷対策に関する条例を制定している自治体が多くあることが分かっていただけたかと思いますが、ゴミ屋敷対策に関する条例を制定するメリットをご紹介しましょう。
ゴミ屋敷対策に関する問題を解決できる
先述したように、ゴミ屋敷は違法とは言い切れませんので法律では対応できません。 しかし条例を制定することで、ゴミ屋敷に対して積極的な対策が可能です。ゴミ屋敷対策に関する条例がない自治体では、あくまでもゴミ屋敷住人の自主性に委ねるしか、解決方法がありません。
自治体職員がゴミ屋敷まで出向き、綺麗に片付けるよう説得するしかありません。もちろんその言葉に強制性はありませんし、自治体はこれ以上何もできません。 しかしゴミ屋敷対策に関する条例があれば、条例に基づいて行政代執行等でゴミ屋敷を綺麗に片付けることができます。
抑止力になる
ゴミ屋敷対策に関する条例があるということは、ゴミ屋敷に対して行政がそれなりに「強権」を発動できると考えることができます。つまり「ゴミ屋敷にしたら行政が黙っていないぞ」と圧力となりますので、ゴミ屋敷の抑止力として期待できます。
ゴミ屋敷対策に関する条例がないエリアの場合、ゴミ屋敷にしてしまったところで罰則もなければ、結局は自治体職員が説得することしかできません。住人にとっては痛くも痒くもないでしょう。
しかしゴミ屋敷対策に関する条例に基づき行政代執行が行われた場合、自宅を勝手に片付けられるだけではなく、多くの自治体が行政代執行の費用請求まで制定していますので、費用まで支払うことになります。
このような処置が嫌であればゴミ屋敷にしなければよいのです。
近隣住民へのアピール
ゴミ屋敷対策に関する条例を制定することで、ゴミ屋敷対策に悩んでいる近隣住民や今後住まいをと考えている人にアピールできます。お伝えしたように、ゴミ屋敷対策に関する条例がなければゴミ屋敷の解決は住人が自発的に清掃することを期待するだけです。
近隣住民とすれば迷惑ですし、これからそのエリアに引っ越そうかと考えている人にとっても嫌な物でしょう。しかし条例があれば片付けることができますし、「いざとなれば片付けます」をアピールできます。
ゴミ屋敷対策のために条例を制定する2つのデメリット

ゴミ屋敷対策に関する条例を制定するメリットをご紹介しましたが、デメリットはないのか。考えられるデメリットをいくつかご紹介しましょう。
地域住民への圧力
ゴミ屋敷対策に関する条例を制定することで、地域住民に対してプレッシャーになってしまうのではとの声もあります。抑止力にもなれば、「汚くしたら行政が動く」と圧力をかけているのです。綺麗好きな住人であれば問題ありませんが、少々だらしない住人にとっては圧力になりかねません。
行政側のリソース
ゴミ屋敷対策に関する条例に基づいてゴミ屋敷に向き合うのは自治体の職員です。しかし、自治体の職員とて決して無限のリソースを抱えている訳ではありません。
ゴミ屋敷対策問題に向き合うことで、他の仕事が疎かになることもあるでしょう。条例を執行するのもまた、人間です。例えば年末年始や年度末等、行政が忙しい時期にゴミ屋敷対策に関する問題が勃発すると、自治体職員は激務となるでしょう。結果、他の地域サービスの質が落ちる可能性があります。
ゴミ屋敷対策のために条例を制定する4つの問題点

ここでは、ゴミ屋敷問題に対応するために条例を制定する際に直面する課題を取り上げます。多くの自治体がゴミ屋敷対策として条例の導入を進めていますが、その実施にはさまざまな問題が伴います。この記事では、実際に条例を制定する際の4つの主要な問題点を解説し、法律の運用面での課題を明らかにします。ゴミ屋敷問題を解決するためのより効果的な方法を考えるための参考となる内容です。
ゴミ屋敷の定義があいまい
ゴミ屋敷対策のための条例制定において、最も問題視される点の一つが「ゴミ屋敷」の定義があいまいであることです。この曖昧さは、条例の適用範囲を不明確にし、必要以上に広範囲に適用される恐れを生みます。例えば、誰がゴミ屋敷と認定するのか、どのような基準で判断するのかが不明確な場合、住民のプライバシーが侵害される可能性があります。また、軽微なゴミの放置でも、条例に基づく罰則が科されることがあるため、不適切な適用を防ぐための明確な基準設定が重要です。さらに、ゴミ屋敷の認定基準が異なる自治体間で不均一となれば、住民間で不公平が生じることもあります。このような問題を解決するためには、具体的かつ合理的な基準が必要です。ゴミ屋敷に関する法律の整備には、慎重な議論と調整が求められます。
地域住民との認識のずれが発生する
ゴミ屋敷対策の条例制定において、地域住民との認識のずれが問題となることがあります。住民によっては、ゴミ屋敷と認定される基準があいまいであるため、自分の家の状態が対象になるのではないかと不安を抱くことがあります。
また、地域ごとにゴミの処理方法や衛生観念が異なるため、条例が一律に適用されることに抵抗感を感じる住民も少なくありません。さらに、住民が自分の生活環境をどのように捉えているかが条例の運用に大きく影響します。
地域特有の文化や価値観を無視した一方的な判断がなされると、住民との信頼関係が崩れ、逆効果を招く可能性もあります。したがって、条例制定に際しては地域住民の理解と協力を得ることが不可欠です。住民との認識のずれを防ぐためには、十分な説明と意見交換が重要です。
罰則の多くが過料でしかない
ゴミ屋敷対策の条例制定において、罰則が過料にとどまることが問題視されています。過料は金銭的な罰則であり、実際に生活困窮者や高齢者などがゴミの処理をできない場合には、罰則が逆効果となる可能性があります。
例えば、経済的な理由でゴミを処理できない場合、過料を支払えないことでさらに生活が困窮し、問題が悪化する恐れがあります。これにより、罰則が問題解決に結びつかず、むしろ住民の負担を増加させてしまいます。
さらに、過料は必ずしもゴミ屋敷の根本的な原因に対処するものではなく、行政が求める対応を強制する手段としての効果も限られます。このため、罰則に代わる支援策や、改善のための具体的なアプローチを並行して実施することが重要です。罰則だけではなく、問題解決に向けた支援体制の充実が求められます。
「通い」の場合には対応できない
ゴミ屋敷対策の条例制定において、「通い」の場合には対応が難しいという問題があります。ゴミ屋敷の状況が悪化している場合、住民が常にそこに住んでいない場合でも、外部からゴミを持ち込んでいるケースがあるからです。
例えば、親の家に頻繁に通っている場合、その家がゴミ屋敷化しているといった状況では、住民が実際に住んでいないため、条例の適用が難しくなります。さらに、住民のプライバシーや自由を侵害せずに問題を解決することは困難です。
このため、条例では住民が住んでいない場所の管理について十分に対応できないことがあります。このような場合、他の方法で支援を行う必要があり、例えば、地域住民や家族の協力を得て、ゴミの処理を促進する施策が求められます。条例の適用範囲を広げるだけでは不十分で、柔軟な対応が求められます。
ゴミ屋敷条例の問題解決のための2つのポイント

近年、ゴミ屋敷問題が深刻化しており、自治体は条例を制定して対応しようとしています。しかし、実際にゴミ屋敷を取り締まるためには、いくつかの課題が存在します。特に、住民のプライバシーとのバランスや、罰則の適用方法など、効果的な対策を取るための難しさが浮き彫りになっています。ここでは、ゴミ屋敷条例の問題解決に向けた2つのポイントについて詳しく解説します。
地域住民によるゴミ屋敷条例の理解
ゴミ屋敷対策のための条例制定において、地域住民の理解が重要な課題となります。条例が制定されても、住民がその内容や意義を十分に理解していなければ、効果的な運用は難しくなります。
特に、条例の適用基準や罰則の内容について、住民が誤解したり、反発したりする可能性があるため、十分な説明と理解を深めることが求められます。地域によっては、ゴミの処理方法や環境衛生への意識が異なるため、条例の目的や必要性をしっかりと伝えることが必要です。
また、条例が施行されることによって、住民間で不公平感や不満が生まれないようにするため、地域住民との対話や意見交換の場を設けることが有効です。地域住民の協力と理解を得ることが、ゴミ屋敷対策条例の成功に繋がると言えるでしょう。
地域コミュニティとの一体感
ゴミ屋敷対策のために条例を制定する際、地域コミュニティとの一体感が重要な問題となります。地域住民が協力し、共に問題に取り組むことが求められますが、条例が強制的な手段として作用する場合、住民の間で対立や不信感が生じる可能性があります。
特に、地域の文化や価値観が異なる場合、一部の住民が条例に対して反感を抱くことが考えられます。このような状況では、地域コミュニティ全体の協力を得ることが難しくなり、条例が機能しにくくなります。
そのため、条例制定に際しては、住民との対話や意見交換を通じて、共感と理解を深めることが不可欠です。地域全体が協力し合い、ゴミ屋敷問題を解決するための一体感を醸成するためには、条例だけでなく、地域のネットワークや支援体制を強化することも重要です。
ゴミ屋敷対策条例に関する豆知識

ゴミ屋敷対策に関する条例が如何に住民生活に直結したものであるかが分かっていただけたのではないでしょうか。そんなゴミ屋敷対策に関する条例について、豆知識をいくつかご紹介しましょう。
全国初のゴミ屋敷対策条例は?
今でこそ多くの自治体にて制定されているゴミ屋敷対策に関する条例ですが、全国初となったのは足立区です。2013年、「足立区生活環境の保全に関する条例」として制定された条例が、いわゆるゴミ屋敷対策に関する条例としては全国初のものとなります。
2013年といえばまだまだ「ゴミ屋敷」という言葉そのものもさほど浸透していない時期でしたが、既に足立区ではゴミ屋敷に悩まされている住人がいたことから、条例化されました。
大都市なのにゴミ屋敷対策に関する条例がないのは?
ゴミ屋敷対策に関する条例は、お伝えしたように「ゴミ屋敷に悩まされている自治体」にて条例化されているものです。そのため、都市の規模は関係ありません。
例えば全国でも有数の大都市・さいたま市にはゴミ屋敷対策に関する条例がありませんし、決して大都市ではなくともゴミ屋敷対策に関する条例を制定しているところもあります。
つまり、ゴミ屋敷対策に関する条例が制定されていないさいたま市ではゴミ屋敷に悩んでいる方が少ないことから、条例の制定には至っていないことが予想されます。
しかし、今後さいたま市でもゴミ屋敷が増加し、多くの住人が悩まされるようなことになればゴミ屋敷対策に関する条例制定に向けて動き出すことでしょう。
実は「ゴミ屋敷対策条例」は存在しない?
先に各都市の条例の紹介でお伝えしたように、厳密には「ゴミ屋敷対策条例」ではなく、それぞれ都市によって名称、さらには中身も微妙に異なります。どの都市でも「いわゆるゴミ屋敷対策条例」といった表現はしているのですが、「ゴミ屋敷対策条例」との名称にて条例を制定しているエリアはありません。
「ゴミ屋敷」の名称は広く知れ渡るようになりましたが、自治体の条例として採用するには少々不適切なのでしょう。そのため、条例の名称には「ゴミ屋敷」は含まれていませんが、想定しているのはゴミ屋敷なので、「いわゆるゴミ屋敷対策条例」といった形で紹介されることが多いです。
ゴミ屋敷対策条例に基づいて行政代執行が行われたことはある?
行政代執行まで明文化されているゴミ屋敷対策に関する条例のある自治体では、指導や勧告等でゴミ屋敷が改善されない場合には行政代執行、つまりは行政による強制的なゴミ屋敷清掃・片付けとなりますが、実際に行政代執行が行われたこともあります。
決して抑止力的に制定されているだけではなく、実際に実行した自治体も多々ありますので、決して「条例化しているだけで実際にやる気がない」訳ではありません。
ゴミ屋敷対策に関する条例が見直されることはある?
ゴミ屋敷対策に関する条例に限らず、条例は実情に見合っていなければ見直されるものです。そのため、もしもゴミ屋敷対策に関する条例が地域住人のニーズ、環境、時代背景にマッチしていないものになれば見直されることもあるでしょう。
これまでも、一般的な環境に関する条例をゴミ屋敷にもある程度対応できるよう文言を加えた自治体は多々あります。逆に、制定したゴミ屋敷対策に関する条例を停止・廃止した事例はありません。その点では、ゴミ屋敷対策に関する条例は時代に求められている条例だと判断できます。
実家がゴミ屋敷の場合は市役所や行政に頼るしかない?

実家がゴミ屋敷になっていて困っている方の中には「近隣住民の迷惑になっていないか」「いずれ行政から指導を受けるのではないか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「手伝うから一緒に片付けよう」と言っても拒否され、「もう行政に頼るしかないのかな」と悩んでいる方も多いでしょう。しかしここまでの解説からもお分かりの通り、自治体が行えるのは指導のみです。そして指導が受け入れられず、近隣住民にも迷惑になっていると判断された場合には、行政代執行が実施されます。
ゴミ屋敷片付け業者への依頼もおすすめ
行政代執行など、事が大きくなる前にゴミ屋敷を片付けるには、ゴミ屋敷片付け業者への依頼がおすすめです。家族がゴミ屋敷片付けの手伝いを断るのは「家族に迷惑をかけたくない」「身近な人に汚い部屋を見られたくない」といった心理が働くからです。
ゴミ屋敷片付け業者であれば、会うのはその日限りですので、そういった心配なく、ゴミ屋敷を片付けられます。
またゴミ屋敷片付け業者であれば、1日でゴミ屋敷の片付けが完了します。以下の記事にて、ゴミ屋敷片付け業者の選び方をチェックしてみてください。
関連記事:ゴミ屋敷片付け業者の選び方|ポイントや注意点を徹底解説します
ゴミ屋敷対策に関する法律・条例についてのまとめ

ゴミ屋敷対策に関する条例とは、ゴミ屋敷改善を目的とされた条例です。全国各地のゴミ屋敷問題を受け、ゴミ屋敷対策に関する条例を制定した自治体は多々ありますが、条例の文言は各地域によって異なります。
これは条例が地域生活に根付いたものであることから、各地域の問題に合わせて条例化される点にあります。そもそも、ゴミ屋敷が問題化していない地域にはゴミ屋敷条例はありません。
条例は法律ではなく、地域のルール的なものです。つまり、地域の実情に合わせたものになりますので、どのようなゴミ屋敷対策に関する条例を制定しているのかを見ることで、各地域のゴミ屋敷問題が見えてくるとも考えられます。




