「物を捨てられなくて部屋がどんどん狭くなる」
「ついコレクションを増やしてしまい、どうしてもやめられない」
など、収集癖をどう治せばよいのか悩んでいませんか?
物を手放せないのは単なる性格だけではなく、不安やストレスが影響しているケースもあります。収集癖を放置すると物だらけになり生活環境が圧迫されて、家族関係などに悪影響が及ぶことも少なくありません。
そこで今回は、物を溜め込む心理や特徴を踏まえた収集癖の治し方を具体的に解説します。病気が隠れている可能性や、無理なく片付けるコツも紹介するのでぜひ参考にしてください。
<この記事で分かること>
- 収集癖の人の特徴と心理状態
- 収集癖の思わぬデメリットと病気の可能性
- 実戦的な収集癖克服法6選
- 片付けをプロに頼むメリット
目次
「収集癖」とはどんな状態?

収集癖とは、必要以上に物を集めてしまう状態を指します。ただの「趣味の収集」というレベルを越えて、生活に支障をきたすほど物を集めすぎてしまい、整理整頓ができなくなるのが特徴です。
収集癖というとアニメやアイドルのグッズを集める「オタク」のようなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実際には日用品や雑誌、調理器具など収集対象は多岐に渡ります。特定分野の道具やアイテムに関心を寄せて、つい集めたくなる傾向が見られます。
「好きだから持っていたい」というポジティブな気持ち以外にも、いつか使うかもしれないという執着や、捨てることへの不安感から手放せなくなり、気づけば部屋が物だらけになっている人も多いです。
収集癖がある人の特徴

収集癖のある人には、共通する特徴があります。それぞれの特徴について、理由や心理的背景とあわせて解説します。
もったいない精神が強く、物を捨てるのが苦手
まだ使えるから、壊れていないから捨てられないという「もったいない精神」が強い人は、物をため込みやすい傾向があります。物を大切にするのはすばらしいことですが、行き過ぎには注意しなければなりません。家の収納力を考えずにため込んでしまうと、住環境が圧迫されて生活に支障が出てしまいます。
もったいない精神は、戦後の物不足を経験した高齢者世代に多く見られると言います。物を粗末に扱うことに抵抗感を感じ、所有することについ固執してしまうのです。
もったいない精神の強い人は「捨てるのはもったいない」と考えがちですが、実は物だらけの部屋は空間の価値を活かすことができないのでむしろ「もったいない」状態と言えます。
片付けられない人はどんな精神状態?ストレスや病気が関係していることも
物への執着心が強いオタク気質
推しのアニメキャラクターやアイドルのグッズなど、趣味の対象に強い愛着を持つ「オタク気質」の人も収集癖の傾向が見られます。関連アイテムを揃えて、自分の世界を完成させたいという心理が働くためです。
しかし、収集が行き過ぎると収納スペースの確保や金銭面での負担が増して、生活に支障が出てしまいます。趣味そのものを否定する必要はありませんが、場当たり的に集めるのではなく、取捨選択して入手したり処分したりすることが大切です。
また、趣味が変わってそのキャラクターやアイドルから卒業したときは、ため込まずに手放す意識が欠かせません。
オタクの汚部屋を片付ける極意と手順|片付ければオタ活は充実する
限定品に弱く、流行にも敏感
「限定」「コラボ」「数量限定」などの言葉に心を動かされやすい人も、収集癖を持っていることが多いです。レアなアイテムを手に入れると一時的な満足感や優越感を得られるので、ついつい購入してしまいます。
とくに現代はSNSや通販サイトから大量の情報が得られるため、収集意欲が高まりやすい環境になっています。流行に敏感な人ほど情報が早いので、収集癖にも注意が必要です。
入手時の快感は一時的なものに過ぎず、後から「本当は必要なかったのに買ってしまった……」と自己嫌悪に陥る人もいます。限定品戦略や情報に踊らされず、自分が本当に必要としている物だけを手に入れるよう意識しましょう。
収集癖のある方の心理状態

収集癖の背景には不安や孤独、承認欲求など満たされない部分を埋めようとする心理が潜んでいることがあります。ここでは、どんな心理状態が収集癖を加速させやすいかを解説します。
自分が買わなくては…という義務感がある
収集癖がある人の中には「推しを支えるために自分が買わなければ」、「このシリーズは全部揃えなければ」といった義務感に駆られている人がいます。
とくに、責任感が強く完璧主義的な傾向がある人は、義務感を強く感じることが多いです。「本当はもう飽きた」「収集をやめたい」と思っていても、不義理を働くような気がしてつい収集し続けてしまうのです。
義務感でコレクションをやめられなくなっている人は、実際は誰からも購入を強制されていないのだと意識しましょう。自分で自分に義務を課しているだけなので、無理に買う必要はないと気づくことが大切です。
寂しさや不安を埋めたい
孤独を感じると、心の隙間を埋めるために何かを集めようとすることがあります。自分の好きな物を集めて自分専用の空間を作ると、安心感や高揚感を得られるからです。
とくに、ひとり暮らしや多忙な生活、人間関係の希薄な環境などでは物を集めることが心の拠り所になりやすいです。新しいグッズを手に入れると一時的に安心しますが、やがてまた不安が戻って他のグッズを集めてしまいます。
悪循環を根本的に断ち切るには、人とつながる、ストレスを発散するなど収集以外の安心源を増やすことが欠かせません。
ゴミを片付けられない人の特徴6選!精神状態か心理状態なのか?改善策とあわせて解説
内向的で寂しがり屋
内向的な性格の人は、外の世界と関わるより自分の世界に没頭して安心感を求める傾向があります。自分が関心を寄せるジャンルのアイテムを集めることで、心を満たそうとするのです。
そして、他人との関わりの中でストレスや疎外感を感じると収集による安心感を求めて、つい部屋を物だらけにしてしまいがちです。無理に外交的になる必要はありませんが、信頼できる相手を見つけて少しずつ交流を増やすと心のバランスを取り戻しやすくなります。
収集し、揃えて満足感を得たい
特定のアイテムを完璧に揃えて、コンプリートした達成感を得たいという人もいます。何かをやりとげたときや楽しいとき、人間の脳からは「ドーパミン」という快楽物質が分泌されます。ドーパミンが分泌されると、脳はさらにドーパミンを得ようとして同じ行動を繰り返そうとするのです。
収集をやりとげると大きな満足感が湧きますが、次のシリーズや新作が出るたびに「また集めなければ」と衝動が再燃してキリがなくなってしまいます。揃えること自体を目的にするのではなく、使用や観賞に価値を置くことが収集への執着を減らすコツです。
人より物を多く持ち、優位に立ちたい
収集癖の背景に、「価値ある物を他人よりもたくさん所有したい」という競争心や承認欲求が隠れているケースもあります。
ブランド品や高級腕時計などは、持っているだけで自分の価値が上がったように感じるものです。自尊心を満たすために、常に身に付けたりSNSで映える写真を公開したりして他人の注目を集めようとする人がいます。
しかし、他人との比較やマウントを取る行為が癖になると、満足感はどんどん薄れていくので要注意です。「他人に負けないために、もっと集めなければ」という心理に追い立てられ、浪費したり家を物だらけにしたりする危険があります。他人との比較ではなく、自分にとっての価値を基準にしましょう。
ストレスが溜まっている
日々のストレスが収集癖を悪化させているケースも多いです。仕事や人間関係などでプレッシャーが続くと、ストレス解消のために買い物や収集をしたくなるのです。一時的な気分高揚のために衝動買いやコレクションを続けていると、家中が物だらけになってしまいます。
どれだけ物を集めても、根本的なストレスが解消されない限り心は満たされません。様々なリラックス法を取り入れたり、適度に体を動かしたりしてストレスそのものを軽減するようにしましょう。
「収集癖」がもたらすデメリット
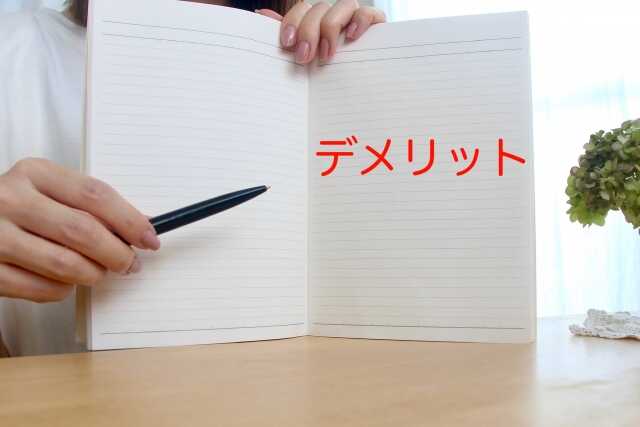
行き過ぎた収集癖は生活空間を圧迫し、人間関係や金銭面、衛生面などに悪影響を及ぼします。ここでは、代表的な5つのデメリットを詳しく解説します。
家族や友人との人間関係が悪化する
収集癖をこじらせると、家族や友人との人間関係が悪くなることがあります。物を捨てないばかりかどんどん増やしてしまうので、生活環境が狭くなって家族に大きなストレスを与えます。家族がいくら「捨てて」と頼んでも、本人が利く耳を持たなければ口論は避けられません。
また、収集にはお金がかかるため、交際費を切り詰めて友人づきあいが疎遠になってしまう人もいます。自分自身が「コミュニケーションを減らしてでも趣味を追求したい」と心から思っているなら良いのですが、本当は飽きてきたのに収集をやめられないというのなら人間関係を優先することをおすすめします。
収集にはお金がかかる
収集を続けるにはお金が必要です。1個数百円の小物でも、大量に集めていれば数万円から数十万円に膨れ上がることもあります。しかも、限定商品やレアアイテムは値段が高く、経済的負担は想像以上です。
収集癖が強すぎると、生活費を圧迫したり貯金ができなくなったりといった問題にもなりかねません。あらかじめ収集にあてる金額を決め、収集の頻度や支出を見える化してきちんとコントロールしましょう。予算を越えない健全な範囲内で収集を続けるのであれば、無理のない楽しみとして継続しやすくなります。
収集グッズで掃除や片付けがしにくい
部屋のあちこちが収集品だらけになると、掃除や片付けが極端にしにくくなります。掃除機掛けや拭き掃除のときに毎回グッズをどかさなければならず、面倒になって片付けを先延ばしがちです。
また、せっかく集めたグッズも、保管環境が悪いとほこりがたまったりカビが生えたりするおそれがあります。ハウスダストやカビはアレルギーや害虫発生の原因になるため、グッズを処分せざるを得なくなる場合もあります。
掃除しやすい空間を保つためにも、収納場所を定めて置きっぱなしにしないようにしましょう。
収納スペースが足りなくなる
収集癖の人は「まだ置ける」と思いがちですが、限られた収納スペースはすぐに限界を迎えます。収納に入りきらない収集物は机などに置きっぱなしにされがちで、暮らしにくくなってしまいます。
衣類や食器、本などが溢れ出すと必要な物を探すのに時間がかかり、生活効率も悪化します。さらに、床や廊下にまで物が侵食し始めると、生活動線が遮られて転んだり移動しにくくなったりするデメリットです。
収納量の理想は収納スペース全体の8割と言われており、2割程度の余白を残すと取り出しがスムーズになります。収納スペースがぎゅう詰めになっている人は、不要な物が詰まっていないかチェックしましょう。
汚部屋化・ゴミ屋敷化が進んでいく
収集癖を放置すると、最終的に家が汚部屋やゴミ屋敷になってしまうおそれがあります。物が積み重なって床が隠れるほどの量になると、もはや自力での片付けるのは困難です。生活動線が完全に遮断されるとゴミ捨てさえも苦痛になるため、ますますゴミをためこむ悪循環に陥りがちです。
汚部屋やゴミ屋敷では、悪臭やカビ、害虫などの衛生問題が発生して健康被害が起こることもあります。さらに、火災や事故のリスクも高まるため、一刻も早い片付けが欠かせません。自力での片付けに限界を感じたら、片付けの専門業者への相談を検討しましょう。
実は収集癖ではなく病気が原因の場合も

ただの収集癖に見えて、実際には心や脳の病気が関係しているケースもあります。病気が原因の場合には意思の力で改善するのは難しく、心療内科や精神科など医療機関での治療が欠かせません。収集行動に関係する代表的な病気を表にまとめました。
<収集癖の背景として考えられる病気>
| 病気 | 概要 | 収集行動との関連 |
| 認知症 | 認知機能、判断力が低下する。 | 要・不要の判断が付かず、不安感解消のために集める。(例:尿失禁が不安で紙ナプキンを大量に集める) |
| ため込み症(ホーディング) | 不要な物をため込み、捨てることに激しい不安を感じる。 | 無価値な物でも処分しようとすると恐怖心や苦痛が湧く。 |
| ASD(自閉スペクトラム症)、アスペルガー症候群 | 発達障害のひとつ。 こだわりが強く、対人関係が苦手な傾向がある。 | 特定の物に強く関心を持ち、こだわって集め続ける。 好きな行動を繰り返す傾向がある。 |
| ADHD(注意欠陥多動性障害) | 発達障害のひとつ。 強い衝動性や注意力欠如の傾向がある。 | 物の置き場を忘れて二度買いしたり、衝動買いしたりする。 片付けの途中で集中力が切れて散らかる。 |
| 強迫性障害 | ある考えに囚われて不安になり、特定の行為を繰り返してしまう | 「本当はいらないのに」と思っていても、耐えがたい不安に駆られて物を集めてしまう。 |
片付けられないのは病気が原因?大人のセルフチェック12と対処法を紹介
「収集癖」の具体的な治し方

なんとなく「集めるのをやめよう」「捨てよう」と思うだけでは、収集癖を治すことはできません。意志の力に頼るのではなく、物をためこみにくくする仕組みを作りましょう。
ここでは、無理なく始められる6つの改善法を紹介します。自分のできそうなものから少しずつ取り入れて、収集癖をコントロールできる習慣を身に着けましょう。
「取っておく理由」を言語化してみる
収集癖を治す上でまず大切なのは、「どうして取っておきたいのか」を自分の言葉で説明することです。「高かったから」「思い出があるから」「不安だから」など、捨てられない理由を正直に書き出してみましょう。
自分の本音に向き合って言語化すると、今でも本当に必要なのか、ただの執着に過ぎないのかなどを客観的に判断できるようになります。曖昧だった理由が明確になるだけで、物への執着が薄れてくことも多いです。
収集癖を治す第一歩として、収集した物ひとつひとつの「捨てられない理由」をチェックしてみましょう。
自分の収集傾向を「見える化」する
自分がどんな物をどんなタイミングで集めたくなるのか把握するのも、収集癖の改善方法です。ノートに記録したり、スマホで写真を撮ったりすると自分の収集パターンが見えてきます。
たとえば、「仕事の繁忙期はストレスが溜まって衝動買いしやすい」という人は、繁忙期のストレス対策を入念に行いましょう。「SNSで期間限定アイテムの情報を見ると買いたくなる」という人は、SNSを見る回数を減らすなどの対策が有効です。
収集行動のきっかけは人それぞれですが、見える化して原因が理解できれば無理なく予防することができます。
少しずつ「手放す体験」を重ねる
これまで収集してきた物をいきなり全部捨てようとすると、不安や後悔が湧いて捨てられなくなってしまいます。収集癖を治すには、無理なく少しずつ処分することが重要です。
「あまり思い入れがない」「代用品も持っている」「壊れている」など、執着せずに手放せる物から捨てていくのがおすすめです。小さな成功体験を積んでいくと、すっきり片付いた、捨てても大丈夫だったという快感や安心感が得られます。自信がつけば、より大きな物の処分にも取り組めるようになります。
収納スペースを決めてしまう
収納できる最大量を決めてしまうのも、収集癖を治す方法のひとつです。「この棚だけ」「このボックスだけ」と、あらかじめ保管場所を決めておきましょう。上限を決めておかないと、ストップが利かずにどんどん集めてしまいます。
収納場所から溢れたら購入を控え、どうしても入手したければ代わりに不要な物を捨てましょう。また、買う前に「置き場所にゆとりはあるかどうか」を考える癖を付けると、衝動買いしにくくなります。物を収める場所を決め、ルールを守り続けましょう。
毎月の収集に欠ける金額を決める
置き場所と同様に、金額にも上限を決めることが重要です。コレクションに費やす金額を毎月あらかじめ決めておき、予算を越えない範囲で収集するようにしましょう。「絶対に物を増やさない」と思うとストレスを感じやすいですが、予算を守ればOKとすれば無理なく収集行動を減らせます。
また、クレジットカードではなく現金で支払うと、「今いくら使っているか」を実感できるのでおすすめです。お金を意識的に使うことは、物への執着を手放す訓練にもなります。
収集以外のストレスを解消方法を見つける
収集癖がある人は、物を集める以外のストレス解消法を見つけることも大切です。収集癖の根底にはストレスや不安があることが多く、そのストレスや不安が根本的に解消されれば収集行動も減る可能性が高いです。
たとえば、散歩や運動、アロマテラピーや映画鑑賞、友人との会話などのリフレッシュ法を試してみましょう。自分に合ったリフレッシュ法をいくつか持っておくと、状況に合わせて柔軟にメンタルケアできるようになります。心が落ち着く時間が増えれば、自然と収集への依存心をやわらいでいきます。
収集グッズを断捨離するなら片付けのプロに頼る

これまでコレクションしてきた物を手放すには、精神的にも体力的にもかなりエネルギーが必要です。「トータルの購入金額を考えて憂うつになった」「単純に物量が多くて大変」「やっぱり捨てたら後悔しそう……」など、いろいろな気持ちが湧いて断捨離の途中で挫折してしまう人も少なくありません。
スピーディかつ確実に断捨離するなら、片付けの専門業者に相談するのがおすすめです。ここでは、プロに依頼する3つのメリットを解説します。
プロと一緒に「本当に残したいもの」を仕分ける
断捨離の判断に悩んだら、片付け専門業者に相談してみましょう。プロは第三者の視点から、残すべき物と手放すべき物を整理することができます。自分ではつい感情的になってしまい判断できない場合にも、専門家のアドバイスを受けると冷静に決断できるようになります。
とくに、思い入れのある品の断捨離や遺品整理のときには「捨てたら二度と取り戻せない」という気持ちから処分できない人が多いです。プロのアドバイスをもとに仕分けして、本当に大切な物だけを残すようにすると後悔のない片付けができます。
気が変わらないうちに手放せる
収集品を自分ひとりで片付けていると、「やっぱり取っておこう」と気持ちが揺らいでしまうことがあります。しかし、プロに依頼すると仕分けから回収まで一気に進めてくれるので、迷いが生じる前に手放せます。
作業が短期間で終わるのも、業者を利用するメリットです。自力で片付けると数週間以上かかるケースもありますが、プロなら最短即日で片付けが完了します。気が変わらないうちに収集品を引き取ってもらって家をすっきりさせましょう。
価値のあるグッズは買取も可能
買取サービスを提供している片付け業者に依頼すれば、市場価値の高いアイテムの高価買取が可能です。これまでコレクションしてきた物の中には希少なアイテムが眠っていることがあり、とくに限定グッズや未使用品は思わぬ収入になることがあります。
買取りサービスを利用すれば、売却で得た金額を片付け料金から値引けるので処分費用が安くなります。また、買取はリユースを前提としているため、自分が手放した物を誰かが有効活用してくれるのもメリットです。ただ廃棄処分するよりも、「有効活用できた」という前向きな気持ちが強くなります。
収集グッズを手放すならゴミ屋敷バスター七福神へお任せください

収集品の処分でお困りなら、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください! 年中無休の最短即日対応で、お客様のお宅に駆けつけてスピーディに回収します。
物品の仕分けや分別にも丁寧に対応しますので、「どれを残して、どれを手放すか困っている」という方はぜひご相談ください。収集品だけでなく、コレクションケースや棚、その他の家具・家電などもまとめてお引き取りが可能です。
さらに、買取サービスも充実しており、豊富な販売ルートで高価買取を実現しています。買取対象品の幅が広く、思い出の詰まった収集品も適正価格で再利用につなげられるのが弊社の強みです。ご相談・お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ

必要以上に物を集めてしまう癖を収集癖と言い、収集癖の人は生活に支障が出るレベルまで物を増やしてしまうことが多いです。もったいない精神が強い人や限定品好きな人には、収集癖の傾向が見られます。また、不安感やストレスに対抗するために、物を集めて安らぎや満足感を得ようという心理が働いていることがあります。
収集癖を放置すると人間関係や金銭面での支障が出たり、家がゴミ屋敷化したりするおそれがあります。捨てられない理由を言語化し、自分がどんな状況でどんなアイテムを収集したくなるのか記録していきましょう。収納スペースや予算を決めておくのも重要です。
自分で処分するのが大変であれば、無理せず片付けのプロに相談しましょう。取捨選択のアドバイスをもらえたり、お得な買取サービスが利用できたりします。収集癖を克服して、心と部屋に快適さを取り戻しましょう。




