建設工事や下水処理を行う際に発生する汚泥は、日本の産業廃棄物の中で約4割を占めるほど排出量が多い廃棄物です。適切に処理しなければ環境負荷が大きくなる一方、正しく処理をすることで自然環境を守るだけでなく、リサイクル資源としても活用できます。
しかし、汚泥の処理には専門的な知識が必要で、処理方法や費用、業者の選定に悩む企業も多いのではないでしょうか。汚泥の種類によっても適した処理方法が異なるため、事前に正しい知識を身につけることが重要です。
そこで本記事では、汚泥の処理方法を9つ紹介します。処理にかかる費用相場や業者の選び方についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
- 汚泥の処理方法
- 汚泥処理の費用相場
- 汚泥処理の業者の選び方
目次
汚泥の処理方法9選

汚泥はそのまま処理すると、環境負荷が大きいため、主に「焼却」「脱水」「乾燥」などの方法で減量化し、最終的に埋め立てやリサイクルを行います。以下では、汚泥の処理方法を9つ紹介します。
- 焼却処分
- 埋め立て処分
- セメント原料化
- 堆肥化
- 脱水
- 溶融
- メタン発酵
- 造粒固化
- 油水分離
焼却処分
焼却処分は、汚泥を脱水・乾燥させた後、焼却炉で燃やす方法です。まず、汚泥の水分を減らすために乾燥処理を行い、その後、約1000度の高温で焼却します。この過程で汚泥内部の有機物の大半が消え、害のない固形物質となります。
この方法のメリットは、汚泥を大幅に減量化できる点です。焼却することで最終的な廃棄物の量を減らし、コストを抑えられます。また、処理時間が比較的短いため、大量の汚泥を効率よく処理できるのも特長です。
ただし、焼却時には「ばいじん」や「燃えがら」といった二次廃棄物が発生するため、それらの適切な処理が求められます。
埋め立て処分
埋め立て処分は、再利用が難しい汚泥や、これ以上の減量が困難な場合に行われる方法です。指定された最終処分場に運び込み、汚泥の埋め立てをします。
ただし、最終処分場の容量は限られており、近年は埋め立て可能なスペースが減少しています。特に都市部では処分場の確保が難しく、埋め立てに頼ることが長期的な解決策にはなりません。そのため、汚泥を可能な限りリサイクルや減量化し、埋め立てに依存しない環境へ配慮した処理方法が求められる時代になっています。
セメント原料化
セメントには粘土が含まれており、汚泥や焼却灰の成分と類似しています。汚泥をセメントの代替原料として活用する方法がセメント原料化です。
この方法では、汚泥をセメント工場で焼成し、セメントの原料に組み込むことで、リサイクルを実現します。汚泥を無駄なく活用でき、環境負荷を抑えられるエコな処理方法です。また、焼成時の高温処理によって有機物が分解されるため、安全性が高まるというメリットもあります。
セメント原料化は、埋め立てや焼却よりも環境負荷を軽減できるため、持続可能な廃棄物管理の観点からも注目されています。
堆肥化
堆肥化とは、脱水処理をした有機汚泥を人為的に発酵させ、肥料として再利用する処理方法です。食品工場や下水処理場から発生する有機汚泥を発酵させることで、栄養豊富な堆肥として農業に活用できます。
堆肥化のメリットは、汚泥に含まれる有機物やミネラルが土壌改良に役立ち、化学肥料の使用量削減にもつながることです。近年では、肥料原料価格の高騰もあり、汚泥の肥料原料としての利用が増えています。
しかし、汚泥の中には重金属や有害物質が含まれているものもあるため、肥料の製造者は汚染物質の濃度を適切に管理することが義務付けられています。そのため、汚泥を堆肥化する前には成分分析が不可欠であり、安全基準を満たしたもののみが農業利用される仕組みとなっています。
脱水
脱水は、汚泥の水分を除去し、固形物として処理しやすくする方法です。脱水処理することで輸送コストを削減し、最終処理の効率を向上させられます。脱水方法には主に以下の2種類があります。
- ベルトプレス型:布を挟んで圧力をかけ、汚泥から水分を絞り出す方式
- スクリュープレス型:汚泥を回転させながら水分を除去する方式
脱水処理では、各脱水装置によって圧縮・ろ過し、水分を分離します。脱水された汚泥は「脱水ケーキ」と呼ばれ、焼却処理や埋め立て処分に適した形となります。
溶融
溶融は、汚泥に1400度以上の高温を加え、無害化する処理方法です。この方法では、汚泥を溶岩状にし、冷却することでガラス状の固形物「溶融スラグ」に変えます。溶融スラグには以下の2種類があります。
- 急冷スラグ:急速に冷却して形成されたもので、硬度が高く、道路舗装やコンクリートの材料に適している
- 徐冷スラグ:徐々に冷やされて形成されるもので、多孔質の構造を持ち、軽量コンクリートや土壌改良材として活用される
この方法のメリットは、汚泥中の有害物質を完全に分解し、環境への負担を大幅に軽減できることです。また、生成された溶融スラグはリサイクル可能で、建設資材やインフラ整備に活用されるため、資源循環にも貢献します。
メタン発酵
メタン発酵とは、微生物の働きを利用して有機汚泥を分解し、メタンガスを発生させる処理方法です。このメタンガスは再生可能エネルギーとして利用され、発電やボイラー燃料として活用されます。特に食品加工工場や下水処理施設から排出される有機汚泥の処理に適しており、廃棄物を減らしつつエネルギーを生産できるという点がメリットです。
近年では、メタン発酵技術の向上により、処理の効率が改善されており、エネルギーの自給自足を目指す自治体や企業が導入を進めています。ただし、メタン発酵施設の設置には広いスペースと高額な設備投資が必要なため、導入コストが課題となることもあります。
造粒固化
造粒固化は、汚泥に特殊な固化剤を加えて、リサイクル処理土として再利用する方法です。固化された汚泥は強度が増し、道路工事や建設現場での再生土木資材として活用されるほか、埋め戻し材としても利用されます。これにより、建設現場や道路工事などで発生する汚泥をその場で再利用し、資源循環を促進することが可能です。
従来の埋め立て処分と比較して環境負荷が低く、リサイクルの観点からも持続可能な処理方法として注目されています。汚泥の成分によっては固化が難しく、安全性と耐久性を確保するためには、気候や地盤条件に応じた処理方法を選択することが大切です。
油水分離
油水分離は、汚泥中の油分と水分を分離し、それぞれ適切に処理する方法です。特に飲食業や工業排水に含まれる油分の除去に適しており、環境負荷の軽減に貢献します。一般的な処理の流れは以下の通りです。
- 化学処理:生活排水などに含まれる油分を苛性ソーダなどの薬品で中和する
- 微生物処理:バクテリアを活用し、汚泥中の有機物を分解する
- 加圧浮上分離:加圧を加え、油分と水を分離し、浮上した油を回収する
- ろ過処理:複数回のろ過工程を経て浄化され、川や海へ放流される
この方法は、脱水処理と似ていますが、最初に汚泥を中和し、微生物処理をする点が異なります。油分を適切に除去することで、最終処理の負担を軽減し、リサイクル可能な汚泥の割合を増やせるのが特徴です。
汚泥の種類

汚泥は、廃棄物処理法により産業廃棄物の一つとして分類されており、適切な処理が求められます。汚泥には、有機汚泥と無機汚泥の2種類があり、それぞれ成分や処理方法が異なるため違いを把握しておくことが大切です。以下では、汚泥の種類とその発生源について解説します。
汚泥の種類
汚泥は、事業活動によって発生した泥状の物質を指し、大きく有機汚泥と無機汚泥に分けられます。法的にはこの分類が必須ではありませんが、処理業者によっては扱える汚泥の種類が異なるため、実務上重要な区別となっているのです。
有機汚泥は、生活排水や食品工場の排水処理過程で発生し、主に微生物や有機物を含んでいます。排水処理の過程で汚水中の有機物が分解される際、微生物の繁殖によって新たな汚泥が生成されることが特徴です。有機汚泥は堆肥化やメタン発酵によるエネルギー回収などのリサイクルが可能なため、環境負荷を軽減できる処理方法が求められます。
一方、無機汚泥は、建設現場や鉱山などで発生し、土砂や鉱物、金属成分を多く含みます。建設現場では「建設汚泥」とも呼ばれ、掘削工事などで発生する泥水や泥土が該当します。無機汚泥には、水銀や亜鉛などの重金属を含むものもあり、不適切な処理が環境汚染につながるため、慎重に管理しなければなりません。
汚泥が発生する業種と発生源
汚泥はさまざまな業種で発生し、その性質も業種ごとに異なります。
| 業種 | 発生源 |
| 建設業 | 掘削工事やトンネル工事で発生する建設汚泥 |
| 食品製造業 | 食品工場の排水処理過程で発生する有機汚泥 |
| 不動産管理業 | ビルの排水槽(ビルピット)に蓄積される汚泥 |
| 紙・パルプ業 | 古紙のリサイクル時に発生する製紙スラッジ |
建設汚泥は、水分を多く含んだ泥水や泥土が生じ、脱水処理が不可欠です。中には有害物質を含むものもあり、適切な処理が求められます。食品製造業では、原材料の洗浄や加工時に発生する排水を処理する過程で有機汚泥が生成されます。食品由来の有機物を多く含み、堆肥化やメタン発酵によるリサイクルが可能です。
不動産管理業では、ビルピットにエアコンのドレン水や厨房の排水が蓄積し、放置すると悪臭や衛生問題の原因になります。特にトイレの排水を含む場合は一般廃棄物として扱われ、産業廃棄物とは異なる処理が必要です。紙・パルプ業では、古紙のリサイクルや紙の製造工程で製紙スラッジが発生します。近年はスラッジをコンクリートやレンガの原料として活用する動きが進んでいます。
参考:ビルピット汚泥
汚泥の処理費用の相場とコストを抑えるコツ
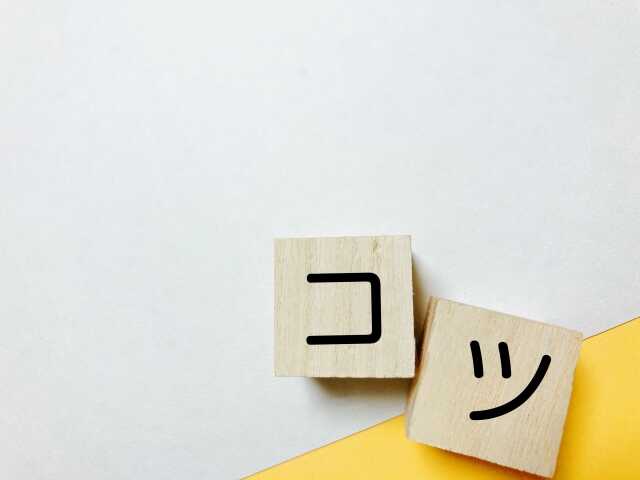
これから汚泥の処理を考えている方は、費用の相場を知っておくことが大切です。適正な価格を把握しておくことで、不要なコストを避け、信頼できる業者を選びやすくなります。以下では、汚泥の処理費用の相場とコストを抑えるコツについて解説します。
【地域別】処理費用の相場
汚泥の処理費用は1kg単位で算出されます。地域や汚泥の種類によって異なりますが、全国の相場は1kgあたり20円前後ほどです。以下にエリアごとのおおよその料金相場をまとめました。
| エリア | 費用の相場 |
| 北海道 | 16円~37円 |
| 東北 | 15円~35円 |
| 関東 | 19円~40円 |
| 甲信越 | 14円~36円 |
| 北陸 | 14円~36円 |
| 東海 | 15円~36円 |
| 関西 | 16円~37円 |
| 中四国 | 15円~36円 |
| 九州 | 14円~35円 |
汚泥の運搬費を含まない場合、処理費用は1tあたり20,000円前後が相場となります。収集運搬費用は別途かかり、運搬距離や手配する車両によって費用が変動するため、事前に見積もりを確認することが重要です。
処理コストを抑えるコツ
汚泥の処理費用は、基本的に「汚泥の重量」によって決まります。重量を左右するのは汚泥中に含まれる水分量であり、これを減らすことでコストを抑えることが可能です。汚泥の含水率を低下させ、固形物の割合を増やすことがポイントとなります。
汚泥の減量方法として、代表的なのが「乾燥」と「脱水」です。処理業者に依頼する前に、乾燥・脱水設備を導入して汚泥の水分を除去することで、処理コストを削減できます。脱水処理することで含水率を85%以下に抑えた「脱水ケーキ」の状態にするのが一般的な処理方法です。
脱水ケーキの状態にした汚泥は、焼却や埋め立て処理が容易になり、最終処分の費用も削減できます。脱水処理は比較的低コストで運用できる方法であるため、大量の汚泥を定期的に処理する事業者であれば、長期的に見てコスト削減につながるでしょう。
汚泥の処理を依頼する業者の選び方4選

汚泥の処理を業者に依頼する際は、適正な処理が行われるかを確認することが重要です。業者選びを誤ると、法的リスクや環境問題を引き起こす可能性があるため、必要な許可や料金体系などを事前にチェックする必要があります。以下では、信頼できる業者を選ぶための4つのポイントを紹介します。
産業廃棄物処理の許可を得ている
汚泥処理を行う業者は、産業廃棄物処理業・産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している必要があります。適正な処理が行われないと、汚泥を排出した企業も処罰の対象となるため、業者が許可を受けているか確認することは欠かせません。許可の有無は、環境省の「産業廃棄物処理業者情報検索システム」で検索できます。
また、汚泥には有機性汚泥と無機性汚泥があり、業者によって対応できる種類が異なります。そのため、処理を依頼する前に、自社の汚泥がどちらに分類されるかを確認し、適切な業者を選定することが重要です。
マニフェストの作成をサポートしてくれる
マニフェストとは、汚泥の適正な処理を証明する管理票であり、不法投棄や環境汚染を防ぐ目的で法律により交付が義務付けられているものです。この書類には、廃棄物の発生から最終処分までの情報が記載されます。
マニフェストには、紙ベースで管理する「紙マニフェスト」と、インターネット上で管理できる「電子マニフェスト」の2種類があります。特に、電子マニフェストは利便性が高く、処理状況のリアルタイム管理が可能です。
しかし、マニフェストの作成には一定の知識が必要なため、経験のない企業では運用が難しい場合があります。そのため、マニフェストの作成や運用をサポートしてくれる業者を選ぶと、手続きがスムーズになり、適正な管理をしやすくなるでしょう。
環境に考慮して処理できる
汚泥は企業の事業活動に伴い発生し続けるため、環境に配慮した処理が求められます。環境負荷の高い処分方法を続けると、企業のイメージダウンにつながる可能性もあるため、持続可能な処理方法を採用することが大切です。
例えば、汚泥をセメント原料として再利用したり、溶融処理を施して資源化したりする方法は、環境に配慮した処理の一例です。一方で、単に焼却や埋め立てを行うだけでは、資源循環が困難になり、環境への負担が大きくなります。現在、SDGsや環境経営が重視されるなかで、企業の社会的責任としても環境に配慮した処理方法を検討することが重要です。
料金体系を明確に提示している
業者に汚泥処理を依頼する際は、料金体系が明確であるかも確認しましょう。依頼後に想定以上の費用がかかるケースもあるため、事前に費用の内訳や追加料金の有無を把握しておく必要があります。
ただし、汚泥を適正に処理するためには、専用の装置や設備のメンテナンスが不可欠であり、それなりの費用が発生します。そのため、単に価格が安いという理由で業者を選ぶのではなく、実績や評判を確認することも重要です。特に、長期間にわたる取引を前提とする場合は、信頼できる業者と適正な価格で契約を結ぶことが、コスト管理と適正処理の両立につながるでしょう。
汚泥を処理しないと起こりうる4つのリスク

汚泥の適切な処理を怠ると、自然環境や社会に深刻な影響を及ぼす可能性があります。河川や土壌の汚染、生態系の破壊、さらには法律違反による罰則など、多くのリスクが伴います。これらの問題は、企業の信用にも大きく関わるため、適正な処理を行うことが欠かせません。
水質汚染が引き起こされる
汚泥を適切に処理せずに放置すると、雨水などによって有害物質が河川や地下水に流出し、水質汚染を引き起こす可能性があります。工場や下水処理施設から排出される汚泥には、窒素やリン、重金属などの有害成分が含まれている場合があるため、特に注意が必要です。
水質汚染が進行すると、生活用水や農業用水としての利用が制限されるだけでなく、魚介類の生息環境が破壊され、水産業にも深刻な影響を及ぼします。また、飲料水の安全性が損なわれることで、健康被害を引き起こすリスクも考えられるでしょう。
土壌汚染が引き起こされる
汚泥の不適切な処理は、土壌汚染にもつながります。特に産業廃棄物由来の汚泥には、水銀や鉛、カドミウムなどの有害物質が含まれており、長期間にわたって蓄積されると、土壌の性質が変化し、農作物の生育を妨げる原因となってしまうのです。
土壌汚染が進行すると、農地だけでなく住宅地や公園、工業用地などの利用も制限され、土地の資産価値が著しく低下します。土壌汚染は一度発生すると除去が困難であり、浄化には多大なコストと時間がかかります。そのため、汚染を未然に防止するとともに、土壌の定期的な検査を実施し、汚染の兆候を早期に発見することも重要です。
生態系に影響する
水質汚染や土壌汚染は、生態系全体に深刻な影響を及ぼします。河川や湖沼に流入した汚泥に含まれる有害物質は、魚類や水生生物の生息環境を破壊し、生物の大量死や生態系のバランスを崩す要因になる可能性があります。さらに、土壌に蓄積された有害物質は、植物の成長を妨げ、動物の食物連鎖にも悪影響を及ぼすことになるでしょう。
重金属や有機化学物質が長期間にわたって蓄積されると、植物がそれらを吸収し、それを摂取した動物や人間にも健康被害が及ぶ可能性があります。このように有害物質が食物連鎖を通じて濃縮される現象は「生物濃縮」と呼ばれ、特に食物連鎖の頂点にいる捕食動物や人間ほど影響を受けやすくなってしまうのです。
法的リスクを伴う
汚泥を不法投棄や不適切な処理をした場合、厳しい罰則が科されます。汚泥の処理責任は処理業者だけでなく、排出業者にも及ぶため、委託先の選定には慎重な判断が必要です。
不法投棄が発覚した場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。さらに、法人が違反した場合には、最大3億円の罰金が科せられます。行政指導や事業停止命令が下されることもあり、企業活動の継続が困難になるリスクも考えられるので、法令を遵守し、透明性のある処理を徹底しましょう。
汚泥の処理に関するよくある質問

汚泥の処理には、法律や手続き、処理方法など多くの疑問が伴います。ここでは、汚泥の処理に関するよくある質問を取り上げ、解説します。
汚泥の処理に関する法規制はありますか?
汚泥の処理には、「廃棄物処理法」が適用されます。この法律は、廃棄物の排出抑制と適正な処理を推進し、人々の生活環境を守ることを目的に昭和45年に制定されました。産業廃棄物としての汚泥は、事業者に適正処理の義務があり、許可を受けた業者による収集・運搬・処理が求められます。
また、下水道管理者が処理する下水汚泥に関しては「下水道法」が適用され、産業廃棄物とは異なる規制を受けます。地域ごとに細かな規定が異なる場合があるため、詳しくは管轄の自治体へ確認しましょう。
自社で汚泥を処理できますか?
汚泥は、排出した企業が適切に処理する責任を負います。ただし、自社で汚泥を処理できる施設を持たない限り、産業廃棄物処理業者に処理を委託するのが一般的です。
処理を委託できるのは、都道府県に「産業廃棄物処理業」「産業廃棄物収集運搬業」の届出を提出し、知事の許可を受けた業者のみとなります。無許可の業者への委託は違法となり、排出企業も責任を問われる可能性があるため、事前に業者が許可を受けているか確認しましょう。
自社で排出した汚泥を敷地内に埋めても良いですか?
汚泥を含む産業廃棄物を埋め立てる場合、必ず許可を受けた最終処分場で行う必要があります。最終処分場の設置には、都道府県知事の許可が必要であり、処理基準を満たした施設で適正に埋立しなければなりません。
例えば、許可を受けていない自社の敷地内に埋めた場合、それが自社の土地であっても「廃棄物処理法違反」となり、罰則が科される可能性があります。「個人所有であっても、土地そのものが公共性の高い存在であり、野放図な管理は許されるものではない」という理念から、このように法律上で定められているのです。
汚泥を再利用する方法はありますか?
汚泥の再利用方法は、有機汚泥と無機汚泥で異なります。有機汚泥にはバイオマス資源としての可能性があり、堆肥化やエネルギー回収が進められています。一方、無機汚泥は有害物質を含む可能性があり、多くは埋立処分されますが、一部は資源として活用が可能です。
| 有機汚泥 | 下水汚泥 | バイオマス資源として再利用される |
| 製紙スラッジ | 焼却灰は、路盤材やセメント原料などに再利用され | |
| 無機汚泥 | 建設汚泥 | 脱水・乾燥させた後に盛土材料などに再利用される |
| メッキ汚泥 | メッキ汚泥に含まれる金属を回収する設備開発や研究が進んでいる |
汚泥の処理でお悩みなら七福神にご相談ください

汚泥の処理でお悩みなら、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください。当社は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しており、汚泥をはじめとするさまざまな産業廃棄物の適正処理を行っています。
汚泥だけでなく、廃材、廃油、金属くずなどの産業廃棄物にも対応可能です。適切な処理方法を熟知したスタッフが、安全かつスピーディーに回収・処理を行います。
また、最短即日での回収が可能で、お客様のご都合に合わせたスケジュールで対応いたします。当日に無料でお見積もりを行い、明確な料金を提示するので、追加料金もかかりません。
「最短で回収してほしい」
「他の産業廃棄物も処分して欲しい」
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ七福神にご相談ください。
最短即日でのお伺いが可能で、当日に無料見積もりが可能です。
〈七福神の特徴〉
- お見積もりご相談0円
- 最短即日対応が可能
- 専門の自社スタッフによる作業
お問い合わせは土日祝問わず、24時間365日受け付けています。
まずは見積もりだけ知りたい方も、電話・メール・LINEからお気軽にご連絡ください。
まとめ

今回は、汚泥の処理方法について詳しく解説しました。汚泥は産業活動や下水処理の過程で発生し、適切な処理を行わなければ環境汚染や法的リスクを引き起こす可能性があります。そのため、法律に準拠した処理方法を選択し、適切な処分を行うことが重要です。
汚泥の処理には、焼却、埋立、リサイクルなどさまざまな方法があります。特に、バイオマス資源としての活用や建設資材としての再利用が進んでおり、持続可能な社会の実現に向けた新たな取り組みが求められています。企業にとっても、環境負荷を低減しつつコスト削減につながる処理方法を選択することが、これからの時代の課題となるでしょう。
汚泥処理を適切に行うためには、信頼できる業者を選ぶことが大切です。ゴミ屋敷バスター七福神なら、汚泥の収集・運搬が可能です。産業廃棄物の処理に精通したスタッフが迅速に対応し、最短即日での回収にも対応しています。 お問い合わせは24時間365日受け付けております。汚泥の処理に関するお悩みがありましたら、ぜひ七福神にご相談ください。




