「親族が孤独死したらしい……。後始末、私がしないといけないの!?」
「孤独死の後始末、どうやってやるの? お金はいくらかかる?」
など、孤独死の後始末でお困りではありませんか。
一人暮らしの高齢の増加により、孤独死は深刻な社会問題になっています。ある日突然に警察から連絡を受けて親族の孤独死を知るケースもあり、誰にとっても孤独死は他人事ではありません。葬儀や死後の手続きなど、急ぎの対応を迫られて困惑するケースも……。
孤独死の後始末には、膨大な手間やお金がかかってしまいがちです。そこで今回は孤独死の後始末を、誰がいつどのように行うかを解説します。この記事を参考に、負担を減らして効率的に後始末を進めていきましょう。
<この記事で分かること>
- 孤独死の後始末は、誰がする?
- 孤独死発見後の手続きや特殊清掃などの流れ
- 家族を困惑させる喪失・解約の諸手続きについて
- 孤独死の後始末に必要な費用の相場
目次
自宅で孤独死したら…後始末は誰がやるの?
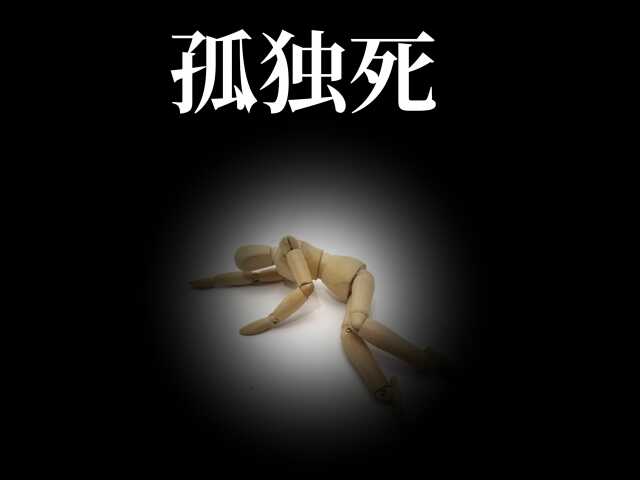
ずばりお答えすると、孤独死の後始末は故人の法定相続人や親族が行います。
故人に身寄りがなかったり、身元不明だったりする場合は、自治体が後始末を行うこととなります。また、身寄りのない人が賃貸物件で孤独死して、連帯保証人と連絡がつかない際には物件オーナーが物件関連の後始末をしなければなりません。
<孤独死の後始末は誰がする?>
| 家族関係 | 孤独死の後始末をする人 |
| 遺族がいる場合 | 法定相続人 (配偶者と子ども。いない場合は兄弟姉妹) 親族 (法定相続人以外の「息子のお嫁さん」や「甥っ子」なども含まれる) |
| 遺族がいない場合 | 自治体、賃貸物件のオーナー |
遺族がいるケースといないケースに分けて、後始末について解説します。
親族や法定相続人が行う
警察は孤独死した人の身元を調べて、親族や法定相続人に連絡をします。基本的に血縁関係が近い順に連絡が入り、連絡を受けた人は警察で検死費用を支払ったり、葬儀を手配したりといった後始末を進めることとなります。
親族が後始末をするのが一般的ですが、厳密に言うと後始末の義務があるのは親族ではなく「法定相続人」です。法定相続人は故人の配偶者や子供で、いなければ故人の親や兄弟姉妹が該当します。故人の財産は法的相続人に移行するため、後始末の費用や負担も法定相続人が追わなければなりません。
しかし実際には、相続権のない嫁や甥、姪などが後始末を任されてしまうケースも見られます。なかでも長男の嫁は、押しつけられてしまうことが多いようです。孤独死関連の費用や諸手続きは、親族間で不公平感がないように話し合うのが理想的です。
なお、故人が遺言書によって相続人を指定していた場合には、その「指定相続人」も後始末の責任を負います。
身寄りのない方の孤独死
警察が現場検証で身元などを確認して身寄りがなかった場合には、自治体が火葬するのが一般的です。特殊清掃や遺品整理は自治体から専門業者に依頼され、費用は故人の遺産から支払われます。遺産が乏しく費用が足りない場合には、自治体が負担します。
孤独死が賃貸物件で起こった場合は、連帯保証人が原状回復義務を負います。しかし、連帯保証人と連絡がつかない場合には、やむを得ず物件オーナーが費用を負担して原状回復することが多いです。
【発見から葬儀】孤独死の後始末の流れ

孤独死が発見されてから、葬儀までの流れを解説します。孤独死の連絡はある日突然に警察から来るため、頭が真っ白になってしまう人も少なくありません。
葬儀までのおおまかな流れを知っておけば、落ち着いて段取りを組めるようになります。どのタイミングでどんな書類や手続きが必要になるのか、分かりやすくまとめました。
身元確認の準備をする
警察から孤独死の連絡が来たら、警察署に出向いて身元確認をしなければなりません。そのため、まずは自分の身分証明書や、故人との続き柄を証明するための書類を準備しましょう。
身元確認の際には、次の物が必要です。
<警察署で必要となる物>
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 故人との関係を証明する物(戸籍謄本、住民票など)
- 印鑑
- 年金手帳
これらは身元確認だけでなく、葬儀などの手続きにも必要となります。なお、すべての書類が必ずしも必要となるわけではないため、警察から連絡を受けた時点で何を持っていけば良いのか確認しましょう。
警察署では、身元確認や死亡状況の説明を受けます。今後行われる遺体の引き取りや死亡届の提出などについても説明されるので、メモを取って聞きもらさないようにしましょう。
葬儀会社を手配する
警察での身元確認の後には、すみやかに葬儀会社を手配しましょう。警察は検死の完了後に死体検案書を作成しますが、遺体の腐敗が激しい場合と検死に時間がかかり、死体検案書の交付までの時間も長くなります。死体検案書を受け取らなければ死亡届を出せず、葬儀を実施することもできません。
警察から死体検案書の連絡を受けるまでに、葬儀の準備を進めておきます。警察が葬儀会社を紹介してくれる場合もありますが、自分で探すこともできます。費用を抑えたい場合には複数の葬儀会社に見積もりを依頼して、費用やプラン、サービス内容を比較検討しましょう。
葬儀会社を決めたら、葬儀の形式や日程、搬送先の火葬場などを相談します。孤独死の場合は遺体の腐敗が進んでいるため、警察で引き取った後にお通夜や告別式をせずに火葬する「直葬」形式となることが多いです。
なお、直葬の費用相場は二十万円程度であり、百万円以上かかるのが相場の一般葬と比べると格段に安くなります。
死亡届・埋火葬許可証申請を出す
警察で死体検案書の準備ができると連絡が来るので、死体検案書を受け取りに行きましょう。死体検案書は孤独死など警察で検死が行われた際に発行される書類であり、この死体検案書がないと死亡届や火葬・埋葬などの手続きを行うことができません。
死体検案書を受け取ったら、死亡届と埋火葬許可証申請を役所に提出しましょう。
| 書類 | 概要 | 提出方法 | 提出期限 |
| 死亡届 | 死亡を証明する書類 | 死体検案書を役所に持参する | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 埋火葬許可証申請書 | 遺体の火葬・埋葬に必要な書類 | 死亡届と同時に申請する | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
いずれも提出期限は「死亡の事実を知った日から7日」となっていますが、孤独死の場合は7日以上経過しているケースも少なくありません。孤独死死体検案書を警察から受け取ったら、すぐに死亡届と埋火葬許可申請書を提出しましょう。なお、葬儀会社が死亡届などの手続きを代行するサービスを用意している場合もあります。
なお、死亡届は役所に提出するため、原本は手元に残りません。保険金の請求などの手続きの際に死亡届のコピーが必要になるため、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。
孤独死があったお部屋の特殊清掃・遺品整理の流れ

孤独死の後始末の流れは、一般的な遺品整理とは大きく異なります。現場に強烈な死臭や血液・体液の痕跡などがしみついており、遺品整理の前に特殊清掃が必要となるケースが多いからです。
ここでは、孤独死現場の特殊清掃と遺品整理の流れについて解説します。
1.特殊清掃業者に依頼する
警察が検死などを済ませて許可を下すまでは、孤独死の起こった家に立ち入ることはできません。警察から立ち入り許可の連絡が来るまでに、特殊清掃業者を選んでおきましょう。
特殊清掃には8万円~数十万円の費用が必要となるため、「節約したいから自力で片付けようか」と考える人もいますが、現実的ではありません。部屋に残された死体の匂いや痕跡を消したり、血液を洗い流したりする作業は専門業者でなければほぼ不可能だからです。亡くなってすぐに遺体が回収されたようなケースを除いて、孤独死現場には特殊清掃が不可欠です。
特殊清掃業者を選ぶときは、複数の業者を比較して専門性や実績、料金、対応の丁寧さなどを考慮しましょう。孤独死現場の清掃実績が豊富で、特殊清掃士や遺品整理士などの資格を持つ業者がおすすめです。
極端に安い業者はサービスの質が低くて脱臭や清掃が不十分だったり、当日に高額な追加料金を請求してきたりするおそれがあるので注意しましょう。
2.特殊清掃終了後、遺品整理を行う
特殊清掃が終わったら、遺品整理を行います。遺品整理は、家に残された遺品を残す物と処分する物に仕分けして整理する作業です。
一般的な遺品整理に比べると、孤独死の場合は処分する物の割合が増えます。普通の遺品整理なら売却可能な家具や家電であっても、孤独死現場では腐乱臭や汚れが染みついて捨てるしかない状態になっていることが多いのです。弊社の現場担当者の話によれば、「経験上、孤独死されたお宅では遺品の8割程度が廃棄処分になることが多い」とのことでした。
なお、遺品整理は業者に依頼せずに、遺族が自力で行うことも可能です。自分達で行えば費用を抑えることができますが、時間と労力がかかる点には注意しましょう。
「すべてを自分で行うのは大変だけれど、できるだけ安く済ませたい」という場合には、自力でできる範囲の遺品整理をして、大がかりな作業を業者に頼むことも可能です。
3.残した遺品を売却または形見分けする
遺品整理のときに見つけた貴重品や価値のある物品は、遺品整理後に売却や形見分けを行います。遺品整理業者が買取サービスを実施している場合には、遺品整理の際に売却して買い取り価格分を費用から値引きしてもらうことも可能です。
ただし、前述のように孤独死現場の遺品は、匂いや汚れがしみついて売値がつきにくい傾向があります。書籍や布製品などはとくに臭いが染みつきやすいため、買い取ってもらえないことも多いです。
なお、形見分けとは、遺族や故人の友人などに思い出の遺品を分け与えることを意味します。本人の写真や手紙、生前愛用していた物などが形見分けされるのが一般的です。
形見分けは故人を偲ぶ風習ですが、受け取る人によっては「孤独死現場の遺留品を受け取るなんて……」と拒否感を覚える可能性があります。相手が「受け取りたい」と言った場合に限り、形見分けを検討しましょう。
孤独死の解約・喪失手続きは膨大
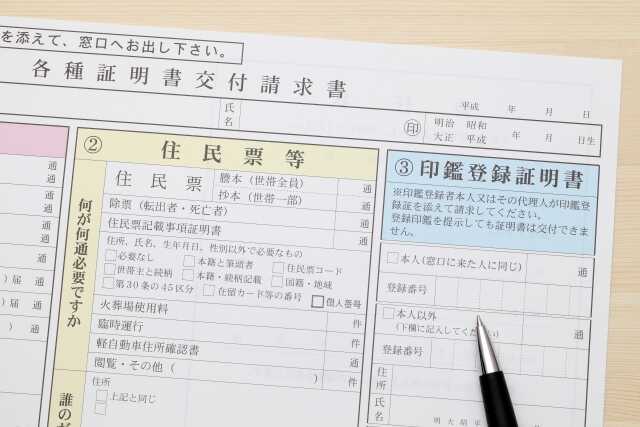
葬儀や遺品整理が終わっても、孤独死の後始末は続きます。やらなければならない解約・喪失関連の手続きは多岐に渡り、手続きが漏れると思わぬ請求などが起こる場合があるので注意しましょう。
孤独死後に必要となる手続きは、大きく分けて「行政的な喪失手続き」「公共料金などの解約手続き」「その他契約・請求の解約手続き」の3種類です。それぞれについて解説します。
世帯主の変更と住民票や各種保険等の喪失手続き
死亡届の提出や葬儀が済んだ頃から、世帯主の変更や健康保険・年金関連など行政関連の喪失・解約手続きをしていきましょう。具体的な手続きを表にまとめました。
| 手続き | 期日 | 必要書類 | 手続き場所 | 備考 |
| 世帯主の変更 (一人世帯の場合は届け出不要) | 死亡後14日以内 | 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード等)、死亡届のコピ― | 役所 | 故人が世帯主だった場合に必要 |
| 除票住民票の写しの請求 | とくになし | 窓口に来た人の本人確認書類 | 役所 | 相続手続きで使用する。相続人のみ請求可能。 |
| 年金受給停止 | 国民年金:死亡日から14日以内 厚生年金:死亡日から10日以内 | 受給権者死亡届、年金証書、死亡を証明できる書類 | 年金事務所または年金相談センター | 受給停止し忘れるとその後も給付され続け、あとで返還請求される |
| 健康保険・介護保険の資格喪失 | 国民健康保険:死亡日から14日以内 被用者保険:死亡日から5日以内 | 各種保険証、死亡届のコピー | 国民健康保険:役所 被用者保険:職場経由で手続き 被用者保険の扶養家族:家族の職場経由で手続き | 市区町村によっては、死亡届を提出すれば国民健康保険資格喪失届を出さなくても良い場合もある |
| 相続 | 相続:相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 故人の戸籍謄本と住民票除票、相続人全員の住民票と戸籍謄本と本人確認書類、遺産分割協議書、印鑑証明 | 税務署で相続税の申告・納付 | 相続放棄の場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立て |
ほとんどの手続きには、期限が定められています。孤独死の場合は期限が過ぎてしまっていることも多いため、提出可能になり次第速やかに提出することが必要です。
これらの手続きには故人の死亡届のコピーや除籍謄本などが必要になるため、事前に用意してスムーズに手続きを進められるようにしましょう。手続きしそびれると故人の年金が不正に受給されたり、税金が誤って請求されたりするおそれがあるので要注意です。
公共料金など故人が契約していたものの解約手続き
ガスや電気、水道、電話回線など、故人が契約していた公共料金関連の解約も必要です。解約するまで引き落としが継続してしまうため、各社規定に従って解約していきましょう。
ただし、孤独死のケースでは解約のタイミングに注意が必要で、特殊清掃や遺品整理が一通り済んだ後で解約することが大切です。なぜなら、孤独死現場に残った血液などの汚れを落としたり、脱臭したりするためには水道や電気などが欠かせないからです。早々と解約してしまうと後始末が進まなくなり、再度開通手続きを取らなければならなくなるので二度手間になってしまいます。
その他契約していたものの解約や請求に関する届出
公共料金以外にも、故人が契約していたものがあれば解約手続きを取っていきます。たとえば、クレジットカードや銀行口座、インターネット回線、新聞や雑誌の定期購読、アマゾンプライムや食品宅配サービスなどのサブスクリプション、民間の医療保険などが挙げられます。
解約しないと月会費などが発生し続けますが、死亡した人の銀行口座は凍結されるので引き落とし不可の状態になってしまいます。支払いの遅延による延滞料金が相続人に請求されるおそれがあるため、迅速に解約しましょう。
また、故人が生命保険に加入していた場合は死亡保険金の受け取りが可能です。加入保険の有無を調べ、加入していた場合は生命保険会社に連絡しましょう。生命保険会社から案内書類が届くので、死体検案書や受取人の戸籍抄本など、指示に従って必要書類をそろえて請求します。約款によって死後3年を過ぎると死亡保険金が受け取れなくなる場合もあるので注意しましょう。
身内が孤独死したときの費用はいくら?誰が負担するの?
身内が孤独死した場合、賃貸物件の原状回復費用や葬儀代などさまざまな費用がかかります。それらの具体的な金額や、誰が負担しなければならないかについて解説します。
賃貸の物件の原状回復費用
身内が孤独死した場合、法的には相続人が賃貸物件の原状回復費用を負担しなければなりません。一般的なハウスクリーニングに加えて孤独死では特殊清掃も必要となるため、原状回復費用は高額となります。
日本少額短期保険協会が2024年12月に報告した「第9回孤独死レポート」によると、孤独死での原状回復費用は平均474170円と決して安くはありません。部屋の状態によっては、100万円を越えるケースも報告されています。
「特殊清掃費用は敷金から出せないのだろうか?」と思う人もいるかもしれませんが、特殊清掃は敷金の対象外です。床などに生じた生活上の傷や汚れなどの通常損耗は異なり、孤独死で汚損した部屋は借主の責任によって原状回復しなければなりません。
借主が死亡しているので費用は相続人の負担となり、もし相続人と連絡がつかなければ連帯保証人に請求が行きます。連帯保証人への請求ができなければ場合、物件オーナーが支払わざるを得なくなります。
遺品整理にかかる費用
孤独死現場の遺品整理の費用負担も、相続人が負うことになります。前述の「第9回孤独死レポート」では、孤独死現場の残置物処理費用は平均295,172円と報じられています。遺品整理と原状回復の費用を合わせると、平均で80万円程度の支出となる点に注意が必要です。
最高では190万円ほどの残置物処理費用が発生しており、家の中がゴミ屋敷状態などのケースでは費用が高額になる可能性が高まります。
未払いの医療費や葬儀の費用
未払いの医療費があった場合には相続人に請求が行き、相続人と連絡がつかなければ、入院時の書類に記載した連帯保証人が支払いの義務を負います。
葬儀費用は相続人の負担です。費用は20万円~200万円程度で、通夜や告別式を行う「一般葬」は100万円以上かかります。一方、通夜や告別式をせずに遺体を火葬する「直葬」は20万円程度で済むため、費用を抑えたいなら直葬が適しています。なお、孤独死した遺体は損傷が激しいため、直葬が選ばれることが多いです。
身内の孤独死による遺品整理の注意点

孤独死後の遺品整理を自分たちで行う場合、絶対に注意しなければならないことが3つあります。
- 特殊清掃前の部屋に立ち入らない
- マスク・手袋をして遺品整理を行う
- 勝手に遺品を持ち出してはいけない
これらを誤ると心身に思わぬ害が生じたり、深刻な相続トラブルに発展したりといった危険が生じます。孤独死の遺品整理で気をつけることを、くわしく解説しました。
特殊清掃前の部屋に立ち入らない
特殊清掃が行われる前に、孤独死現場に立ち入るのはやめましょう。なぜなら、遺体があった場所やその周辺には体液や血液、腐敗臭などが染みついている可能性が高いからです。
現場にはハエやゴキブリ、雑菌やウイルスなどが繁殖しているおそれがあり、感染症を引き起こす危険性もあります。また、腐敗臭は非常に強烈なので、気分が悪くなったり体調を崩したりすることもあります。
特殊清掃が必要な状況であれば、まずは特殊清掃業者に依頼して指示に従うようにしましょう。特殊清掃業者が汚染物質や腐乱臭を取り除いて立ち入り可能な状態にするまでは、安易に立ち入らないようにしてください。遺品整理を自分たちで行う場合でも、特殊清掃後に行うことが重要です。
マスク・手袋をして遺品整理を行う
孤独独死後の遺品整理を行うなら、マスクと手袋の着用は必須です。故人の部屋には、体液や血液、腐敗臭などが残っている可能性があり、感染症につながる危険があるためです。特殊清掃業者が脱臭や消毒を済ませていても、遺族側も万全を期して感染対策などを行いましょう。
また、感染症以外にも、部屋に溜まったホコリやカビからアレルギー症状を引き起こすことがあります。マスクや手袋を着用することで、アレルギーの原因物質から身を守ることが可能です。
マスクは高性能な物が望ましく、布マスクより不織布のマスクのほうがおすすめです。作業後は、しっかりと手を洗いうがいをしましょう。
勝手に遺品を持ち出してはいけない
遺品整理は慎重に行い、勝手に遺品を持ち出すことは絶対に避けましょう。遺品は相続財産であり、相続人全員の共有物となるからです。勝手に遺品を持ち出してしまうと、他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。
また、故人の遺言書が見つかった場合にはその内容に沿って遺産分割を行う必要があり、勝手に遺品を持ち出すと遺言書の内容と矛盾が生じるおそれがあります。
遺品整理を行う際は、必ず相続人全員で話し合って同意を得てから始めましょう。業者に遺品整理を依頼する場合も、事前に相続人全員の同意を得ることが大切です。
まとめ

孤独死の後始末は相続人や親族が行うものであり、法的には相続人が義務を負います。身寄りがなく相続人と連絡がつかない場合には、連帯保証人や賃貸物件のオーナーが後始末をするのが一般的です。
孤独死が発見されると、警察から親族に連絡が行き、身元確認の後に葬儀を手配したり役所に死亡届を提出したりと慌ただしい日が続くことになります。孤独死現場の特殊清掃や遺品整理も行わなければならず、合計で数十万円以上の出費が避けられません。
葬儀後も忙しさは続き、役所や年金事務所での諸手続きやガス・電気などインフラ系の解約、生命保険の請求手続きなども済ませる必要があります。孤独死の後始末には手間やお金がかかるため、相続人が複数いる場合にはきちんと話し合って不公平感をなくしておくことが大切です。
孤独死の後始末で困ったら、七福神へご相談ください

孤独死後の後始末でお困りなら、ゴミ屋敷バスター七福神にご相談ください!年中無休の最短即日対応で、お客様のもとへ駆けつけます。
弊社は特殊清掃から遺品整理まで一括してお引き受け可能で、ゴミ屋敷・汚部屋清掃やハウスクリーニング、不用品回収なども行っています。
孤独死に見舞われたご遺族は精神的なショックを抱えながら、厳しい日程の中で葬儀や諸手続きを進めていかなければなりません。その心労は計り知れず、少しでもご負担を和らげるためにも業者を活用することがおすすめです。
ゴミ屋敷バスター七福神では現地での下見を含め、相談・見積もりを無料で承っています。事前に見積もりした分について、追加請求が発生することは一切ございません。ご予算に応じた最適なプランをご提案しますので、お気軽にご相談ください。




