家屋の床面に敷き詰められたクッションフロアは、築年数を重ねると徐々に劣化し、カビが生えてしまうことがあります。クッションフロアの表面というより、内側から滲むように繁殖したクッションフロアのカビは、市販のカビ取り剤を使用しても落としきることが難しく、最悪の場合張り替えなければなりません。
しかし、賃貸物件のクッションフロアは勝手に張り替えられないので、最初からカビが生えないよう予防したり、いざという時の対策を立てておくことが大切です。
クッションフロアにカビが生えてしまう原因と、カビを防ぐためにやっておくべき予防策を詳しく解説します。
目次
クッションフロアにカビが生える原因

クッションフロアは、表面がビニール系の素材なので水を弾きやすく、汚れも簡単に拭き取れるため、カビは生えにくいように思われがちです。しかし、カビは一定条件さえ揃えばすぐ繁殖してしまうため、こまめに掃除をしていてもクッションフロアがカビてしまいます。
クッションフロアのカビ予防は、繁殖原因を知って根本原因から対処することが大切。なぜクッションフロアにカビが生えてしまうのか、その原因を詳しくご紹介しましょう。
部屋の湿度が高い
湿度が高い部屋に敷かれたクッションフロアは、湿気を含みやすいのでカビが生える可能性が高いです。カビは、60%〜80%の湿度を好むと言われており、湿度が高い部屋ほどカビは発生しやすくなります。
クッションフロアは、表面がビニール素材なので水分も弾けると思われがちですが、裏側までは加工されていないので湿気を吸いやすい状態です。水分を含んだクッションフロアは、裏側からカビが繁殖して表層に到達するため、まるで内側から滲み出ているようにカビが生えてしまいます。
床に汚れが溜まっている
室内の床に溜まった汚れも、クッションフロアにカビが生える原因の一つです。カビは、ホコリや体毛・垢・皮脂などを好んで餌にしており、わずかな量でも栄養源として取り入れ繁殖します。
特に、模様入りで表面に凹凸があるクッションフロアは、綺麗に見えても汚れが残っていることが多く、フローリングワイパーなどではなかなか取りきれません。日常的な掃除はフローリングワイパーなどで行っても、定期的に手作業で雑巾掛けしたり、薬剤を使用した掃除をしたりといった対処が必要です。
クッションフロアのカビを掃除する方法

定期的にお手入れをしたり気をつけたりしていても、クッションフロアの特性と室内の状況が合わさると、どうしてもカビが生えてしまいます。クッションフロアにカビが生えた場合、限られた範囲・場所なら自分で掃除することも可能ですが、この時に気をつけなければならないのが、正しいカビの掃除方法です。
カビには、さまざまな健康被害のリスクがあるため、正しい掃除方法と掃除道具で安全に対処しなければなりません。クッションフロアのカビを自分で掃除する時の、適切な方法と手順・注意点を詳しく解説します。
【NG】カビに掃除機をかける
カビの除去掃除を行うときは、たとえ広範囲で手間がかかったとしても、絶対に掃除機で吸い取ってはいけません。カビが生えている場所を確認したとき、黒くて非常に細かい粒子状のものを目にすることもありますが、それらはカビの胞子です。
胞子とは、簡単に言うと植物の種子のようなもので、空気中に舞った胞子が風に流されて移動し、新たな場所へ着床して繁殖します。カビに掃除機をかけると胞子が空中に舞い散ってしまい、他の場所に着床してカビが生えたり、胞子を吸い込んで病気になったりするため、カビに掃除機をかけてはいけません。
カビ取りの事前準備・注意事項
クッションフロアのカビ取りは、念入りな事前準備と注意事項の確認が必須です。カビ取りに使用する薬剤は強力な塩素系が多く、取り扱いを間違えると人体にも悪影響が出てしまうので、安全に対処できるよう準備を行い、注意事項を守って掃除してください。カビ取りの事前準備では、以下のような物を用意します。
- カビ取り用の洗剤(キッチン・バス用のカビ取りスプレーなど)
- スプレーボトル(スプレータイプの洗剤を使用しない場合)
- 拭き取り用の布(雑巾や廃棄予定の布など)を2枚以上
- マスク
- ゴム手袋や使い捨て手袋
- ゴーグル
- 色落ちしても良い服
事前準備が整ったらカビの掃除を行いますが、ここで注意しなければいけないのが次の2点です。
- カビ取り用の洗剤は1種類だけにする(2種類を使用したり混ぜたりしない)
- 窓を開けたり換気扇を回したりなどして空気をこもらせない
塩素系の薬剤は、混ぜると塩素ガスと呼ばれる危険なガスを発生させてしまい、呼吸器官や目などに重大な症状を引き起こします。カビは胞子を撒き散らすため、空気がこもっていると胞子を吸い込みやすくなり、重大な健康被害を負う可能性も0ではありません。
カビ取りに使用する洗剤は1種類だけにし、塩素ガスやカビの胞子を吸い込まないよう、窓を開ける・換気扇を強めに回すなどの対策をしましょう。
カビ取り手順
事前準備が整ったら、次の順番でカビ取りを行います。
- 長袖シャツ・ゴム手袋・ゴーグルなどの防護用品を身につける。
- カビ取り用の洗剤を、カビが生えている範囲より少し広めに吹きかける。
- 使用している洗剤の使用方法を確認し、指定されている一定時間放置する。
- 一定時間放置したら、固く絞った雑巾でカビを拭き取る(外側から内側に向かって、カビを寄せ集めるような拭き方をする)
- 乾いた雑巾で同じ場所を拭き取り、水分がなくなって乾いたら終了
もっとしっかりカビを取り除きたい場合は、事前に中性洗剤で同じ作業を行い、そのあとにカビ取り洗剤で掃除してみましょう。ただし、中性洗剤が残っていると危険なので、必ずしっかり拭き取りを行い、完全に乾いてからカビ取り洗剤を使用してください。
クッションフロア裏面のカビはなかなか落ちない

クッションフロアのカビ取りをする場合、作業中に気になるのがクッションフロアの裏側だが、残念ながら表面からのカビ取りだけでは、クッションフロアの裏側まで綺麗にできません。クッションフロアの裏側は、防水加工されていないケースがほとんどで、クッション性を持たせるための中間層はスポンジのような作りをしています。
クッションフロアの裏側で繁殖したカビは、中間層まで深く根を張り色素沈着を起こしているため、薬剤が染み込まず完全に消し去ることは不可能です。カビの範囲を確認したとき、クッションフロアの裏側までカビが繁殖しているようなら、カビ取りよりもクッションフロアの全面張り替えの検討が得策です。
クッションフロアにカビが生えると退去費用はいくら?
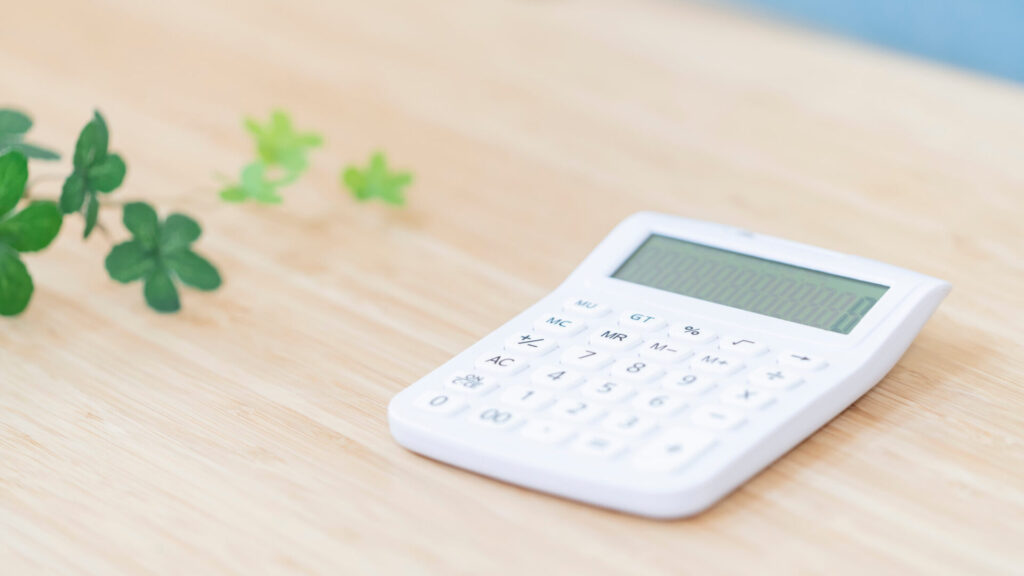
賃貸物件のクッションフロアにカビが生えていたとき、借主は退去時に原状回復費用を請求される可能性があります。退去費用は、1㎡あたりの単価×張り替え面積×減価償却の計算に基づき割り出されますが、どの項目も状況によって異なるため、はっきりした目安は出しにくいのが現状です。
「それでもある程度の目安が欲しい」という人は、減価償却分を無視して、次の計算式で退去費用の目安を出してみましょう。
クッションフロアの1㎡あたりの平均単価×張り替え面積=退去費用
かなり大幅な目安ですが、減価償却分が引かれていないだけなので、請求金額の最大値がわかるだけでも安心です。例えば、6畳のワンルーム全面にクッションフロアが敷かれていて、退去時に全面張り替え費用を請求されるとします。
6畳は約10㎡、クッションフロアの平均金額は1㎡あたり約2,000円〜4,000円なので、ここでは間をとって1㎡3,000円で計算した場合、大まかな退去費用は以下の通りです。
3,000円×10㎡=30,000円
6畳間のクッションフロア全面張り替え分だけで考えるなら、退去費用の大まかな目安は約30,000円になります。実際には、住んでいる年数によって減価償却され安くなったり、他の補修分が加算されて高くなったりするので、退去時は必ず貸主や管理会社へ問い合わせてください。
10年住んだアパートの退去費用の相場は?カビやタバコのヤニ汚れも解説
クッションフロアのカビ対策

クッションフロアのカビは、敷く前にカビ対策をしておけば、事前に防ぐことは十分可能です。賃貸物件ですでに敷いてあった場合も、日常生活でちょっと工夫したり気をつけたりしておけば、退去時にカビを発見して慌てることもありません。
現在の自分の状況に合わせ、適切なカビ対策をしてクッションフロアのカビ発生を防ぎましょう。具体的なカビ対策の方法を、以下で詳しくご紹介します。
防カビシートを活用する
これから室内にクッションフロアを敷く予定の人は、先に防カビシートを敷いてからクッションフロアを敷きましょう。防カビシートとは、カビの発生を防ぐ成分が含まれたシートのことで、敷いた場所の湿気を軽減し結露などを防いでくれます。
クッションフロアの下に防カビシートを敷いておけば、カビの発生源となる湿気が大幅にカットされるので、クッションフロアの裏面からカビが大量発生する心配がありません。ただし、脱衣所やトイレなどの湿気が多い場所は、思ったよりも早く防カビシートが劣化する可能性があるため、こまめなケアや交換が必要です。
換気して空気を入れ替える
日常生活に取り入れやすく、簡単なカビ対策からやってみたい人は、換気の習慣を身につけることから始めてください。空気の通りが悪く一定の湿度が保たれている環境は、カビにとって繁殖しやすい場所です。日常的に換気しておけば、空気が通るので湿度も軽減され、クッションフロアにもカビが生えにくくなります。
空気に流れがあるほど換気がよくなるので、寝室の窓とキッチンの小窓、玄関とリビングの窓、というように、できるだけワンセットで空気の通り道を作り換気するのがおすすめです。窓が少なく流れが作れない場合は、扇風機やエアコンの送風・サーキュレーターなどで空気の流れを良くしましょう。
部屋を除湿する
室内に除湿機をかけ、定期的に除湿するのも良い方法です。日本には雨期があり、特に5月〜9月にかけては気温も高めになるため、定期的な換気をしていても高温多湿は避けられません。
カビにとって、高温多湿な部屋は繁殖に最適なので、数日であっという間に広がり、気がついたらクッションフロアの裏がカビだらけ、というケースも考えられます。エアコンの除湿機能や、除湿に特化した家電製品を利用すれば、強制的に湿度が下げられるためカビ予防に効果的です。
こまめに掃除する
換気や除湿と並行しつつ、クッションフロアの掃除もこまめに行なっておきましょう。掃除機などでゴミやホコリを吸い取るのはもちろんのこと、フローリングワイパーで拭き掃除をしたり、時間があれば雑巾がけをするなど、細かい汚れを残さず拭き取ることがカビ防止に繋がります。
特に、暗褐色系や凹凸があるクッションフロアは、汚れの見落としも少なくありません。毎日は無理でも、数日に一回は拭き掃除の時間を作って汚れを拭き取れば、餌がないのでカビも発生しにくくなります。
床を濡れたまま放置しない
クッションフロアの床に、何かしらの水分を付着させたりこぼしたりした場合、濡れたまま放置してはいけません。例えば、お風呂場の床がクッションフロアで、風呂上がりの足拭きマットをそのままにしたり、水滴に気がつかないまま放置したとします。
クッションフロアは水分を弾きますが、湿気はそこに溜まったままなので、放置しておくとクッションフロアの裏側からカビが発生し、壁や床板まで侵食しかねません。クッションフロアが水分で濡れたら、すぐに水分を拭き取って乾燥させ、湿気をこもらせないようにしてください。
万年床にしない
寝室をクッションフロアにしている人は、布団の敷きっぱなしやマットレスの敷きっぱなしといった万年床を避けましょう。人間は、寝ている間に体温調節のために寝汗をかくと言われており、大人が一晩でかく寝汗の量はコップ1杯〜1杯半(約200ml)とも言われています。
布団やマットレスが万年床だった場合、毎日それだけの水分がクッションフロアを濡らしていることになり、さらに寝具が空気を防いでいるため乾きません。最悪の場合、布団やマットレスまでカビが生えてしまい、寝具の買い替えや深刻な健康被害といった、悪影響を及ぼすこともあります。
観葉植物を直置きしない
クッションフロアを敷いた室内に観葉植物を置く場合は、鉢植えを床に直置きしてはいけません。この場合の直置きとは、植物が植えられた鉢だけではなく、水の受け皿まで含めた直置きと考えてください。観葉植物に水を与えると、土に吸収しきれなかった分が受け皿に溜まり、常に水を蓄えている状態です。
クッションフロアに直置きした場合、床面のすぐ上に水分があるため、観葉植物の周辺のクッションフロアに湿気が溜まり、カビやすくなってしまいます。室内に観葉植物を置く場合は、脚付き台を用意してその上に設置し、クッションフロアとの距離を持たせましょう。
脚付きの家具を設置する
クッションフロアに家具を設置する場合は、できるだけ脚付きタイプのものを揃えて、家具本体が床につかないようにします。例えば、雑貨を入れるためのチェストや飾り棚、ソファ・ベッドなどを設置する場合、脚がないと本体をクッションフロアに直置きしなければなりません。
家具類は、よほどのことがなければ滅多に移動しないため、家具本体が直置きされた場所のクッションフロアは、湿気も空気もこもりがちになりカビが生えてしまいます。脚付きの家具なら、クッションフロアから本体が浮いた状態を保てるので湿気もこもりにくく、ホコリ取りや拭き掃除といったカビ対策も楽になります。
クッションフロアの特徴

クッションフロアは、一般住宅から店舗・ビルの室内まで、幅広い種類の建物で活用されている床材です。クッションフロアという名前にピンと来なくても、特徴を知ると「うちの床材もクッションフロアだ」と気づく人もいます。
価格・使い心地・デザインの面から重用するケースも多く、手軽なDIY素材としても人気があるクッションフロアは、魅力的なメリットが満載です。クッションフロアの特徴を、以下で詳しく解説します。
低コストで気軽に施工できる
クッションフロアは、他の床材と比較すると金額がお手頃で、気軽に施工できる点が魅力的な床材です。良く使用される床材と比較してみると、そのお手頃さがはっきりわかります。
| 床材 | 費用(6畳あたり) |
| クッションフロア | 約4万〜10万円 |
| フローリング | 約10万〜20万円 |
| カーペット | 約6万〜12万円 |
| 畳 | 約8万〜20万円 |
敷くだけという点でみると、カーペットも比較的低コストに見えますが、それでもクッションフロアに比べれば高めと言わざるを得ません。低コスト住宅が注目されている現代では、クッションフロアは欠かせない床材となっています。
デザインが豊富で賃貸でもリフォームのような模様替えができる
デザインが豊富で扱いやすく、賃貸物件なのにリフォームのような模様替えができるのも、クッションフロアで特筆すべき特徴です。例えば、フローリングに暖色系のフロアクッションを敷いて暖かみを出したり、チェス盤のような白黒模様でモダンな雰囲気にしたりなど、賃貸でも思い切った模様替えができます。
クッションフロアの上に家具を設置すれば、接着剤を使用しなくてもずれにくく、賃貸の床を傷つける心配もありません。部屋全体にしかなくても、㎡売りで手頃な大きさのクッションフロアを購入し、キッチンだけ、トイレだけといった、ピンポイントの模様替えも可能です。
ビニール素材で水に強く、お手入れしやすい
日常生活におけるクッションフロア使用のメリットとして、「水に強い」「お手入れしやすい」という意見も良く耳にします。クッションフロアの表面はビニール素材なので、飲み物をこぼしても床に浸透せず拭き取りも簡単です。木材のフローリングのように、定期的にワックスを掛け直すなどのお手入れも必要ありません。
犬や猫などのペットを飼っている場合、掃除のしやすさとお手入れ不要の気軽さから、床にクッションフロアを敷き詰め粗相対策をし、拭き掃除や消臭作業を楽にしている人もいます。
クッション性があり、防音効果も期待できる
クッションフロアは多層構造で、表面と裏面の間に発泡塩化ビニールの層があるため、クッション性があり防音効果も期待できます。例えば、集合住宅は複数の居住空間が隣り合っているため、足音や声などの生活音が響きやすい環境です。
特に、足音や物を落とした時の音は、床を通して階下に響きやすく、ひどい場合は近隣トラブルに発展しかねません。クッションフロアを敷いていれば、発泡塩化ビニールのクッション層が音を和らげてくれるため、防音効果の面でも安心できます。
踏み心地が柔らかく安全
クッションフロアは、その名の通りクッション性のあるカーペットなので、踏み心地が柔らかく衝撃も軽減されて安全です。クッション性のないタイルやフローリングの場合、衝撃がダイレクトに跳ね返ってくるので、幼い子供やお年寄りが転んだ場合、思わぬ怪我を負う可能性があります。
クッションフロアの場合は、クッション層が転んだ衝撃を和らげてくれるため、硬い床よりも怪我をしにくく、もし怪我をしても軽度で済む可能性は高いです。全く怪我をしないというわけではありませんが、少しでも衝撃が和らげば体への負担が軽減されるので、クッションフロアは幼い子供やお年寄りがいる家庭にぴったりの床材と言えます。
クッションフロアのデメリット

魅力的なメリットの多いクッションフロアですが、実際に使用してみると気になるデメリットも0ではありません。クッションフロアのメリットばかり注目していると、後から思わぬデメリットに気がついて悩んだり、後悔したりするケースも良く見られます。
クッションフロアの導入を検討するときは、デメリットも確認した上でメリットとよく比較し、後悔のない施工や部屋選びをしましょう。クッションフロアでよく見られるデメリットを、以下で詳しくご紹介します。
劣化しやすい
クッションフロアは、塩化ビニール製のシートをボンドで貼り付けて使用するため、耐久年数が短く劣化しやすい点がデメリットです。例えば、クッションフロアを日当たりの良い場所に敷いた場合、日焼けして表面の色が変色を起こしてしまい、元の綺麗な色合いを維持できません。
日当たりの良いクッションフロアが熱を吸収し、ボンドの劣化を早めて剥がれやすくなったりずれたりすることもあります。劣化の目安は約10年と言われていますが、住んでいる地域によっては、日差しが強かったり気温が高かったりするため、状態によっては短い期間での張り替えが必要です。
傷がついたり、凹みやすい
傷がついたり凹みやすいといった点も、クッションフロアのデメリットにあげられます。クッションフロアの主な素材はビニールで、ハサミやカッターなどの刃物や尖った物がぶつかれば、簡単に傷が付くような作りです。
クッション性を持たせるための発泡塩化ビニール層は、集中した重さがかかると凹みやすく、長時間放置された場合はほとんど元に戻りません。引越しや模様替えの予定がないなら気になりませんが、気に入ったフロアクッションを長く使いたい人には、傷のつきやすさや凹みやすさがデメリットになります。
汚れが沈着すると、落としにくい
クッションフロアは、汚れが沈着すると落としにくくなり、無理に落とすと劣化させてしまう点も理解しておくべきデメリットです。沈着した汚れにピンとこない人は、油性マジックのシミ落としを想像してみてください。
ビニール素材は油性マジックに弱く、一度沈着するとなかなか落とすことができません。除光液などで落とすことも可能だが、除光液はビニールを溶かしてしまうので、拭き取った部分のクッションフロアが劣化したり、最悪の場合は表面が溶けてしまったりします。
表面のテカリは安っぽく感じる
クッションフロアの表面はビニール素材なので、しっとりした落ち着きや高級感を求める場合は、ビニール素材特有の安っぽさを感じるテカリはデメリットです。例えば、フローリングとクッションフロアを比較した場合、フローリングが放つのはワックス特有の高級なツヤ感で、光を反射するようなテカリではありません。
クッションフロアの表面は、落ち着いた色調のフローリング模様であっても、光を反射するような安っぽいテカリが出てしまいます。購入前のカタログでは落ち着いた雰囲気に見えても、実際に貼ってみると安っぽさが気になるパターンもあるため、検討する人は十分な確認が必要です。
湿気がこもりやすくカビが生えることもある
湿気がこもりやすくカビが生えるのは、クッションフロアを使用する上で、特に気に留めておくべきデメリットと言えます。ビニール素材のクッションフロアは、水を通しにくい反面空気の通りが悪いので、接着面はどうしても湿気がこもりがちです。
カビは、クッションフロアを敷く時に使用した接着剤まで餌にしてしまうため、汚れや掃除に気をつけていても繁殖してしまうこともあります。事前にカビ対策をしていれば、クッションフロアのカビ発生も防ぎやすくなりますが、万が一の可能性もあるので、カビが生えやすいというデメリットも視野にいれておきましょう。
カビの生えたクッションフロアの処分は七福神へお任せください

「カビの生えたクッションフロアを処分したいが、大きいので運ぶのが大変」「カビの範囲が広くて、剥がした後の掃除に困っている」とお悩みの方は、ゴミ屋敷バスター七福神にお任せください。七福神は、大型家具の処分から徹底的なハウスクリーニングまで、お部屋の清潔トラブルに対応している清掃業者です。
カビが生えたクッションフロアを剥がして引き取り、ご希望があればハウスクリーニングまでいたしますので、大変なゴミ出しやカビ取り作業で悩む心配はありません。ご相談の受付は、年中無休で9:00〜19:00、電話・メール・LINEと3種類の窓口をご用意しております。些細な悩みは質問でも丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ

クッションフロアは、表面はビニール素材でコーティングされ、クッション層が湿気を含み通気性も悪いため、敷きっぱなしにしているとカビが生えやすくなってしまいます。カビは、適度な湿気があり空気がこもった場所に繁殖しやすいので、カビ取りシートを活用したりこまめに換気したりといった、カビ対策を日常的に行うことが大切です。
クッションフロアに生えてしまったカビは、拭き取ることが難しく劣化が進んでしまうため、剥がして破棄するしかありません。クッションフロアは、おしゃれな模様替えが低コストでできる反面、カビや汚れの沈着といったデメリットもあるので、よく検討してから活用しましょう。




