各地でゴミ屋敷が社会問題となっています。 近年、テレビなどでも取り上げられることが多く、ゴミに埋もれた家の様子を見て驚いた事のある人も多いのではないでしょうか。 ゴミ屋敷の住人たちは、なぜあんなにモノを溜め込み、捨てられなくなってしまうのでしょう。
家がゴミ屋敷になってしまう原因のひとつに「ためこみ症」があるといわれています。 「ためこみ症」とは一体どのようなものなのでしょうか。 また、どのような人がなりやすく、どのように対応して行けば良いのでしょうか。
目次
ためこみ症とは?

“汚部屋”や“ゴミ屋敷”に住む人は、もしかしたら「ためこみ症」になっているかもしれません。
ためこみ症は精神疾患のひとつで、適切なアプローチをしないと改善が難しい症状とされています。
ためこみ症とは、どのような病気なのでしょうか。
ためこみ症とは?
ためこみ症の芽は、11~15歳ごろに現れるといわれています。
その後、20代中ごろまでに日常生活を妨げるようになり、30代中ごろまでには仕事や私生活などが難しくなり、慢性化することもしばしばです。
ためこみ症の人は自分の趣味のもの、価値のあるものだけを集めるコレクターとは違います。
ためこみ症の人は、普通に考えれば不要で価値のないモノを大量にためこみ、手放すことができません。
このようなためこみ症は、適切な治療をしなければ収集欲を止められず、汚部屋やゴミ屋敷を生んでしまうのです。
ためこみ症の原因とは?
なぜ、ためこみ症を発症してしまうのでしょうか?
それには3つの要因が考えられます。
気質要因
ためこみ症の人は、優柔不断な性格であることが多いと言われています。
そのほかに以下のような気質も、ためこみ症の人の特徴としてよく見られます。
- 完璧主義
- 面倒事の回避
- 問題の先延ばし
- 計画を立てて仕事をまとめることが苦手
- 注意散漫
環境要因
強いストレスによる心的外傷が原因となり、ためこみ行為が始まることがあります。
また、すでにためこみ症が始まっている場合は、悪化したりするケースもあります。
遺伝要因
ためこみ行為には遺伝的要因もあります。
ためこむ症になる人の約50%には、同様にためこみ行為をする親族がいることが報告されています。
発達障害や強迫性障害との関係性
ためこみ症は、不要な物を捨てられずにため込んでしまう症状で、強迫性障害と混同されることがあります。しかし、両者は異なる特徴を持っています。強迫性障害は不安を和らげるための反復行動が中心ですが、ためこみ症では物への執着が主な原因とされています。
また、背景には発達障害の特性が関係している場合もあり、注意欠如や情報処理の苦手さが影響することがあります。これらの違いや関連性を正しく理解することで、より適切な支援や治療が可能になります。理解を深めることが、当事者への適切な対応に役立ちます。
ためこみ症の症状とは?

では、ためこみ症の症状について見ていきましょう。
兆候
テーブルや椅子などに衣服や書類、小物などが山積みになって、テーブルや椅子として使えない状態が5年以上経ってしまっていませんか?
このような状態は、ためこみ症の兆候と言われています。
症状が進むと、浴室やトイレにまでモノが溢れ、使用するのが難しい状態になると危険信号です。
ものを捨てることが苦痛
ためこみ症の人は、モノを捨てることを非常に苦痛だと感じます。
それが、普通の人にとっては全く価値がなくても、とにかく捨てられない、取っておかなければいけない、という意識にとらわれます。
モノをゴミとして捨てることはもちろん、リサイクルに出す、売却する、譲渡するなどほかの手段であっても同じです。
ためこみ症の人は、自分がためこんだモノに対して価値を感じていたり、強い愛着をもっていたりします。
そして、モノを手放すことをかわいそうに感じたり、時には捨てることに恐怖感を持っていることもあるのです。
モノに強く執着してしまう
ためこみ症の人は、自分の収集したモノに強い執着心を持っています。
ためこみ症の人がゴミでさえも集めてしまうのは、そのモノの価値の有無ではなく、「モノを溜めておくこと」が目的だからです。
対象物は人によって違いますが、過剰に買い物をしたり、チラシや他の人が捨てたゴミなど無料のモノの収集をすることも。
また、「動物ためこみ」といって、狭い部屋であっても、非常に多くの動物を飼育しているケースもあります。
その多くは、動物たちの衛生状態や健康状態を良好に保つことができません。
不必要な物を大量に集める
ためこみ症の特徴のひとつは、使う予定のない物を過剰に集めてしまうことです。多くの場合、明らかに不要な品物でも「いつか使うかもしれない」と感じて処分できません。たとえば、古い新聞や壊れた家電、空の箱などを手放せずに積み重ねてしまいます。
これにより、生活空間が物であふれ、安全や衛生にも影響が出ることがあります。ためこみ症は、単なる片づけ下手とは異なり、精神的な問題が背景にあることも多いため、早期の理解と対応が大切です。
家がモノで溢れる
ためこみ症の人の最も大きな特徴は、家の中にモノが散乱し、生活に支障が出ていることです。
症状が重くなればなるほど大量のモノを溜め込み、生活のための空間が埋まってしまうほどになります。
ためこみ症を放置するとどうなる?
ためこみ症を発症してしまった人が、そのまま放置されてしまうと、どのようなことが起こるのでしょうか。
ゴミ屋敷になる
ためこみ症を治療せず放置していると、家じゅうにモノが増え続け、最終的にゴミ屋敷になってしまいます。
ゴミ屋敷は悪臭やネズミなどの害獣や害虫などの温床のため、近隣の住民に被害が及ぶ可能性も大です。
それでも、ためこみ症の方はものを捨てることができません。
無秩序に収集し、ためこみ続けることで、ゴミ屋敷化はさらにどんどん進んでいきます。
ゴミ屋敷になるのは「ためこみ症」のせい?なりやすい人の特徴や治す方法について解説
生活が困難になる
ゴミ屋敷の中は、生活スペースもモノが埋め尽くしているため、生活が困難になります。
堆積したゴミのわずかな隙間から出入りし、ゴミを踏まなければ家の中を移動できません。
ゴミ屋敷では、キッチンやリビングもまともに使うことができません。
そのため、食事や睡眠など基本的な生活を行うことができず、健康を害することになります。
また、家の中にゴミが大量にあると、少しの火気でも大規模な火災が起きる可能性も高まります。
周囲から孤立してしまう
モノが蓄積され過ぎて部屋の掃除もできないゴミ屋敷は、とても人を呼べる状態ではありません。
その結果、友人や家族を招くこともできず、孤立しやすい状況となってしまうのです。
また、ゴミ屋敷は、悪臭や害虫などの発生により、周辺の人に悪影響を及ぼします。
そのため、近隣住民との関係性の悪化も考えられます。
ためこみ症の相談先は?

ためこみ症は、不要な物を手放せずに生活空間が物であふれてしまう状態で、日常生活に支障をきたすこともあります。このような状態を自力で改善するのは難しいため、専門機関への相談が大切です。ここでは、ためこみ症の主な相談先についてご紹介します。
精神科・心療内科
ためこみ症は、強迫性障害やうつ病、発達障害など他の精神的な疾患と関連している場合があります。そのため、まずは精神科や心療内科を受診することが推奨されます。医師による診断を受けることで、必要に応じた治療や投薬、専門的なアドバイスを受けられます。
特に、物をためてしまう原因が精神的なストレスや不安に由来している場合、専門医の支援が症状の改善につながることがあります。また、医療機関では、カウンセリングや認知行動療法などの心理的アプローチが行われることもあります。
治療の初期段階では、自分の状態を正しく理解し、無理なく改善を目指すことが重要です。自覚がない場合でも、家族の働きかけで受診につながるケースも多いため、周囲の理解と協力も欠かせません。
自治体の心の相談窓口
各自治体では、地域住民の心の健康を支援するための相談窓口が設けられています。ためこみ症のような精神的な問題についても、相談を受け付けている場合があります。専門の相談員や保健師が対応しており、医療機関への紹介や福祉サービスとの連携など、適切なサポート体制が整っています。
自治体の相談窓口は無料で利用できることが多く、気軽に相談しやすい点が特徴です。また、家庭訪問や日常生活の支援など、個別のニーズに応じた支援を受けられることもあります。身近な場所で安心して相談できる環境が整っているため、ためこみ症に悩む方やその家族にとって、心強いサポートとなるでしょう。
心理カウンセラー
ためこみ症に関して、心理カウンセラーに相談することも効果的です。心理カウンセラーは、対話を通して心の問題を整理し、クライアント自身が気づきを得られるよう支援します。認知行動療法や感情のコントロール方法を取り入れながら、問題の根本にアプローチしていきます。
カウンセリングは、医療行為ではないものの、日常生活で感じる不安や葛藤について自由に話せる場です。ためこみの背景にある感情や思考のクセに気づくことが、症状改善への第一歩となります。継続的なカウンセリングを通じて、生活習慣を見直し、少しずつ行動を変えていくことが可能です。
ゴミ屋敷の原因は心の病気?可能性のある8つの原因と対処法とは
親にためこみ症の疑いがあるとき

高齢の親が物を捨てられず、家の中にモノがあふれている場合、「ためこみ症」の可能性があります。これは単なる整理整頓の問題ではなく、精神的な背景が関係しているケースも少なくありません。家族としてどう向き合うべきか、注意点やチェックリストを通じて考えてみましょう。
ゴミ屋敷状態でも勝手に捨ててはいけない
親の家がゴミであふれていると、「片づけてあげたい」と思うのは自然なことです。しかし、本人の許可なく勝手に物を捨てるのは避けるべきです。ためこみ症の方にとって、どんな物にも強い執着があり、不要に見える物でも本人にとっては価値があると感じています。
勝手に処分してしまうと、信頼関係が壊れたり、精神的なショックを与えたりする可能性があります。まずは本人の気持ちに寄り添い、対話を重ねて理解を深めることが大切です。必要に応じて、医療機関や専門家に相談するのも有効です。
ためこみ症のチェックリスト
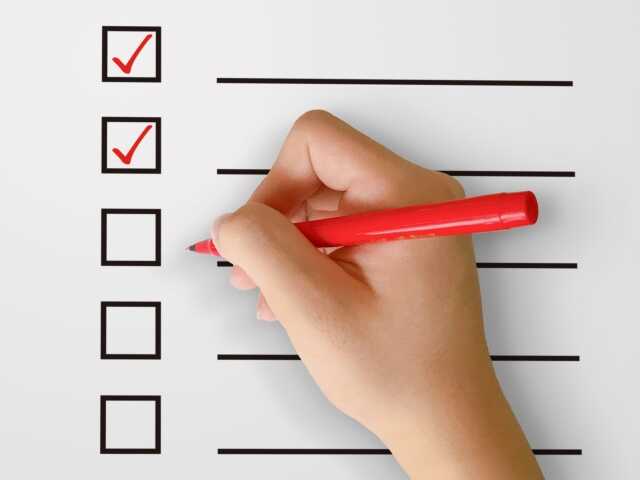
以下は、親にためこみ症の傾向が見られるか確認するためのチェックリストです。複数項目に該当する場合は、専門的な対応を検討しましょう。
- 不要な物を捨てるのに強い抵抗がある
- 使わない物を「いつか使う」と保管し続ける
- 家の中に物が積み上がり、生活スペースが狭くなっている
- 他人が物に触れることを極端に嫌がる
- ゴミをゴミとして処分できない
- 家族から片づけを促されると激しく怒る
- 衛生状態が悪化していても片づけようとしない
このような傾向がある場合は、早めに対応することが重要です。
ためこみ症の治療とは?

現在のところ、ためこみ症の治療は非常に難しいと言われています。
ためこみ症の患者自身の治療意欲が低いことも相まって、薬物療法と認知行動療法に反応するケースも少ないようです。
そんな中でも、どのような治療が行われているかを見ていきましょう。
抗うつ薬による治療
ためこみ症には、抗うつ薬が効くことがあるようです。
具体的な薬の内容は、医師が症状に合わせて判断します。
薬を服用する場合は、量や飲み方について、必ず医師の指示を仰ぎましょう。
認知行動療法
ためこみ症の治療には、認知行動療法が選ばれるケースもあります。
認知行動療法とは、心の病に対して、意思決定と分類のトレーニングをしていくというものです。
ためこみ症の場合は、「モノを捨てる」という刺激を繰り返しながら慣れていくことによって、「捨てても大丈夫」という認識を身につけていきます。
認知行動療法は、医師が症状に合わせ、個別に治療方法を考えていくのが一般的です。
家族からの支援や環境サポート
ためこみ症を治すためには、家族の支援が重要です。家族が患者を理解し、無理なく支えることが、治療の大きな助けとなります。まず、家族は患者の気持ちに寄り添い、批判や非難を避けることが大切です。
そうすることで、患者は自分を責めることなく、治療に前向きに取り組むことができます。また、家族は生活環境を整えることも大事です。片付けや整理をサポートし、患者がストレスなく生活できる空間を作ることが治療の進展に繋がります。
さらに、家族が患者の治療計画を一緒に考え、積極的に参加することで、患者の安心感を高めることができます。治療は時間がかかることもありますが、家族の支えがあれば、患者は少しずつ改善を実感できるでしょう。家族の理解と協力が、ためこみ症克服の鍵となります。
ゴミ屋敷の片付けはバスター七福神へご相談ください

ためこみ症でゴミが溢れてしまったお住まいの片付けも、バスター七福神にお任せください。当社は、ゴミ屋敷の片付けに豊富な経験を持ち、お客様のご要望に応じた迅速で丁寧な対応をいたします。
長年放置された部屋の片付けは、手がつけにくい場合がありますが、専門のスタッフが必要な処理を行い、きれいな状態へと改善します。また、家具や家電の処分も一括で行えるため、手間がかかりません。
片付け後の清掃もお任せいただけますので、安心してご依頼いただけます。どんな状況でも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
ためこみ症の人は、不要なモノにまで激しく執着し、モノを捨てることに大きな苦痛を感じてしまう精神疾患です。 そのため、家にあるモノを捨てられないばかりか、どんどんモノを集め、ためこみ、ついにはゴミ屋敷となってしまいます。 この症状が現れたら、精神科や心療内科を受診しましょう。 現在、有効な治療法などは確立していませんが、まずは、患者本人がカウンセリングなどを根気よく続ける必要があります。 医師とよく話し合いながら、解決への道を探していきましょう。 治療によりものへの執着が軽くなったら、部屋を片付け、健康的な生活を送れるようにしましょう。




