日常生活の中で出てくる生ゴミには、ふと虫の姿を見かけることが珍しくありません。
衛生面を考えると決して好ましいものではありませんが、そもそも生ゴミの中で見かけるゴミはどこからやってくるのか。
その疑問やどのように駆除するのかなどを見てみましょう。
生ごみの虫はどこから発生するの?

部屋の扉や窓をしっかり閉めていても、家の中に虫を引き寄せるものがあれば、わずかな隙間からでも侵入してしまうものです。
特にキッチンは、水や食べ物が豊富にあるため、虫にとって格好のエサ場となります。家の中に虫を招き寄せてしまう要因として、次のような点が考えられます。
生ゴミの腐敗臭に引き寄せられる
ゴミ捨て場の周りを飛び回る虫を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。虫は食べ物の腐敗臭に引き寄せられるため、長時間放置された生ゴミは、虫が集まる原因となってしまいます。
この現象は、何もゴミ捨て場に限った話ではありません。家庭でも同じことが起こります。例えば、三角コーナーに野菜くずや食べ残しを放置していると、虫が寄ってくるのです。
さらに、虫は腐敗臭を感知して狭い隙間にも入り込んできます。生ゴミだけでなく、飲み残した飲み物やそのまま放置されたコップにも発生しやすいので、注意が必要です。
観葉植物から部屋へ侵入する
生ごみの虫はどこから発生するのでしょうか?実は、観葉植物が原因になることがあります。観葉植物は土や葉に虫を引き寄せることがあり、その虫が部屋に侵入することがあります。特に湿度の高い場所や温暖な環境では、虫が繁殖しやすくなります。これらの虫が生ごみと接触すると、食べ物を食べて繁殖を繰り返します。そのため、観葉植物を室内に置く際は、虫の発生に注意が必要です。虫が発生しないように定期的に植物をチェックし、適切に管理することが大切です。
密封されていないお米から発生
密封されていないお米には、コクゾウムシやノシメマダラメイガなどの虫が発生することがあります。これらの虫の卵は、スーパーで購入したお米の中にも含まれている可能性があります。
特に、お米が流通する過程で卵が混入し、適切な保管がされないと孵化しやすくなります。コクゾウムシは小さな黒い甲虫で、お米に穴を開けて食害します。一方、ノシメマダラメイガの幼虫は米粒を食べながら成長します。
これらの虫を防ぐためには、密閉容器で保存し、冷蔵庫など低温環境に保管することが有効です。また、購入後はすぐに袋を移し替え、長期間放置しないことも大切です。
生ゴミが入った三角コーナーから発生
三角コーナーに生ゴミを放置すると、虫が発生する大きな原因になります。なぜなら、生ゴミは家の中にいる虫の好物だからです。
また、三角コーナー自体は汚れにくいため、こまめに掃除する習慣がない方も多いのではないでしょうか。しかし、生ゴミが腐敗すると強い臭いを発し、虫を引き寄せてしまいます。
特に、キッチンは湿気が多く、虫が繁殖しやすい環境です。そのため、三角コーナーは多くの家庭で虫の発生源になりやすい場所のひとつです。虫の発生を防ぐためには、生ゴミを長時間放置せず、こまめに処分することが大切です。三角コーナーも定期的に掃除し、清潔に保ちましょう。
排水溝のつまりから発生
排水溝が詰まると、虫が発生しやすくなります。特に、家の中に侵入した虫が、排水溝に溜まった水に卵を産み付けることもあり、そのまま放置すると大量発生の原因になります。
日ごろの何気ない行動が、排水溝の詰まりを引き起こしている場合もあります。例えば、食べかすや油汚れをそのまま流してしまうと、汚れが蓄積して水の流れを悪くし、虫の発生を助長してしまいます。
虫の発生を防ぐためには、定期的な掃除が欠かせません。こまめにゴミを取り除き、専用のクリーナーを活用して清潔に保ちましょう。予防を徹底することで、快適な環境を維持できます。
外に放置した生ゴミに虫が湧きやすい
室内に臭いがこもるのを防ぐため、ゴミ袋を外に出している方もいるのではないでしょうか。しかし、これは虫を引き寄せる原因のひとつです。
屋外は室内よりも気温が高く、生ゴミはすぐに腐敗します。その結果、臭いが強まり、虫が集まりやすくなります。特に夏場は、短時間で虫が発生し、状況が悪化することもあります。
さらに、外で増えた虫が玄関周辺に巣を作ると、扉の開閉時に室内へ侵入しやすくなります。虫の発生を防ぐためには、生ゴミを適切に密閉し、決められた収集日に出すことが大切です。ゴミの管理を徹底することで、虫の被害を最小限に抑えられます。
季節と湿度の影響で生ごみの虫は増加!

ここでは季節と湿度の影響でどのように生ごみの虫が増えるのかについて解説していきます。
湿度が高い季節は特に注意
生ゴミに発生する虫は、湿度の影響を受けやすいです。特に梅雨や夏場は湿気が多く、生ゴミが腐敗しやすくなるため、虫が増えやすくなります。湿度が高いとゴミの発酵が進み、強い臭いを放ちます。この臭いが虫を引き寄せる原因となるのです。
キッチンやゴミ置き場など、湿気がこもりやすい場所は特に注意が必要です。虫の発生を防ぐためには、以下の対策を行いましょう。
- こまめに換気をして湿気を減らす
- ゴミは密閉し、早めに処分する
- キッチンを清潔に保ち、臭いの発生を防ぐ
日頃から湿気対策を意識することで、虫の発生を抑えることができます。
夏は生ごみに集まる虫が増える
夏場は気温の上昇とともに、虫の繁殖スピードも速くなります。例えば、コバエの一種であるショウジョウバエは、わずか1週間ほどで成虫になります。そのため、生ゴミを少し放置するだけで、あっという間に虫が発生してしまいます。
さらに、高温になると生ゴミの腐敗が進み、強い臭いを放つことで、より多くの虫を引き寄せます。特に屋外のゴミ置き場では、直射日光が当たると温度が上がり、腐敗が加速するため注意が必要です。
虫の発生を防ぐためには、生ゴミをこまめに処理し、密閉した袋に入れるなどの対策を徹底しましょう。
生ゴミに発生する虫の種類

生ゴミにいる虫としてまずイメージするのがコバエなのではないでしょうか。
生ゴミの中、あるいはその近辺を飛んでいるコバエは、実はコバエにもいくつかの種類があります。
むしろ「コバエ」という種類そのものはありませんし、ハエの子供でもありません。
そもそもハエの子供は蛆虫であり、コバエとハエは別の存在です。
しかし大して生物に興味のない多くの人にとっては、ハエであろうがコバエであろうが迷惑なものである点は同じです。
そんなコバエですが、4種類存在しています。
ショウジョウバエ
体長2mmから3mmで、台所の生ゴミ近辺で見かけるコバエの多くがこちらです。
特に果物や野菜を好物としていることから、英語で「fruit fly」と呼ばれています。
腐って発酵を始めた果物はショウジョウバエの大好物なので発生源になりやすいのですが、他にも酢、アルコールの飲み残しなども好物としているので、それらに吸い寄せられて姿を見かける機会も増えることでしょう。
ショウジョウバエの特徴の一つに、繁殖能力が挙げられます。
ショウジョウバエは産卵からおよそ10日で羽化するのですが、1日におよそ80個もの卵を産みます。
そのため、放置していた果物や野菜に吸い寄せられて発生したショウジョウバエが居ついてしまい、そこで産卵をすると、猛スピードで増加します。
結果、大量のショウジョウバエが発生することになってしまうのです。
ノミバエ
春から秋にかけて見かける機会が多いコバエです。
体長はショウジョウバエとほぼ同じサイズですが、発生源はショウジョウバエよりも多いです。
生ゴミだけではなく、腐った植物や排水溝、さらにはペットの糞で、素早く歩きながら活動し、繁殖を繰り返します。
ちなみに食品、料理に入りこんで産卵することもあるので日常生活にも影響を及ぼすコバエです。
キノコバエ
体だけを見ると、ハエではなく蚊を思わせる、土に産卵するタイプのコバエです。
梅雨の季節によく見かけるのは、湿度が好きな特性があるからこそ。
土に産卵することから、梅雨時、庭やベランダの観葉植物に産卵して大量発生するケースもあります。
厄介なことに、明るい場所に誘われる習性があるので、「家」そのものに寄り付きやすいです。
チョウバエ
こちらも幼虫やサナギの時は蚊を思わせる形状のコバエです。
体長5mmに達するタイプもいますが、主な発生源は水です。
しかし、きれいな水では繁殖できません。皮脂、有機物などで汚れ濁った水を好物としており、特にトイレ周りを飛んでいることが多いです。
梅雨の時期に見かける機会が多いのですが、衛生環境が悪い、つまりチョウバエにとって適している環境があると、季節を問わずに発生します。
生ゴミに湧く虫の予防方法

コバエの発生を抑える、つまりは予防のためには清潔が大切です。
コバエの種類の紹介でもお伝えしたように、コバエは人間にとって清潔とは言い難い場所に現れ、産卵して繁殖します。
1匹の侵入を許すだけで、いずれは大量に発生するのがコバエです。
まずは予防を徹底することが大切ですが、予防法としては主に下記が挙げられます。
三角コーナーに生ごみを放置しない
生ゴミに虫が湧くのを防ぐためには、三角コーナーにゴミを長時間放置しないことが重要です。生ゴミは湿気を含みやすく、時間が経つと腐敗が進み、強い臭いを発します。この臭いが虫を引き寄せる原因になります。
また、三角コーナー自体も汚れが溜まりやすく、不衛生な環境になりがちです。虫の発生を防ぐためには、以下の対策を実施しましょう。
- 生ゴミはこまめに処分する
- 三角コーナーを定期的に洗浄し清潔に保つ
- ゴミ袋はしっかり密閉し、臭いが漏れないようにする
日頃の工夫で、虫の発生を抑えることができます。
排水溝の掃除はこまめに
コバエは汚い水が大好きです。
台所のシンクなど、目に見える部分であれば掃除も行いやすいのですが、排水溝に関しては目に見えない部分であり、かつ手を入れることも難しいのでどうしても放置してしまいがちですが、こまめに掃除を心掛け、清潔を保つことでコバエを近づけさせません。
食べ残し・飲み残しはすぐに処理
食べ残したもの、あるいは飲み残したものをそのまま放置しておくことは控えましょう。
放置しておくと、匂いによってコバエが近寄ってきます。そして産卵、大量発生となりますので、飲み物も食べ物も残さないようにしましょう。
食べ残しや飲み残しが発生してしまった場合には、いつまでも放置しておくのではなく、処分しましょう。
また、皿も同様です。
例えば食べ物が付着している皿。
「後で洗おう」と思って放置しておくと、コバエが寄ってきます。
洗い物もできるかぎり溜めないか、後で洗うのであれば残りものをそそいでおくなどの工夫が必要です。
新聞紙やペットシーツに包み、ビニール袋に入れる
生ゴミに湧く虫を防ぐためには、いくつかの方法があります。まず、生ゴミを新聞紙やペットシーツで包み、その後ビニール袋に入れることが効果的です。これにより、ゴミが湿気を持ちにくくなり、虫が発生しにくくなります。
また、ゴミを密閉することで、虫の侵入を防ぐことができます。ゴミ箱自体もこまめに掃除し、清潔を保つことが大切です。さらに、ゴミの回収頻度を増やすことも、虫の発生を防ぐ方法の一つです。
これらを実践することで、虫の発生を抑え、衛生的な環境を保つことができます。
フタつきのゴミ箱を使う
フタつきのゴミ箱を使うことも効果的です。ゴミ箱にフタをつけることで、虫が入りにくくなり、臭いも外に漏れにくくなります。特に生ゴミは湿気や臭いが強いため、ゴミ箱にフタがあると、虫が集まりにくくなります。
また、ゴミ箱を定期的に洗い、清潔に保つことも大切です。ゴミを捨てる際は、できるだけ袋をしっかりと縛り、生ゴミがこぼれないようにしましょう。これらの対策を実践することで、虫が湧くリスクを減らすことができます。
生ごみ処理機を導入する
生ごみに湧く虫の予防方法として、生ごみ処理機を導入することが効果的です。処理機は、生ごみを短時間で処理し、虫が寄りつきにくい環境を作ります。家庭で発生する生ゴミを効率的に減らすことで、虫の発生を防げます。
また、処理後は堆肥として活用できるため、環境にも優しいです。生ゴミの管理を徹底することで、清潔な環境を保ち、虫の繁殖を防ぐことができます。生ごみ処理機を使うことで、衛生面でも安心できるようになります。
さらに生ごみ処理機を導入することで本体購入金額の2分の1などを補助してくれる自治体もあるのでチェックしてみましょう。
参考:https://www.city.minato.tokyo.jp/gomigenryou/kurashi/gomi/kate/3r/namagomi.html
生ゴミを冷凍庫で一時保管する
生ゴミに湧く虫を予防するためには、冷凍庫を活用するのが効果的です。生ゴミをそのまま放置すると、温かい環境で虫が発生しやすくなります。そこで、生ゴミを出す前に冷凍庫で一時的に保管する方法を試してみましょう。
冷凍することで、虫の発生を防げるだけでなく、臭いも抑えられます。特に、家庭から出る生ゴミは種類も多く、長時間放置すると衛生面でも問題が発生します。冷凍庫に保管することで、ゴミをまとめて処理できるため、手間も省けます。生ゴミの虫対策として、ぜひ取り入れてみてください。
ゴミ袋は密封することが好ましい
ゴミ袋はできれば密封できるタイプにしましょう。
隙間があると匂いに導かれてコバエがやってきます。
さらにはゴミ袋の中に侵入してしまい、産卵に至ります。
特にゴミ袋の中は、コバエにとっては快適な空間なので注意しましょう。
コバエの駆除の方法は?
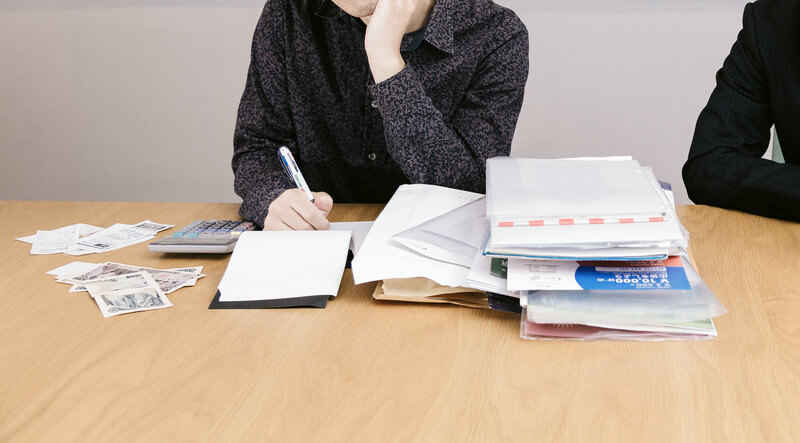
予防も大切ではありますが、発生しているコバエ対策としては駆除になります。
コバエの駆除グッズも多々ありますが、コバエがどのような形で発生しているのか、つまりは環境によって異なります。
コバエ駆除グッズを活用する
ドラッグストアやスーパーには多くのコバエ駆除グッズが販売されていますので、これらを使用することで、コバエの駆除が可能です。
しかし、あくまでも一時的なものです。コバエが大量に発生しているのは、寄ってきたコバエが産卵したから。
つまりは環境の問題になりますので、駆除グッズはあくまでも表面処理にすぎません。
もちろん何もしないよりはマシですが、駆除グッズだけでコバエを自宅から一掃できるかというと、現実的には難しいです。
結局、その場にいるコバエを駆除したとしても、環境が同じであれば再びコバエが寄ってきて、繁殖し、大量発生するだけです。
害虫駆除専門業者に依頼する
専門業者に依頼することで、コバエの駆除はもちろんですが、コバエが近寄ってこない環境の構築が可能になります。
専門業者の強みとして、コバエの特性を知り尽くしている点にあります。
コバエの種類も把握していますので、4種類いるコバエそれぞれが近寄ってこない方法を確立しつつの駆除となりますので、コバエがいなくなるだけではなく、以降、コバエが発生しにくくなります。
また、自分自身では手を加えることができない部分の掃除も問題ありません。
排水溝やシンクの奥、浴室やトイレの奥など、自分自身では難しい部分の掃除も問題ありません。
駆除グッズを使用しても、すぐにまたコバエが発生して悩んでいるようであれば、一度専門業者に相談してみるのもよいでしょう。
虫が湧く原因となる汚部屋を片付ける
汚部屋を片付けることで虫がいなくなる理由は、虫の発生源である食べ残しや湿気、ホコリがなくなるからです。ゴミや汚れは害虫のエサや住処となり、放置すれば繁殖の温床になります。
防ぐには、まずキッチンや食卓周りから片付けるのが効果的です。なぜなら、食べ物のカスや生ゴミが虫を引き寄せる最大の要因だからです。次に、湿気がこもりやすい浴室や押し入れを整理し、換気を行うことで害虫の発生を防げます。
床に物を置かない習慣をつけ、こまめに掃除をすることも重要です。清潔な環境を保てば、虫が寄りつきにくくなります。
まとめ

生ごみに発生する虫は、主に外から侵入してきます。特にゴミを放置したり、食べかすが残っていると、虫を引き寄せやすくなります。予防方法としては、ゴミの管理を徹底し、密閉容器に入れることや、部屋を清潔に保つことが大切です。さらに、湿気対策や定期的な換気も虫の発生を防ぐ効果的な方法です。これらの予防策を実践することで、生ごみから虫を防ぐことができます。
虫が来る汚部屋はゴミ屋敷バスター七福神が片付けます

もし、虫が発生する汚れた部屋にお悩みであれば、ゴミ屋敷バスター七福神にご相談ください。資格を持った特殊清掃士が対応し、クリーニングだけでなく、部屋を汚す原因となるゴミや、使えなくなった家具や布団の回収も行います。手間をかけずにスムーズに部屋をきれいにすることが可能です。急ぎの場合でも最短即日対応ができますので、早急に解決したい方にも安心です。
また、ゴミ屋敷バスター七福神はゴミ屋敷や汚部屋の掃除をはじめ、細やかなハウスクリーニングまで幅広く対応する不用品回収業者です。業界最安値を目指している当社では、価格交渉も受け付けています。料金が気になる方は、まずはお気軽にお問い合わせください。




